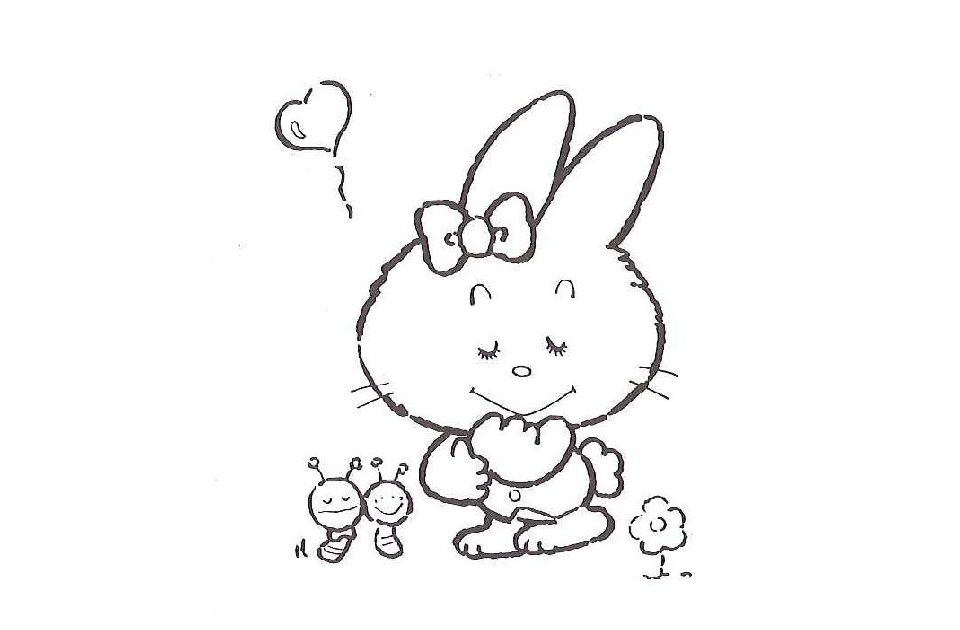|
自分が、いままさに死にゆかんとしていることを知らないままに死んでいく人間などいないと、ぼくは思う。そうでなければ、人間が死ぬ必要などどこにもないではないか。人間は、そのことを思い知るために、死んでいくのだ。
寒い朝、ぼくは草間からの電話で起こされた。「新聞に、あの絵のことが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
|
主は語っていた。「用事が済んだら、ちゃんと返しとくのがルールやて言うたやろ。志水がいつまでも返さへんから、こんなことになったんや」と草間はそれほど
ぼくはニ、三日、落ち着かない日を過ごした。「星々の悲しみ」から、出来るだけ遠ざかっていたかった。だが、そうなるといっときも早く、絵を持ち主に返してしまいたくて仕方がないようになってしまった。ぼくは意を決して、妹の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | ||
|
「
「この絵、もっとほかの題がついていたら、何でもないただの絵かも知れへんなァ」――絵はいつになく光っていた。 (宮本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | ||
□□□□□□□□□□□□□□