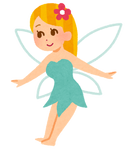すみひなさん、こんにちは。今回の作文について拝読しました。行列がどのように社会的
秩序や効率性に
影響を
与えるか、というテーマで非常に興味深い内容でした。まず、行列の社会的意義を
掘り下げた点が非常に良かったです。
例えば、日本と他国の行列に対する態度の
違いを具体的な例で説明している点が理解しやすかったです。また、デジタル社会における「行列」の
概念への
言及は、現代的な視点が加わっていて
新鮮です。
作文の中で、行列を守ることの重要性を説くために、具体的なデータを引用している点も素晴らしいです。「富士山の2024年の登山者数は約21万人…」といった部分は、実際の数字を用いることで説得力を増しています。さらに、日常生活での行列の例(信号、レストランのチケット
購入等)を挙げることで、読者が自身の経験と照らし合わせやすくなっています。
ただ、一部で日本人が信号を守らない場合もあるとの
指摘は、議論を呼ぶかもしれませんが、多角的な視点を提供するために有効な記述です。
「石橋を叩いて
渡る」の故事が、この作文にはピッタリだと思います。行列を通じて、用心深く社会的ルールを守る行動につながるからです。
◎データがよく書けています。「富士山の2024年の登山者数は約21万人なのだがその中で、
途中でルールを守らなかったことが原因でトラブルが発生した割合は、30%に上った。」
語彙力評価:
-字数が1200字以上書けています。
-表現豊かな言葉がよく使われています。
| 作文字数1303字 |
 |
| 目標字数1200字 |
| 総合点 82 点 |
| 思考語彙 71 点 |
| | 

| 表
現
語
彙
89
点
|
| 知識語彙 86 点 |
■思考語彙 41種 0個 (種類率INF%) 71点
かまわざる,も同様,なじむはず,防ぐため,保つため,と考える,ことによって,なかったら,したら,。しかし,いない,、必ずしも,限らない,守らない,みると,守らない,ないたら,したら,上ったら,なければ,だったら, 確か,並ばない,あるかも,しれない,。しかし,は単に,はない,するため,。つまり,もいえ,。例えば,うと,開けない,いない,はない,と思っ,と思っ,、例えば,はない,これにより,
■知識語彙 67種 0個 (種類率INF%) 86点
一種,不可欠,不可能,事務,事務所,事故,人数,人気,信号,先客,入場,全員,処理,割合,午前,原因,同様,周囲,商品,場合,場所,大切,大勢,大変,富士山,役所,役目,日本人,時刻,時間,死亡,水族館,注文,海外,混乱,火災,物事,物理,状況,現代,現象,理由,発想,発生,登山,監視,目的,社会,秒針,秩序,腕時計,自分,行列,話題,賛成,購入,赤信号,近代,途中,道路,達成,重視,長蛇,開店,青信号,順番,高速,
■表現語彙 127種 0個 (種類率INF%) 89点
いくつ,お互い,こと,これ,さ,せい,そう,そこ,たび,ため,とき,ところ,の,はず,もの,やり方,よう,わけ,アクセス,アラブ,オンライン,ギリシャ,スムーズ,スーパー,チケット,ディズニーランド,デジタル,トラブル,ドア,ヒーロー,ポスター,ルール,レストラン,一種,万,上,不可欠,不可能,中,事務,事務所,事故,人,人数,人気,例,信号,先客,入場,全員,処理,分,列,前,割り込み,割合,午前,原因,右,同様,周り,周囲,商品,場合,場所,大切,大勢,大変,好き,富士山,左,年,役所,役目,数,日本人,早め,時,時刻,時間,死亡,水族館,注文,海外,混乱,火災,物事,物理,状況,現代,現象,理由,発想,発生,登山,的,監視,目,目的,確か,社会,私,秒針,秩序,者,腕時計,自分,行列,話題,誰,賛成,購入,赤信号,車,近代,途中,道路,達成,重視,長蛇,開店,青信号,順番,高速,%,1つ,2つ,
■経験語彙 39種 個 (種類率INF%) 82点
いえる,かまう,さばく,しまう,しれる,そろう,とる,なじむ,られる,れる,わかる,上る,並ぶ,乱れる,保つ,出る,増える,守る,待つ,招く,挙げる,捉える,曲がる,果たす,根ざす,止まる,立てる,答える,続ける,縛る,考える,見張る,買う,起こる,進む,開ける,防ぐ,限る,集まる,
■総合点 82点
■均衡点 3点
日本のルール
中1 すみひな(sumihina)
2025年12月4日
行列は、民主主義社会の平等性に特有の現象である。身分制社会では性差や人種差がある場合、どんな場合でも先着順が基本となってしまう。しかし、日本人はきちんと並んで物事を進める。行列は用件を一つずつ片付けるという近代的事務処理の発想に根ざしているのだ。行列についての海外の例としてギリシャを挙げてみよう。ギリシャの役所や事務所では先客にかまわず、処理しやすいものから答えていくというやり方をとることが多いそうだ。アラブ社会も同様だそうだ。このような社会に行列がなじむはずがない。もし並んだとしても、割り込みを防ぐため、お互いを監視しているのだそうだ。まるで、スーパーヒーローのように周りを見張り続ける役目を果たすわけだ。私は、行列を守ることが社会的秩序を保つために不可欠であると考え、賛成する。
1つ目の理由は、行列などのルールを守ることによって物事がより早く、スムーズに進むからだ。高速道路などの大きい道路などには信号がいくつもある。左に曲がったり右に曲がったりするたびに青信号を待つ車はどんどん増えていく。これがもし、信号がなかったらどうなるだろう。秩序が大きく乱れてしまう。事故のせいで火災が起こったり死亡者が出たりしてしまったりしたら大変だ。だからこそ、赤信号をしっかり守ろう、というポスターが立ててあったりするのだ。人気のレストランや話題になっている水族館のチケットを買う場合もそうだろう。しかし、細い道路で周囲に誰もいない状況で赤信号の場合、必ずしも日本人全員が、そこで止まるとは限らない。
2つ目の理由は、ルールを守らない人がいると混乱してしまうからだ。富士山を挙げてみると秩序の大切さがよくわかる。富士山の2024年の登山者数は約21万人なのだがその中で、途中でルールを守らなかったことが原因でトラブルが発生した割合は、30%に上った。登山は行列ではないが、ルールを守る例として秩序の大切さがわかるだろう。また、ディズニーランドの2024年の入場者数は1510万人だ。これも、行列がなければ混乱を招き、これほどの人数をさばくことは不可能だっただろう。
確かに、待つときに並ばなくていい時もあるかもしれない。しかし、行列は単に目的もなく並んでいるわけではなく、自分の目的を達成するために並んでいるのである。つまり、行列とは自分と同じ目的の人が大勢集まっているところともいえる。例えば、ダイマルは午前10時から開店するのだが長蛇の列があろうと、1分前であっても、秒針がそろって時刻が来るまでドアを開けない。腕時計をじっと見ていないで少しくらい早めでもいいのではないかと思ってしまうが、秩序を守るのが好きな人がいるからこのような現象が起こるのだと思う。また、現代のデジタル社会においては、例えばオンラインでのチケット購入や商品の注文も一種の行列として捉えられることがある。この場合、物理的な場所で並ぶのではなく、時間やアクセスの順番が重視される。これにより、場所に縛られることなく、デジタル上でも秩序が保たれているのだ。