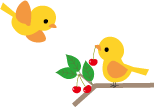あえみもさん、作文の
提出ありがとうございます。
あなたの作文は、科学や歴史、コミュニケーション
技術の進化といった
多岐にわたるテーマを
扱っており、それぞれの分野についての
理解が深いことが伝わってきます。
特に、科学の部分では「自由な心で科学を
論じる」という
表現が、研究の進歩には
柔軟な思考が必要であることをよく表していて
素晴らしいです。
また、コミュニケーション
技術の変化については、
過去と
現在を
比較しながら、
技術の進化がどのように
私たちの生活に
影響を
与えているかを具体的に
述べていて、
理解しやすいです。
歴史の学び方に関しても、「イイクニ作ろう
鎌倉幕府」という
語呂合わせを例に挙げることで、
記憶の工夫を具体的に
示し、歴史
解釈の
変遷をうまく説明しています。
さらに、ピアノの話題を取り入れて、自分の
興味から学びを深めることの大切さを
述べる部分も印象的でした。
全体を通して、あなたの
好奇心と学ぶ
意欲が感じられる作文で、読んでいて楽しく思いました。
これからも様々な分野に
興味を持ち、深く
探求していく
姿勢を大切にしてください。
【
項目評価】
-
内容の
豊富さ:★★★★☆
-
表現の工夫:★★★★☆
-テーマへの
理解:★★★★★
-読みやすさ:★★★★☆
「まるで自然の
姿の一部をかじっているよう」というたとえがうまく使われています。
森リン評価 格物致知 ne 03月3週 あえみも字数/基準字数:
961字/1000字
思考点:58点
知識点:78点
表現点:73点
文化点:82点
総合点:72点 | ●語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 文化点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
●語彙の説明| 語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
|---|
| 思考語彙 | | 18個 | | 58点 | 考える言葉です。
理由、方法、原因などの説明の語彙。
多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。
|
| 知識語彙 | 55種 | 87個 | 63% | 78点 | 難しい言葉です。
社会的な例や調べた例の語彙。
多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。
|
| 表現語彙 | 96種 | 155個 | 62% | 73点 | 豊かな言葉です。
話題の幅が広い語彙。
多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。
|
| 文化語彙 | 39種 | 53個 | 74% | 82点 | 詳しい言葉です。
身近な例や経験した例の語彙。
多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。
|
| 種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
961字
 | | 58点
 | | 78点
 | | 73点
 | | 82点
 |
| 字数 | | 思考語彙 | | 知識語彙 | | 表現語彙 | | 文化語彙 |
■思考語彙 15種
。考える,あるかも,いると,ことによって,たどると,だろう,とらわれざる,と思う,と言える,ないので,なければ,のかも,作ろう,大切かも,覚えるため,
■知識語彙 55種
一部,不便,事実,原型,史実,問題,変更,大切,大陸,学問,学術,学説,定義,対面,小学校,幕府,成立,成長,手段,手紙,技術,提唱,教科書,早急,時代,普及,格物致知,構造,歴史,生活,用語,発展,発見,社会,科学,移動,習得,習慣,自分,自然,自由,自身,見方,観察,角度,解釈,誕生,起源,追及,連絡,進化,進歩,鎌倉,電報,電話,
■表現語彙 96種
こと,さ,そこ,それ,たくさん,たち,もと,もの,よう,インターネット,クニ,コミュニケーション,ピアノ,メール,一つ,一部,不便,事実,今,何,力,原型,史実,問題,変更,大切,大陸,姉,姿,学問,学術,学説,定義,対面,小学校,幕府,年,弦,当たり前,後,心,成立,成長,手段,手紙,技術,提唱,教科書,数,新た,早急,昔,時代,普及,格物致知,構造,歴史,父,生活,用語,界,発展,発見,社会,私,科学,秒,移動,習得,習慣,考え方,者,自分,自然,自由,自身,見方,覚えるため,観察,角度,解釈,誕生,語呂合わせ,説,起源,追及,連絡,進化,進歩,道,違い,鎌倉,電報,電話,音,頃,
■経験語彙 40種
。考える,かじる,くれる,こだわる,しまう,しれる,すぎる,たどる,つながる,できる,とらわれる,と思う,と言える,ぶつける,もつ,やる,られる,れる,わかる,争う,伝える,伝わる,作る,優れる,出来る,取り入れる,呼ぶ,変える,弾く,感じる,教える,生まれる,知る,究める,続く,覚える,認める,調べる,論じる,鳴る,
格物致知
小5 あえみも(aemimo)
2025年3月3日
科学は何もかも知っているのではなく、ほんの自然の姿の一部をかじっているのにすぎないので、いろいろと角度を変えて自然を見ているとつぎつぎと新しい発見が生まれてくる。そこから新しい学説が発展し、それをもとにしてまた優れた技術が誕生するといったことがこれからも続いていくのである。ウェーゲナーは大陸移動説を提唱した。実際に大陸が移動するのだということが事実として認められるようになり、こだわらない自由な心で科学を論じるというのも一つの進歩の道と言えるのである。自由な観察力や考え方を科学者や科学界にぶつけて思いがけない進歩が生まれるということがあるかもしれない。
コミュニケーションの技術の進化が大きな違いだと言える。昔は対面でしか伝えられないことがほとんどで電話や手紙での連絡手段しかなかった。早急に伝えなければならないのは電報という手段しかなかった。私は手紙で伝えるということがとても不便に感じてしまう。今はメールやSNSで数秒後には伝わっていて、インターネットの普及は当たり前のように生活に取り入れられているのである。古いものにとらわれずに新しも見方をすることが大切かもしれないが、古い時代の生活習慣もその時代は不便さを感じていなかったのかもしれない。
父に社会の教科書で小学校の頃、鎌倉幕府の成立年を覚えるために「イイクニ(1192)作ろう鎌倉幕府」という語呂合わせで覚えた。今は1185年が鎌倉幕府の成立年に変更されたと姉が教えてくれた。「鎌倉幕府の成立年」は歴史の史実を争っているのではなく、学術用語として「鎌倉幕府」と呼ぶには何をもって鎌倉幕府と定義できるのか、という歴史の解釈の問題なのだということだ。
格物致知というように私たちは自分の学問を究めて追及し発見することが大切だということがわかった。考えたことを深く調べることによって今まで知らなかったことを発見することが出来る。ピアノを弾いているとどうやって音が鳴っているのだろう、ピアノの構造はどうなっているのだろうとピアノの弦を知りたくなる。それをたどるとピアノの起源やピアノの原型がクラヴィコードであり、もっと知りたいと思うことがたくさんある。発見が新たな自分自身の成長にもつながることを習得できた。