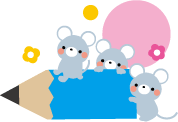わてひさん、こんにちは。あなたの作文を拝読しました。
まず、社会問題をテーマに
据えた
選択が素晴らしいです。現代社会において、テクノロジーがもたらす便利さとその裏に
潜む問題点を考察することは非常に重要です。あなたは、「使いにくいのは機械のほうが悪い」という主張を明確に展開しており、読者に対して強いメッセージを投げかけています。社会問題の主題がよく書けています。
また、複数の原因を挙げてその問題を
深堀りしている点も評価できます。特に、多機能でありながら使いこなせないスマートフォンの例や、
高齢者が操作に苦労する最新家電の話は、具体的で説得力があります。原因がよく書けています。
さらに、名言を引用して、あなたの論点を強化しているのも印象的でした。「人間の歴史は簡単に作られてきたのではなく、複雑に作られてきたのである」という言葉は、テクノロジーの進化が必ずしも人間にとって最良ではないことを強調しています。名言がよく書けています。
この作文は、現代社会のテクノロジー
依存を問題視し、人間本来の役割とテクノロジーの適切な位置づけを考える良いきっかけを提供しています。さらなる研究や思考の発展に期待しています。素晴らしい
洞察をありがとう。
【
項目評価】
-社会問題の主題がよく書けています。
-原因がよく書けています。
-名言がよく書けています。
森リン評価 社会は本質的に nnga 06月2週 わてひ字数/基準字数:
1366字/600字
思考点:85点
知識点:87点
表現点:83点
経験点:85点
総合点:94点
均衡点:9点
| ●語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
1200字換算:
思考点:点
知識点:点
表現点:点
経験点:点
総合点:点
均衡点:9点
| ●換算語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
●語彙の説明| 語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
|---|
| 思考語彙 | 23種 | 26個 | 88% | 85点 | 考える言葉です。
理由、方法、原因などの説明の語彙。
多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。
|
| 知識語彙 | 71種 | 134個 | 53% | 87点 | 難しい言葉です。
社会的な例や調べた例の語彙。
多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。
|
| 表現語彙 | 122種 | 202個 | 60% | 83点 | 豊かな言葉です。
話題の幅が広い語彙。
多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。
|
| 経験語彙 | 44種 | 69個 | 64% | 85点 | 詳しい言葉です。
身近な例や経験した例の語彙。
多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。
|
| 種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
1366字
 | | 85点
 | | 87点
 | | 83点
 | | 85点
 |
| 字数 | | 思考語彙 | | 知識語彙 | | 表現語彙 | | 経験語彙 |
■思考語彙 23種 26個 (種類率88%) 85点
たしかに, 第,。しかし,。たとえば,。だからこそ,。例えば,あるべき,すぎざる,そのため,だろう,なければ,なると,は言える,れるべき,使いこなせざる,助けるはず,姿勢こそ,気づけば,言わざる,誰にとって,進化によって,運ぶため,間違えれば,
■知識語彙 71種 134個 (種類率53%) 87点
主導,主役,事実,交換,人間,仕事,他人,使用,便利,偶然,利便,利用,制限,前提,効率,勉強,十分,原因,名言,問題,場面,大切,姿勢,存在,家電,専門,影響,役割,必要,思考,意見,搭載,操作,支援,文化,方法,早急,時間,最初,最新,本末転倒,本来,機器,機能,歴史,深刻,混乱,現代,生活,睡眠,社会,節約,簡単,自分,荷物,行動,製品,複雑,設定,設計,証左,説明,講習,進化,道具,適応,都合,長者,電子,電話,高齢,
■表現語彙 122種 202個 (種類率60%) 83点
あまり,おかげ,おろそか,くらし,こと,これ,しだい,そのため,そのもの,それ,それら,たくさん,はじめ,ほう,もの,やり方,よう,わけ,わらしべ,ストレス,スマート,フォン,ボタン,ルール,一,一つ,主導,主役,事実,二,交換,人,人々,人間,仕事,仕組み,他人,何,使い方,使用,例,便利,偶然,利便,利用,制限,前提,助けるはず,効率,勉強,十分,原因,名言,問題,場面,多く,大切,姿勢,存在,家電,専門,度,影響,役割,必要,思考,性,意見,手助け,搭載,操作,支援,文化,方,方法,早急,時間,書,最初,最新,本,本末転倒,本来,権,機器,機能,歴史,深刻,混乱,点,物,現代,生活,睡眠,社会,節約,簡単,者,自分,荷物,行動,製品,複雑,設定,設計,証左,説明,誰,講習,車,逆,進化,運ぶため,道具,遠く,適応,都合,長者,電子,電話,面,高齢,
■経験語彙 44種 69個 (種類率64%) 85点
あきらめる,あわせる,うばう,える,かけ離れる,しばる,しまう,すぎる,つくる,できる,は言える,られる,れる,上がる,与える,作る,使いこなせる,使う,使える,助ける,受ける,合わせる,変える,学ぶ,役立つ,得る,感じる,戸惑う,持つ,振り回す,気づく,求める,生み出す,直す,続ける,見つめる,見受ける,見直す,話せる,読み直す,追い求める,運ぶ,間違える,関わる,
■総合点 94点
■均衡点 9点
社会は本質的に
高2 わてひ(watehi)
2025年6月2日
コンピュータをはじめとする複雑な機械が使いにくいのは、利用者の能力の問題ではなく、機械やそれを作る側に問題がある。技術は本来、人間のためにあり、誰もが直感的に使えるものであるべきだ。にもかかわらず、今の社会では「使えない人が悪い」とされがちで、使いづらい製品があふれている。これを変えるには、「使いにくいのは機械のほうが悪い」と言える文化をつくる必要がある。道具は人間に従い、人間を支援するものでなければならない。道具に振り回される社会は本末転倒であり、人間が主導権を持つ姿勢こそが求められている。
道具に振り回される社会には深刻な問題がある。現代社会において、誰にとっても使いやすく、真に役立つ道具とは何かを改めて見つめ直す必要がある。大きな原因の一つは、利便性を追い求めるあまり、真に必要とは言えない多機能な道具を次々と生み出してきた点にある。例えば、スマートフォンには数多くのアプリや機能が搭載されているが、それらを十分に使いこなせず、かえって混乱やストレスを感じる利用者も少なくない。また、最新の家電製品には複雑な操作方法や多くのボタンがあり、高齢者をはじめとする利用者が戸惑い、使用をあきらめてしまう例も見受けられる。これは本来、人間の生活を助けるはずの道具が、逆に人間の行動や思考を制限するようになっている証左である。人間が道具に適応しなければならない社会は、本末転倒と言わざるを得ない。
第二の原因として、「道具のほうに人間が合わせる」ことを前提として設計された製品が多く存在するという問題がある。人間が主役であるべきなのに、気づけば道具の都合にあわせて行動する社会になってしまっている。「わらしべ長者」は最初は一本のわらしべだったが、長者になるまでには偶然や他人の都合に合わせることで物を交換し続けていた。現代の人々もまた、道具の持つ機能や仕組みに合わせて自分のやり方を変え、学び直さなければならない場面が多い。たとえば、電子機器の設定や操作方法が複雑で、説明書を何度も読み直したり、専門の講習を受けたりしないと使えないことがある。それは本来の道具の役割、「人間を助ける存在」からかけ離れている。このような社会は早急に見直されるべきである。
たしかに、道具のおかげで生活が便利になったことは事実である。重い荷物を運ぶための車、遠くの人と話せる電話、時間を節約できる家電など、人間のくらしを助ける道具はたくさんある。さらに、道具の進化によって仕事の効率が上がり、より多くのことができるようになったという面もある。そのため、「道具に振り回される」というのは人間の使い方しだいであり、道具そのものが悪いわけではないという意見もあるだろう。しかし、「人間の歴史は簡単に作られてきたのではなく、複雑に作られてきたのである。」という名言がある。どんなに便利なものであっても、使い方を間違えれば本末転倒である。たとえば、スマートフォンは便利だが、使いすぎて勉強や睡眠がおろそかになると、かえって生活に悪い影響を与えてしまう。道具はあくまで人間の手助けをするものにすぎず、人間が道具のルールにしばられたり、時間をうばわれたりする社会は望ましくない。だからこそ、道具との関わり方を見直すことが大切なのである。