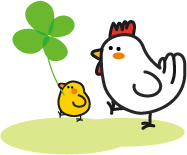あえたしさん、今回の作文は
非常に
興味深く、多くの重要なポイントを上手く
表現できています。
まず、作文のテーマについて、多様な文化の中での「物の見方」や「考え方」に
焦点を当てている点が
素晴らしいです。
このテーマを通じて、あえたしさん自身の
経験や学びを
反映させながら、読者に対しても思考の
余地を
与えています。
また、具体的なエピソードを用いることで、テーマがより身近で
理解しやすくなっています。
特に、給食での食べ方に関するエピソードや、
美術館でのダリの絵画についての体験は、文化の
違いがもたらす
影響を具体的かつ生動的に
示しており、
効果的です。
さらに、絵画の
解説を読んだ後に感じた変化を
描写する部分では、
知識がどのように
私たちの
認識を変えるかをうまく表しています。
この部分からは、あえたしさんが新しい
情報を受け入れ、自身の
見解を
柔軟に
変更できる様子が伝わってきます。
終わりに向けての
結論も、自分の考えが
絶対ではないという学びをしっかりと読者に伝えることができていて、作文全体のまとまりとしても
非常に良いです。
以下は
項目評価です:
-たとえがうまく使われています
-前の話聞いた話がよく書けています
-書き出しの結びがよく書けています
この作文は、
自己の成長と文化
理解の深まりを見事に
表現しているため、大変
素晴らしい作品だと感じます。
森リン評価 角度を変えて世界を見ると na 06月3週 あえたし字数/基準字数:
1025字/500字
思考点:62点
知識点:66点
表現点:69点
経験点:73点
総合点:73点
均衡点:6点
| ●語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
1200字換算:
思考点:71点
知識点:75点
表現点:79点
経験点:81点
総合点:77点
均衡点:6点
| ●換算語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
●語彙の説明| 語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
|---|
| 思考語彙 | 14種 | 20個 | 70% | 62点 | 考える言葉です。
理由、方法、原因などの説明の語彙。
多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。
|
| 知識語彙 | 41種 | 53個 | 77% | 66点 | 難しい言葉です。
社会的な例や調べた例の語彙。
多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。
|
| 表現語彙 | 90種 | 151個 | 60% | 69点 | 豊かな言葉です。
話題の幅が広い語彙。
多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。
|
| 経験語彙 | 36種 | 64個 | 56% | 73点 | 詳しい言葉です。
身近な例や経験した例の語彙。
多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。
|
| 種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
1025字
 | | 62点
 | | 66点
 | | 69点
 | | 73点
 |
| 字数 | | 思考語彙 | | 知識語彙 | | 表現語彙 | | 経験語彙 |
■思考語彙 14種 20個 (種類率70%) 62点
、きっと,。例えば,いると,だから,だろう,でもなぜ,として思う,とっと,と思う,と考える,みると,入れば,知らざる,見ると,
■知識語彙 41種 53個 (種類率77%) 66点
一目,不潔,今度,以前,印象,友達,右手,固執,場所,大切,学校,家族,対比,左手,帰化,年生,文化,日本人,昆虫,時計,時間,流動,現実,理解,生物,直接,知識,空間,給食,絵画,絶対,美術館,習慣,自分,表現,見方,解説,記憶,象徴,雑音,食器,
■表現語彙 90種 151個 (種類率60%) 69点
あなた,おにぎり,がらくた,こと,これ,ごはん,ご飯,さ,とき,どこ,なん,ぼく,みんな,もの,よう,ら,わけ,アリ,インド,ダメ,ダリ,マナー,一,一目,不潔,人,今度,以前,全て,印象,友達,口,右手,固執,場所,声,大切,好き,子ども,学校,家,家族,対比,左手,帰化,年生,心,性,手,文化,方,日本人,昆虫,時計,時間,机,椀,死,気,流動,現実,理解,生物,的,直接,知識,空間,箸,給食,絵,絵画,絶対,美術館,習慣,考え,考え方,肉,自分,落書き,表現,見方,解説,記憶,謎,象徴,郷,隣,雑音,食,食器,
■経験語彙 36種 64個 (種類率56%) 73点
あわてる,いれる,おく,おこる,できる,として思う,とらえる,とる,と思う,と考える,ひく,ひろいあげる,まるめる,られる,れる,使う,入る,入れる,分かる,変える,変わる,始める,従える,感じる,書く,溶ける,知る,笑う,聴こえる,落ちる,言い聞かせる,追い出す,違う,間違う,限る,食べる,
■総合点 73点
■均衡点 6点
角度を変えて世界を見ると
小5 あえたし(aetasi)
2025年6月3日
コオロギの声は、日本人には美しく聴こえるが、ヨーロッパ人には雑音として聴こえるといわれている。アオマツムシの声も、帰化昆虫だということを知ってからうるさく聴こえるようになった。知識や習慣は、ものの見方を変える。自分のものの見方や考え方が絶対のものだと思わないことが大切だ。
一年生のときのことだ。学校で給食を食べていると、肉がぽとっと机に落ちた。「もったいな」とぼくはあわてて手でひろいあげて口に入れた。すると隣の友達が「汚いわね、手を使わないで。あなたインド人なの」とおこった。
ぼくは恥ずかしくなって、今度は絶対手で食べないぞと自分に言い聞かせた。
でも、はたして「手で食べる」ことは絶対にダメなことだろうか。
インドでは「手食」の文化があって、みんな右手でご飯を食べる。左手は不潔な手として思われていて、また食器を使うことも一度使った食器を使うことは汚いことと考えられているのだ。
もし日本人がインドに行って、インドの文化を知らずに、友達の家にいって箸を使って食べ始めたら、きっとインドの人に追い出されるだろう。郷に入れば郷に従えだ。
しかも、ぼくは手で直接食べた方がおいしく感じる。例えば、おにぎりだ。ごはんをまるめてお椀にいれて箸で食べるより、手を使っておにぎりを食べた方が温かさが感じらるし、ずっと食べやすくて美味しいのだ。
だから、ぼくはマナーや習慣が違うだけで、手で食べることは絶対にダメだとは限らないと考えた。
以前、家族で美術館に行ったとき「ダリ」の絵画を見たことがある。「記憶の固執」という、どこか分からない場所に、がらくたのように溶けた時計がごちゃごちゃおかれているだけの絵だ。ぼくは一目見ると「なんだこれは、子どもの落書き」と笑った。でもなぜか、とても心をひかれた。
絵の解説を見ると、「柔らかいもの」と「硬いもの」の対比していること、白い謎の生物はアリで「死」の象徴であること、時間の流動性と超現実的な空間の表現していると書いてあった。そう言われてみると、落書きだと思っていたダリの絵も、少し理解できたような気がした。
全てのことは、とらえ方が違うだけで、印象や考えも変わるということが分かった。
自分が「好きではない」「間違っている」と思うことでも、絶対自分が正しいわけではないと考えた。