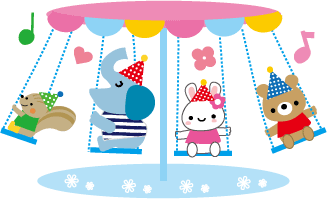あえらてさん、今回の作文は、人間と他の大型
哺乳類との
比較を通して、学習の重要性というテーマを深く
掘り下げることができています。
特に、サルと人間の学習能力に
焦点を当てた部分は、具体的な例を交えながら非常にわかりやすく説明されています。
また、文中で「人は食べるために生きるのではなく、生きるために食べるのである」ということわざを引用することで、人間の生活が単なる生存以上の意味を持つことを効果的に表しています。
この引用は、作文の主張をより強調し、読者に深い印象を
与える要素となっています。
学習する重要性を論じながらも、人間の文化や社会の発展がどのように学習によって支えられているかを示すことで、学習の社会的な側面も見事に
描かれています。
全体を通して、情報が整理されており、論理的に展開されているので、読みやすい作文となっています。
あえらてさんがこれからもこのような
洞察に富んだ作文を書き続けることを期待しています。
#
項目評価
-ことわざがよく書けています
-
一般化の主題がよく書けています
-書き出しの結びがよく書けています
森リン評価 学習 ma 05月2週 あえらて字数/基準字数:
1260字/600字
思考点:82点
知識点:94点
表現点:86点
経験点:64点
総合点:80点
均衡点:-1点
| ●語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
1200字換算:
思考点:点
知識点:点
表現点:点
経験点:点
総合点:点
均衡点:-1点
| ●換算語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
●語彙の説明| 語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
|---|
| 思考語彙 | 22種 | 26個 | 85% | 82点 | 考える言葉です。
理由、方法、原因などの説明の語彙。
多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。
|
| 知識語彙 | 81種 | 149個 | 54% | 94点 | 難しい言葉です。
社会的な例や調べた例の語彙。
多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。
|
| 表現語彙 | 129種 | 239個 | 54% | 86点 | 豊かな言葉です。
話題の幅が広い語彙。
多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。
|
| 経験語彙 | 30種 | 43個 | 70% | 64点 | 詳しい言葉です。
身近な例や経験した例の語彙。
多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。
|
| 種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
1260字
 | | 82点
 | | 94点
 | | 86点
 | | 64点
 |
| 字数 | | 思考語彙 | | 知識語彙 | | 表現語彙 | | 経験語彙 |
■思考語彙 22種 26個 (種類率85%) 82点
n第,。いわば,。つまり,。例えば,あろう,いるため,これにより,これに対して,すると,ないから,のに対し,はむしろ,は単なる,は単に,も可能,役に立つから,生きるため,生存にとって,維持にとって,能力こそ,言えば,食べるため,
■知識語彙 81種 149個 (種類率54%) 94点
人生,人間,仲間,体型,便利,促進,個体,創造,動物,区別,危険,名言,向上,哺乳類,回避,基盤,変化,外界,多様,大切,大型,存続,学習,容易,対応,強化,役割,必要,意味,成長,技術,敏捷,文化,方向,方法,有意義,本能,条件下,柔軟,水中,活用,特徴,特性,特殊,状況,理由,環境,生存,生活,生物,発展,発達,目的,知識,社会,種族,積極,筋肉,経験,結果,維持,繁栄,習得,能力,草食,行動,要因,解放,身体,追求,進化,過程,適応,遺伝,重要,限定,陸上,集団,雑食,非常,食料,
■表現語彙 129種 239個 (種類率54%) 86点
いるため,いろいろ,おしまい,こと,これ,これら,それ,つき,ところ,もの,も可能,よう,クジラ,サル,トラ,ライオン,一,上,下,中,二,人,人生,人間,仕組み,他,仲間,体型,便利,促進,個体,創造,力,動物,化,区別,危険,名言,向上,哺乳類,回避,基盤,場,変化,外界,多様,大切,大型,存続,学,学び,学習,容易,対応,強化,役割,必要,性,意味,成長,手,技術,敏捷,文化,方向,方法,有意義,本能,条件下,枠,柔軟,様々,水中,活用,点,爪,牙,特徴,特性,特殊,状況,獣,率,理由,環境,生きるため,生まれつき,生存,生活,生物,発展,発達,的,目的,知識,社会,種,種族,積極,筋肉,経験,結び,結果,維持,繁栄,習得,能力,草食,行動,要因,解放,豊か,身,身体,追求,進化,遊び,過程,適応,遺伝,重要,限定,陸上,集団,雑食,非常,食べるため,食料,餌,
■経験語彙 30種 43個 (種類率70%) 64点
うる,おる,せる,つく,できる,れる,付ける,備える,備わる,入る,入れる,加える,基づく,学ぶ,役に立つ,得る,持つ,探す,支える,果たす,比べる,求める,生きる,生まれつく,示す,言い換える,超える,限る,際立つ,食べる,
■総合点 80点
■均衡点 -1点
学習
中1 あえらて(aerate)
2025年5月2日
生物界の中でヒトという種を特徴づけてみると、優れた学習能力がほぼ一生にわたって維持される、ということが第一に挙げられるであろう。例えば、クジラやライオンのような大型哺乳類について言えば、クジラは水中生活に便利なように体型が変化しており、またライオンやトラは、筋肉が発達し、敏捷で、しかも鋭い牙や爪を備えている。したがって、ある環境条件下では餌を手に入れ、種族を維持していくことが容易である。反面、これらの大型哺乳類は、限られた環境下においてのみ繁栄しうる。クジラはもはや陸上で生活することはできないし、ライオンやトラは比較的大きな草食獣が手に入らなくなったらおしまいである。これに対して、サルの仲間は、そういった身体上の特徴を持っていない。さらにまた、生まれつきの行動の仕組みが比較的少なく、加えて雑食性でもあるところから、様々な環境に適応しうる。いわば、他の大型哺乳類が特殊化するという方向で進化してきたのに対し、サルの仲間はむしろ、環境に対する柔軟性において進化してきた、ということができるであろう。したがって、サルの仲間では、経験に基づいて外界についての知識を身に付けることが、個体の生存にとっても、また種の維持にとってもそれだけ重要になってくる。つまり、サルはもともと学習する種である、と言い換えることができる。
第一の理由は、人間は学習しないと成長しないからである。人間は、他の大型哺乳類に比べ身体的な適応能力が限定されているため、知識や技術を習得することで環境に適応する必要がある。生物学的な進化はその過程で学習の重要性を際立たせ、特に人間のような種においては、この学習の能力が文化や社会の発展を支える基盤となった。学習を通じて得た知識は、個体の生活を支えるだけでなく、集団としての存続や繁栄をも可能にしているのだ。
第二の理由は、学習するといろいろなことが身につき、役に立つからだ。例えば、サルの仲間は環境の変化に柔軟に対応する能力を持っているが、それは単に遺伝的な要因だけではなく、経験を通じて新しい知識や技術を習得する力によるものだ。これにより、食料を探したり、危険を回避する方法を学んだりすることができ、結果として個体の生存率が向上する。他の動物には生まれつき備わっている本能的な行動の枠を超えて、多様な状況に適応する能力を持つ点で、学習は非常に重要な役割を果たしているのだ。
この学習する能力こそが、人間を他の大型哺乳類やサルの仲間と区別する重要な特性である。「人は食べるために生きるのではなく、生きるために食べるのである」という名言が示すように、人間の人生は単なる生存の追求だけではなく、より深い意味や目的を求めるものだ。その中で、遊びも重要な役割を果たす。遊びは創造性を解放し、学びを促進し、社会的な結びつきを強化する場となる。人間がもともと持つ学習する能力を大切にし、それを積極的に活用することで、人生は単なる生存の枠を超えて、豊かで有意義なものへと発展していくのである。