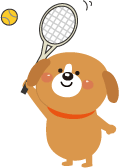あきひろさん、作文を読ませていただきました。
まず、
昆虫と鳥の食生活の
違いから始まる
導入部は、
興味深い視点を
提供しており、読み手の注意を引くのに成功しています。
また、
過去の
経験と
現在の観察を
織り交ぜることで、テーマに対する深い
理解と
個人的な関連付けが見られました。
特に、カイコの話では、先生のエピソードを交えることで話が生き生きとしており、読む側にもその場の
雰囲気が伝わってきます。
「かわいい子には旅をさせよ」ということわざを用いて、命の重みや成長についての考察を深める部分は、
感慨深いものがあります。
食に対する
子供と大人の感覚の
違いについても、具体的な例を挙げながら説明しており、
理解を助けています。
全体を通して、さまざまな食べ物へのチャレンジを
促すポジティブなメッセージが伝わってきて、とても心地よい結びになっていると感じます。
たとえがうまく使われています。
前の話聞いた話がよく書けています。
ことわざがよく書けています。
わかったことがよく書けています。
書き出しの結びがよく書けています。
森リン評価 ポトリポトリ ni 07月4週 あきひろ字数/基準字数:
1316字/700字
思考点:67点
知識点:63点
表現点:72点
経験点:70点
総合点:75点
均衡点:7点
| ●語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
1200字換算:
思考点:点
知識点:点
表現点:点
経験点:点
総合点:点
均衡点:7点
| ●換算語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
●語彙の説明| 語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
|---|
| 思考語彙 | 16種 | 16個 | 100% | 67点 | 考える言葉です。
理由、方法、原因などの説明の語彙。
多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。
|
| 知識語彙 | 37種 | 45個 | 82% | 63点 | 難しい言葉です。
社会的な例や調べた例の語彙。
多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。
|
| 表現語彙 | 97種 | 145個 | 67% | 72点 | 豊かな言葉です。
話題の幅が広い語彙。
多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。
|
| 経験語彙 | 34種 | 45個 | 76% | 70点 | 詳しい言葉です。
身近な例や経験した例の語彙。
多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。
|
| 種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
1316字
 | | 67点
 | | 63点
 | | 72点
 | | 70点
 |
| 字数 | | 思考語彙 | | 知識語彙 | | 表現語彙 | | 経験語彙 |
■思考語彙 16種 16個 (種類率100%) 67点
。だから,。だからこそ,あるらしい,いえば,くると,しまう場合,たので,たまらざる,だろう,でどうして,と思う,について考える,みると,よると,子どもにとって,感じるから,
■知識語彙 37種 45個 (種類率82%) 63点
世話,以上,体験,元気,先生,印象,友達,反応,味覚,夢中,大人,学者,必要,悲鳴,意味,成長,挑戦,敏感,教室,最初,本能,栄養,理由,理科,生徒,真剣,経験,結果,絵本,自分,自然,苦味,苦手,表情,言葉,酸味,防衛,
■表現語彙 97種 145個 (種類率67%) 72点
いろいろ,おなか,おまえ,がち,きっかけ,こと,これ,さまざま,しまう場合,そう,その後,それ,たくさん,たち,とき,にこにこ,ぼく,みんな,もの,よう,ん,アオムシ,カイコ,キャベツ,チャット,テレビ,テンポ,ピーマン,ベテラン,世話,中,以上,体,体験,価,元気,先生,勢い,印象,友達,反応,周り,味,味覚,命,夢中,大人,大好き,嫌い,子,子ども,学者,年,心,必要,悲鳴,意味,成長,挑戦,敏感,教室,方,旅,時,最初,本能,栄養,桑,母,毒,気,理由,理科,生きもの,生徒,的,目,真剣,経験,結果,絵本,自分,自然,苦味,苦手,葉,表情,言葉,話,酸味,重み,間,防衛,食べ物,1つ,2つ,7つ,
■経験語彙 34種 45個 (種類率76%) 70点
あける,いきわたる,しまう,すう,せる,たまる,てる,できる,と思う,について考える,もらう,よる,られる,れる,わかる,上げる,入る,分かる,嫌う,思い込む,感じる,持つ,描く,教える,止む,残る,知る,続ける,聞く,話しかける,調べる,避ける,食べる,飼う,
■総合点 75点
■均衡点 7点
ポトリポトリ
小5 あきひろ(asiguru)
2025年7月4日
手作りの虫かごの中で、アオムシがキャベツの葉をすさまじい勢いで食べながら、緑色の丸い大きな糞をポトリポトリと落としていく様子を、ぼくは感心しながらながめていた。ほとんどの鳥は葉を食べない。ハクチョウのような大型の鳥をのぞいて、草食性の鳥は果実や穀物を食べることが多い。葉を食べるということは、栄養価の低いものを大量に摂取しなければならないことを意味している。それでは胃袋ばかり重くなり、空を飛ぶには不都合なのだ。昆虫は「変態」によって小さな体の短所をうまく解消してきた。昆虫の生き方は、そのサイズと密接に関わっているのだと思った。
小学3年生の頃、理科の授業でカイコを飼うという活動があった。ぼくには姉がいて、カイコの飼い方を教えてもらっていたので、カイコのことを自然とかわいく感じられた。理科の先生は、20年以上教えてきたベテランで、カイコについてとても詳しかった。先生は最初に教室に入ってくると、
「みんな大好きカイコを持ってきました〜!」
と、にこにこしながら言った。ですが嫌いな生徒もいて
「キャー」
と悲鳴を上げていた。ぼくは心の中でどうしてみんな大好きと言う必要があったのだろうとぎもんがあった。
悲鳴が止んだ時1テンポ間をあけて学者のような真剣な表情でこう続けた。
「カイコといえば『桑』。桑の葉は栄養価が低いけれど、おなかにたまらずたくさん食べることができる。だから、結果的に栄養が体にいきわたり、元気になるんだよ。」
そのとき、カイコたちはまるでウサイン・ボルトのような勢いで桑の葉を食べていた。思わずぼくは、
「おまえ、おなかすいてたんだろ〜」
と話しかけてしまった。
「かわいい子には旅をさせよ」という言葉がある。カイコの世話をする体験は、命の重みや生きものの成長について考えるきっかけになった。だからこそ、この言葉の意味が少しわかった気がした。
子どもはピーマンを嫌うことが多い。それは、母の話によると「子どもにとってピーマンの苦味は毒のように感じるから」だそうだ。実際にチャットGPTで調べてみると、理由は7つあるという。1つ目は、子どもは大人よりも味覚が敏感で、特に「苦味」や「酸味」に強く反応するということ。これは本能的な防衛反応でもあるらしい。
2つ目は、絵本やテレビで「ピーマン=まずいもの」として描かれることが多いこと。さらに、周りの大人や友達が「ピーマンが嫌い」と言っているのを聞いて、自分も嫌いだと思い込んでしまう場合もある。そして、初めて食べたときに苦いと感じた経験が、「苦手」という印象として残り、その後も避けがちになることがあるのだ。
この話を通して、ぼくは「食べたことがないものは、食べられるようにならない」と思い、いろいろな食べ物に挑戦してみたいと感じた。
アオムシがキャベツの葉を夢中で食べていたように、ぼくもさまざまな味を知って、大人になると言うことが分かった。