
|
総合選抜入試にも対応。探究学習を超えた、新しい創造発表学習。 AI時代には、知識の学力よりも、思考力、創造力、発表力の学力が重要になる。 ▶
創造発表クラスのご案内
|
 学年別作文感想文の書き方
学年別作文感想文の書き方
1. 時間をかけて人物を評価するために作文力のテストが増える
作文テストを入試に採用するところが増えています。第一は、公立中高一貫校の入試問題です。公立中高一貫校では、これまでの受験テクニックだけでは解けないような本当の実力を見るということから、作文や考える問題を中心に入試問題を作るようになっています。
第二は、高校入試や大学入試で広がっている推薦入試の際の作文テストです。高校や大学では、少子化に対応して早めに推薦で入学者を確保するというところが増えているからです。 第三は、社会に出るときに受ける入社試験です。ここでも、エントリーシートや作文の試験が頻繁に行われています。さらに、社会に出てからも、責任ある立場になれば、文章で他人にわかりやすく説明する能力が必要になってきます。 これまでのペーパーテストは、短期間に大人数を一斉にテストする際に使われてきました。しかし、これからは、少人数をじっくり見る形の評価が中止になってきます。そのときのテストの中心は、作文や小論文です。作文力は、これからますます必要になってくるのです。 | 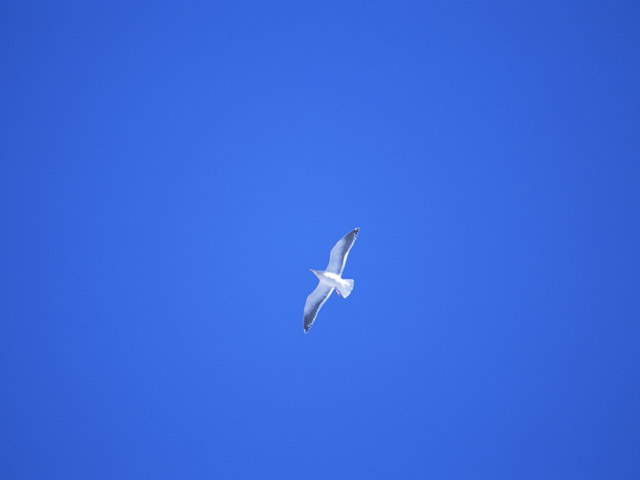 |
2. 小学校1年生の作文は、読む力をつけることで自然に直す
小学1年生のころは、まだ作文を上手に書くことができません。聞く生活には慣れていますが、読む生活には慣れていないので、「わ」と「は」の区別などもよくできません。また、会話にカギカッコをつけるということも、読む生活が増えてきて初めてわかることなので、最初はできないのが普通です。
このような時期に言葉の森で作文を書く練習をするのは、楽しく書く習慣をつけるためです。 作文自体は、ゆっくりと正しく書けるようにしていけばいいのですが、読む勉強は書く勉強よりも先行して進めることができます。 作文の勉強というと、文章を書かせてそれを直すというやり方を思い浮かべがちですが、小学1年生の場合はそういう勉強法はあまりいいやり方ではありません。むしろ、長文暗唱や読書や読み聞かせでたっぷり日本語の読みと聞きの力をつけ、それが作文に反映されるようになるまで、褒め続けてじっと待つという勉強の仕方をしていくのです。 |  |
3. 小学2年生は、作文の勉強が軌道に乗る時期
小学校2年生は、書く力が安定してくる時期です。また、学校生活にも慣れてきます。そして、勉強の習慣をつけやすい最後の時期です。
作文については、楽しんで書かせることが大事です。この時期に他人と比較することは意味がありません。小学校2年生で文章が上手な子は、例外なく本をたくさん読んでいます。文章力は読む量に比例していますから、作文に弱点があった場合でも、作文で直すのではなく読書で直すと考えておくことが大切です。 小学2年生のころは、面白く読める本はたくさんあります。この時期に本を読まないという子はまずいません。しかし、そういう時期のうちに、読書は勉強の中でいちばん優先して取り組むものだという考えを持たせることが大事です。つまり、どんなに忙しい日があっても、読書だけは毎日欠かさないという生活を送っていくということです。 このように、小学校2年生のうちに、作文、自習、読書などが生活の中に溶け込むようになると、その延長で、高学年まで作文や読書の勉強を続けていくことができるようになります。 |  |
4. 小学校3年生、4年生は、作文を上手に書ける時期
小学校3年生、4年生のころは、作文を上手に書ける時期です。
これは、子供たちが学校生活に慣れてくるとともに、書く力もさらに自由に使えるようになってくるからです。このころはギャングエイジとも呼ばれるとおり、作文にもいたずらっぽい楽しさが出てきます。小学校3、4年生の子供たちは、表現の工夫を楽しんだり、内容の面白さを意識して作文を書こうとしたりします。 この時期の作文指導で、大事なことは三つあります。 第一は、表現の工夫を楽しむ指導をすることです。例えば、たとえを使ったり、ダジャレを使ったりして書く練習をします。 第二は、出来事を個性的に書く指導をすることです。この時期は、子供自身にも面白いこと書こうとする意識がわいてきます。時には、家族の話をおもしろく書きすぎることもありますが、あまり目くじらを立てないことが大切です。 第三は、感想を個性的に書く指導をすることです。感想の個性は、大人との対話の量に比例しています。お父さんやお母さんがいろいろな話を聞かせてあげると、それに比例する形で、子供の感想を書く力も深まってきます。 |  |
5. 小学5年生、6年生は考える力のある作文を書く時期
小学校5年生、6年生は、考える力が育ってくる時期にあたります。それは、このころから物事を構成的に考える力がついてくるからです。従って、文章の要約などができるようになるのも、この小学校5、6年生のころからです。物事を構造的にとらえる力がついてくるので、作文の構造も、立体的なものになります。立体的な作文とは、単に時間の順序に書いていくのではなく、過去にさかのぼったり似た話と結びつけたりしながら展開していく作文です。
小学校5、6年生のころは、作文以外の算数、理科、社会などでも、考える要素が出て難しくなる時期です。従って、小学生の勉強は、小学校5、6年生からが本当の勉強らしいものになります。 小学校5、6年生で伸びる子は、小学校3、4年生のころに実力を蓄えた子です。例えば、小学校3、4年生までの時期に本をたくさん読んだ子は、速読力がついてきます。これが小学校5、6年生の国語力の基礎になっていきます。 |  |
6. 中学生は意見を深める時期。言葉の森で考える作文を書く練習を
中学生は、意見を深める時期にあたります。言葉の森では、中学生は意見中心の作文を書く練習をします。
しかし、中学生の時期は、書くのが苦手になる時期でもあります。その理由は第一に、作文の勉強というものが学校で行われなくなるので、勉強の意義を感じにくくなるからです。ただし最近は、高校入試の推薦で作文の試験が課せられるところも増えています。 第二に、中学生のころは、作文のような内面に関わることは身近な人に読まれたくないという時期だからです。 第三に、いちばん大きい理由は、意見文を書くのにふさわしい語彙がまだ備わっていないということです。中学生の時期は、読む力があるほどには書く力がないという時期なので、文章を書いていて、自分の文章がうまくないと漠然と感じてしまうのです。 このため、中学生は大部分の生徒が小学校5、6年生のときよりも作文が下手になるというような印象を受けます。ただし、それは書くジャンルが違うからです。例えば小学校5、6年生のときは、「私のあだな」という題名で実例を中心に作文を書いています。中学生になって、「あだなはよいか悪いか」という題名で意見とその理由を書くという書き方をすると、語彙力が育っていない時期はどうしても内容がものたりなくなってしまうのです。 しかし、中学生のころに上手に書ける子ももちろんいます。その子たちの共通点は、読書量があることです。 |  |
7. 上手な作文に共通するのは、光る表現があること
誤字がなく、字数も長く書けるという作文の基礎力ができた人は、どこに注意をして作文の勉強をしていったらいいのでしょうか。
人間の評価には、不思議な特徴があります。それは、全体的によく書けている文章よりも、どこかに光る場所がある文章の方に高い評価を与えがちだということです。反対に、どこかに誤表記があると、それだけで全体の評価は実力よりもずっと下がります。つまり、全体に90点の文章を書くよりも、全体が80点で一ヶ所100点のところがある文章の方が評価は高くなることが多いのです。 特に印象に残る1ヶ所は、結びの部分です。上手な作文は、途中が上手であるよりも、結びに光る表現があるという特徴を持っています。 |  |
8. 高校生が国語力をつけるためには過去問が最適
高校生が、国語力の土台となる読解力をつけるためには、全国の大学の過去問1年間分の問題集を読んでおくことです。読んでいて内容がつかめない意味不明のところだけ、国語の先生などに聞いておきましょう。
テストの成績を上げるためには、三つのことが大事です。 第一は、問題文の全文を、一息で、味わいながら、ところどころに線を引きながら、読んでいくことです。物語文などでは、特にこの味わって読むことが大切です。問題文の世界に没入して味わって読んでおくと、そのあとの選択問題を答えるときにも、改めて問題文を読み返す必要がなくなります。 第二に、選択問題の解き方です。選択肢のどこがなぜ違うのかということを記録に残しながら解いていきます。記録を残さないで解いた場合、うまく合っていても力がつきません。間違っていた場合でも、なぜ間違えたのかということが反省できなくなります。他の教科と同じように、国語も理詰めに解いていくことで力がつきます。 第三に、志望校の過去問の性格を知ることです。 過去問の性格とは、わかりやすい性格、ひねっている性格など、問題自体の性格のことです。志望校の過去問の性格を知っていると、選択に迷ったときに、役に立ちます。 |  |
 受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。 電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。
電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。| 教育技術(5) 教育論文化論(255) 教室の話題(26) ゲーム的教育(4) 構成図(25) 公立中高一貫校(63) 国語問題(15) 国語力読解力(155) 子育て(117) 言葉の森サイト(41) 言葉の森の特徴(83) 子供たちの作文(59) 合格情報(27) 作文教育(134) 作文の書き方(108) 質問と意見(39) 小学校低学年(79) 森林プロジェクト(50) 受験作文小論文(89) 生徒父母向け記事(61) センター試験(7) 対話(45) 他の教室との違い(22) 大学入試(14) 知のパラダイム(15) 中高一貫校(11) 読書(95) 読書感想文(19) 日本語脳(15) facebookの記事(165) 勉強の仕方(119) メディア(8) 森リン(103) 問題集読書(33) |