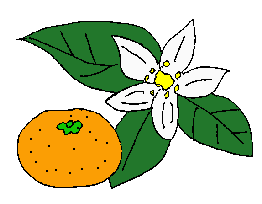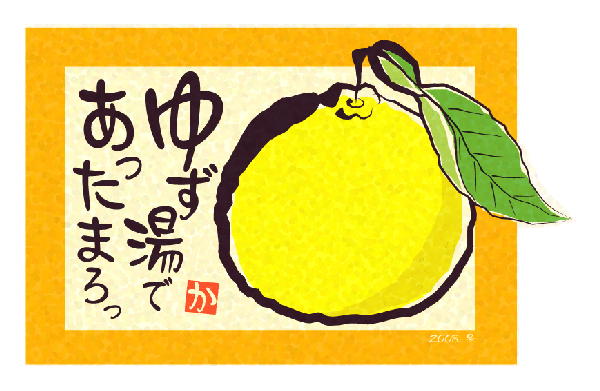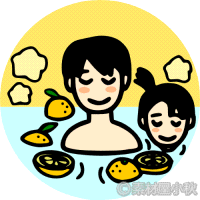12月の実行課題集 1
12月の実行課題集 1
年賀状・ミカン・吹き矢


ミカンの皮をリサイクル
冬にこたつで食べたい果物といえば、やっぱりミカンですね。みずみずしくてとてもおいしい果物ですが、味だけでなく、さわやかな柑橘の香りが好きという人もいるでしょう。あの香りは、じつは実ではなく皮の方に含まれる「リモネン」という成分によるもの。ですから、食べ終わった皮を捨てずに再利用することで、その香りを生かすことができるのです。
たとえば、柚子湯のようにネットに入れて、お風呂に浮かべるのもいいでしょう。(ミカンやユズの仲間ということで、「オレンジ湯」や「レモン湯」もできるかも!?)あるいは靴の中や電子レンジに入れておくと、消臭の効果が発揮されます。さらに、少し工夫がいりますが、ミカンの皮の使った「アロマキャンドル」や「香水」を作ることもできます。
しかもミカンの皮には、香り以外にも汚れを落とす効果まであり、直接こすったりスプレー洗剤にしたりすることでお掃除にも使えます。ミカンの皮は、まさしく優れものなのです。
食べるだけでは未完成、そのまま捨ててしまってはもったいないですね。
オリジナル年賀状
今は、新年の挨拶もメールで済ませてしまうことが多いようですが、お正月くらいは、自分らしい年賀状を作って送りたいものです。
ネット検索をすると、消しゴムハンコ、木版画、芋版などの作り方が載っています。消しゴムハンコや芋版は、手軽にできるので、まずは、このあたりから挑戦するといいかもしれません。芋版を作った後、版の部分を切り取って、残りを焼いて食べてもおいしそうです。このほかにも、手形や足形(?)を押したり(葉書に収まる大きさであることが条件ですが)、飼い犬の肉球を借りたりするとユニークな年賀状が出来上がるでしょう。
また、この機会に年賀状のマナーについて調べてみると勉強になりますね。
ストロー吹き矢
ストローと綿棒で吹き矢を作ります。ストローは蛇腹の部分を切り取ります。綿棒は半分に切ります。綿棒が矢になります。ストローに綿棒が入らない場合は、綿棒の頭をはさみで切って小さくするとよいでしょう。ストローは綿棒が入る太さで準備した方が吹きやすいです。矢をストローの中に入れて、後ろからふっとふくと矢が飛んでいきます。
できたら、的も作ってみましょう。射的の的のようなものや、当たると倒れる的などいろいろできます。難易度は高いですが、ボール紙に穴をあけて、そこを吹いて通せるか、というチャレンジもできます。
 12月の実行課題集 2
12月の実行課題集 2
手作りクリスマス


木の実で作るクリスマスリース
秋に集めた木の実を使って、オリジナルクリスマスリースを作ってみてはいかがでしょうか?
準備するもの
・リース(100円ショップで入手できます)
・木の実(どんぐり、松ぼっくり、つばきの実など)
・リボン、綿、羊毛、毛糸などなど・・
・ボンドかグルーガン
リースに、木の実やリボン、綿などをボンドかグルーガンでどんどんつけていくだけです。
(グルーガンを使う場合はやけどに注意しましょう)
毛糸はぐるぐる巻くだけでもかわいい。
カラースプレーなどがあれば、緑や銀色などに色付けしてもいいですね。
みんなで作って、飾り付け。クリスマスが待ち遠しくなりますね。
松ぼっくりのクリスマスツリー
松ぼっくりでかわいいクリスマスツリーを作ってみましょう。松ぼっくりは、笠が開いていて、形のよいものを選びます。
アクリル絵の具で色を塗ります。緑や白にするとクリスマスツリーらしくなります。ビーズ、BB弾、色紙で作った星、リボンなどをボンドで飾り付けます。雪に見立てた綿をつけてもよいでしょう。
台は、小さな箱やスポンジなどで。これもボンドで固定します。
たくさん作って、それらを組み合わせると大きなツリーにもなります。
手作りオーナメント・ヒイラギの風車
サンタクロース、ヒイラギの葉、トナカイ、鐘、キャンドル、雪だるま、十字架、プレゼントボックス、星、リボン、雪の結晶、天使などのオリジナルオーナメントを作ってみましょう。折り紙、フェルト、紙粘土、厚紙など、身近にある材料で簡単に作れそうです。サンタクロース、トナカイ、天使の顔の部分に家族の写真を貼ってみるのも楽しいですね。
手作りに疲れたら、ヒイラギの葉を使った風車遊びを。ヒイラギの葉は、トゲが葉の中央にあるものを選ぶと回しやすいです。葉のトゲの部分を、親指と人差し指で持ちます。痛くない程度に軽く持つのがコツです。この状態で、葉の上半分(または下半分)に息を吹きかけると、くるくると風車のように回ります。
 12月の実行課題集 3
12月の実行課題集 3
冬至は柚子湯でリラックス


「いとこ煮」を作ってみよう
「いとこ煮」とは、硬いものをおいおい(甥)入れて、めいめい(姪)炊き込んでいくことから、甥と姪のいとこにかけて名付けられた料理のことです。小豆とかぼちゃのいとこ煮を作ってみましょう。
<材料>(4人分)
かぼちゃ:400g 小豆:100g(水煮しておく) 砂糖:大さじ4 醤油:小さじ2
<作り方>
1.小豆とかぼちゃに水を加えて20分煮る。 2.砂糖と醤油を加えて味を整え5分煮る。 3.火を止め、しばらく置いて味を含ませれば出来上がり。
冬至とは
冬至とは、二十四節気の一つです。年によって日にちは変わりますが、だいたい12月22日ごろの、北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年のうちで昼が最も短く、夜が最も長くなる日を指します。また、この日から、次の節気の小寒前日までの期間を意味することもあります。
冬至には、なんきん(カボチャ)・れんこん・うどんなど、「ん」のつく食べ物を食べると長生きすると言われています。特に、カボチャの煮物は、冬至に食べる食べ物としてよく知られています。この日に小豆粥を食べると疫病にかからないという伝承もあります。
また、冬至に柚子湯に入ると風邪を引かないと言われています。柚子は香りが良いだけでなく、体を温める効果もあります。ゆっくり柚子湯に入って、心も体もリラックスさせたいですね。お隣に柚子の木があったら、柚子の実を一つゆずってもらうといいかもしれません。
「ん」のつく食べ物
「ん」のつく食べ物は、「なんきん」、「れんこん」、「うどん」のほかにどんなものがあるでしょうか。「だいこん」、「いんげん」、「ぎんなん」、「みかん」、「れもん」、「きんかん」、「にんじん」、「かんてん」、「あんぱん」、「かつどん」……。ほかにもいろいろありそうですね。
食べ物以外の「ん」のつくものも、思いつくだけ言ってみましょう。「ずきん」、「ずかん」、「すいぞくかん」、「たいいくかん」、「おめん」、「みほん」、「せんすいかん」、「あきかん」、「がめん」、「しつもん」……。意外とむずかしいですね。なかなか簡単には見つかりませんね。
 12月の実行課題集 4
12月の実行課題集 4
お坊さんも走る! 師走


正月事始め
12月13日は「事始め」とも言い、年神様を迎えるために様々なお正月の準備を始める日です。
・煤払い~昔はほとんどの家に囲炉裏があり煤がつきやすかったため、行われていました。現在は、お寺や神社などでお堂やご本尊を清めるための煤払いが行われています。年神様を迎えるための神聖な行事とされ、家庭では神棚や仏壇の掃除をします。
・松迎え~昔は、門松のための松やお雑煮を炊くための薪を取るために恵方の山へ行く習慣がありました。門松やしめ飾りは年神様が降りてくる目印と考えられ、12月26日から28日に飾るのが一般的です。29日は「苦松」「苦立て」といってきらい、31日も「一夜飾り」で一夜では年神様への誠意に欠けるとしてきらう風習があります。
大晦日
毎月の30日(月末)を「晦(みそか)」というので、一年の最後の晦を「大晦日(おおみそか)」といい、この日の夜を「年越し」といいます。
・年越しそば~大晦日には縁起ものであるそばを食べる風習があります。この風習は江戸時代から始まったといわれ、「そばのように細く長く寿命や幸福が続くように」との願いが込められています。そばはうどんなどに比べて切れやすいことから、「年切りそば」といって「その年の苦労や災いを断ち切って新年に持ち越さない」という意味もあるそうです。また、金箔職人が作業場で散った金を、練ったそば粉で集めたことから、「金運がよくなる」との説もあるとか。家族そろって年越しそばをいただき、よい一年のしめくくりにしたいものですね。
父「今年の年越しそばはどんな味かな?」
母「できましたよ~。」
父「お~、みそ(味)か~!」(味噌そばなんてあるんかいな?)
新年を迎えるために
・掃き納め~大晦日にする掃除のことをいいます。元旦の掃除は「福を掃く」として縁起が良くないとされています。一年最後の日にきれいに掃除をして、新しい年を迎えたいものですね。
・年の湯~大晦日の夜にお風呂に入ることをいいます。今は毎日入るのが当たり前なので意識しませんが、昔は一年の垢を落とす特別な入浴だったそうです。大掃除できれいにした風呂に入り、身も心もきれいさっぱりにして新年を迎えたいですね。