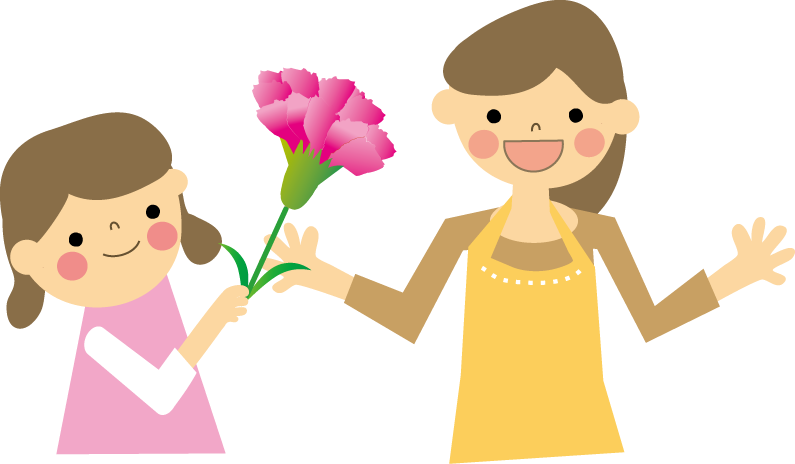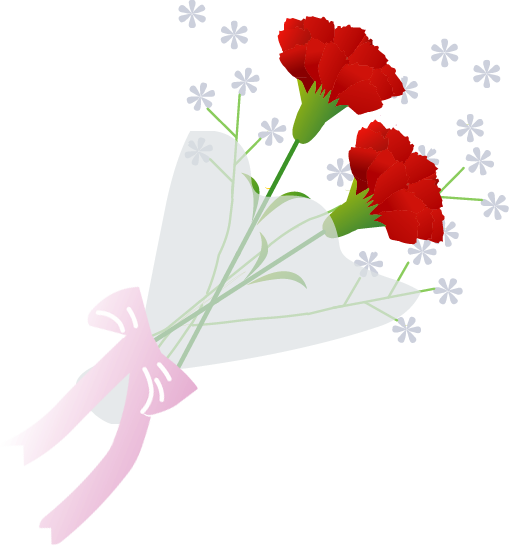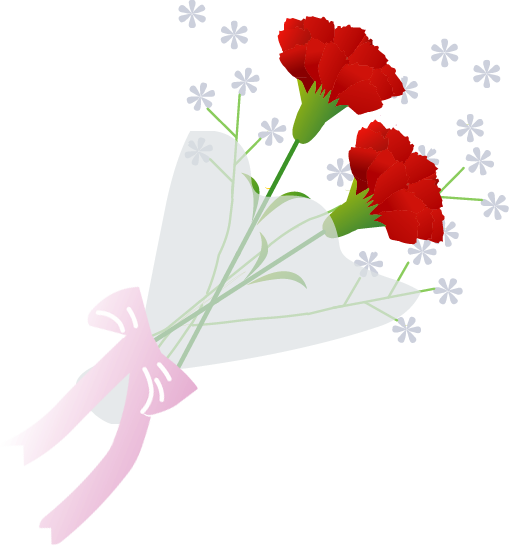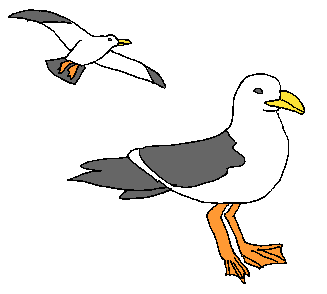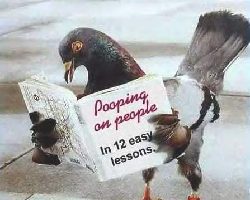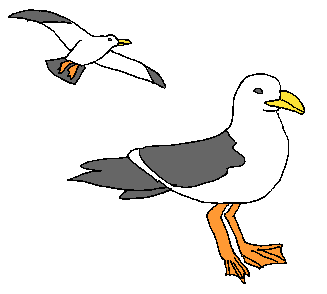5月の実行課題集 1
5月の実行課題集 1
5月5日GOGO!こどもの日


空高く泳ぐ鯉のぼり
5月5日は子どもの日。昔から男の子のいるうちでは、元気に育つようににと願いをこめてこいのぼりを飾ります。これは、古くは中国の「後漢書」による「黄河にある竜門という滝を多くの魚が登った時、鯉だけが最後まで登って、竜になることができた」というお話から、鯉の滝登りはつらいことを乗り越えて、りっぱに身を立てることを表しているのです。
現在のこいのぼりは、一番上に5色の吹き流し、黒い真鯉(お父さん鯉)、赤い緋鯉(お母さん鯉)、青い子どもの鯉という構成です。吹き流しと、上にのっている矢車は魔除けの意味があるそうです。
各地で大きなこいのぼりが飾られる行事があるので、連休にでかけてみるといいですね。
2005年にギネスブックに認定された群馬県館林市の世界一こいのぼりの里まつりでは、5箇所で5000匹のこいのぼりがあげられるということです。
東の柏餅と西の粽
柏餅は、上新粉とくず粉をまぜて作った「しんこ餅」にあんを挟んで、柏の葉で包んだ和菓子です。柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないので「子孫が繁栄するように」と端午の節句に食べるようになりました。 また端午の節句には、「粽」という人もいるでしょう。粽はもともと中国から端午の節句が伝わった時に一緒に伝えられ、広まりました。粽とは餅を茅や楝樹の葉で包んだもので、「災いを除ける」という意味があるそうです。
兜をかぶっとる!
江戸時代の武士の間では「菖蒲」が「勝負」や「尚武(武道を重んじる)」に通じることから、男の子の誕生や成長を祝う日へと結びつきました。やがてこの風習は一般の人々まで広がり、七歳以下の子供のいる武家では、玄関前に幟を立てていましたが、これが厚紙で作られた兜や人形になり、さらには紙や布に武者絵を書いたものも飾られるようになりました。
立派な兜飾りも素敵ですが、新聞紙で兜を折って、みんなでかぶってみるのはいかがでしょうか?
まずは新聞紙を正方形に切ります。できあがりは8分の1くらいの大きになります。折り方は折り紙の兜と同じです。
 5月の実行課題集 2
5月の実行課題集 2
お母さんの休日

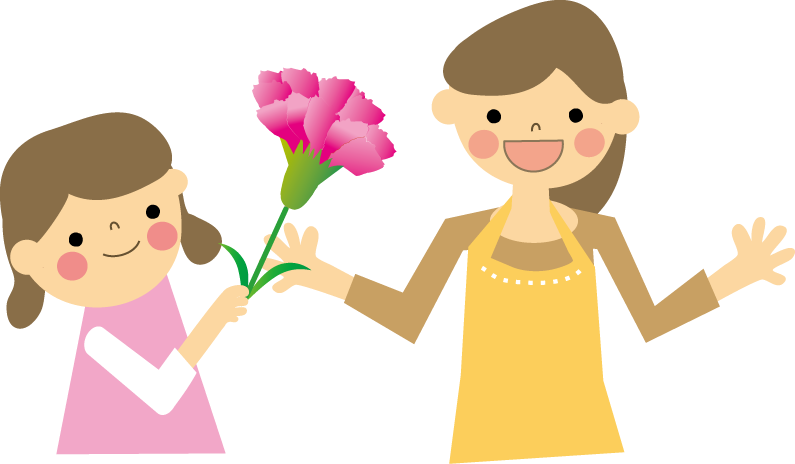
梅シロップを作ろう
分量
梅の実 500グラム
氷砂糖 500グラム
酢 大匙2杯
量はお好みで。梅の実と氷砂糖をほぼ同じ分量で入れてください。
作り方
1、梅の実を水洗いする。
2、梅についているへたをつまようじや竹串でとる(お子さんと一緒に)
3、キッチンペーパーで水分をふき取る。
4、清潔にした瓶に梅の実を一段敷き詰める。
5、その上に氷砂糖を敷き詰める。
6、梅の実と氷砂糖を交互に入れていき、一番上に氷砂糖がくるようにする。
7、最後に酢を入れてふたをする
8、毎日ゆらして、約2週間、氷砂糖が溶けて、梅の実が浮いてきたら出来上がりです。
お母さんの休日
何か買ってあげることだけがプレゼントではありません。いつもお母さんがしてくれていることを手伝ってみるのはどうでしょう。
食事の支度の手伝い (テーブルをふく、食器をならべる、ご飯をよそうなど)
食事の後片付け (食器洗い、テーブルをふく)
部屋の掃除 (掃除機をかける、床をふく)
お風呂の掃除 (バスタブをみがく、お風呂の床をきれいにする)
洗濯物 (背が届く場合、干したり、取り込んだり。取り込んだものをたたむのはできますね。)
弟や妹の世話
カーネーション作り
母の日には、お母さんへの感謝を込めて、折り紙でカーネーションを作ってみましょう。
途中までは、朝顔を作るときと同じです。朝顔ができたら、周囲をぎざぎざに切っていきましょう。カーネーションの花らしくなります。
「カーネーション 折り紙」で検索すると、ほかにもいろいろな折り方が紹介されているので調べてみてください。花だけではなく、茎の折り方も載っています。
素敵なカーネーションの花束を作って、お母さんにプレゼントしてください。お母さんは喜んで、優しく頭をなでなでしてくれるかもしれません。(カーネーションはナデシコ科の花です。)
 5月の実行課題集 3
5月の実行課題集 3
夏も近づく八十八夜チャッチャ


親子で日本茶を
八十八夜に摘んだ茶葉は良質で、末広がりの八が重なることから縁起が良いとされています。甘みから渋み、さらには苦みへと変化していく日本茶を、たまには親子で味わってみてはいかがでしょうか。
<おいしい日本茶のいれ方>
茶さじいっぱいの茶葉を急須に入れる。→三分間さましたお湯を急須に。→ふたをして一分間待つ。→湯飲みを温めていたお湯を捨て、お茶を最後の一滴まで注ぐ。
二煎目、三煎目をおいしくいただくために茶葉が蒸れないよう急須のふたを少しずらしておく。
粉茶を作ろう!
栄養があるのに普段はなかなか葉まで食べることがない緑茶を粉茶にして残さずいただいてみましょう。作り方は、緑茶を適量すり鉢に入れ、すりこぎで粉になるまですりつぶします。アレンジもいろいろできます。
★緑茶クッキー・ホットケーキ
★緑茶オーレ(牛乳、蜂蜜で。この場合は粉を直接入れるとだまになってしまうので、少量の水で溶いてから使用してください)
バケツ稲、いーね!
5月は、皐月(さつき)とも言います。これは、苗代で発芽させた稲の苗、早苗を田んぼにうつしかえる月、早苗月から来ているそうです。みなさんも毎日食べるお米を作ってみませんか? 広い田んぼがなくてもできるのです。学校によっては高学年の授業で体験するところもあります。これは田んぼの代わりにバケツを使うので、バケツ稲と呼ばれています。種もみ・肥料・土とバケツを用意すれば、お庭やベランダでお米を作ることができます。種もみと肥料は、下のところに申し込むと送ってもらえます。(先着1万名・4月30日12時締め切り)
「全国農業協同組合中央会のバケツ稲作りセット申し込み」
じょうずに育てて、秋には自分で作ったお米でご飯を食べましょう。
 5月の実行課題集 4
5月の実行課題集 4
愛鳥週間


愛鳥週間とは
5月10日から16日までの7日間は、「愛鳥週間」(バードウィーク)です。愛鳥週間の愛鳥とは、鳥を手元においてかわいがるということではなく、自然の中で自由に飛び回る鳥を愛でるということです。鳥にとって棲みよい環境を作るためには、鳥だけではなく、鳥をとりまく生態系を守っていくことが大切です。
スズメ、カラス、ハト、ムクドリ、メジロ、ヒヨドリ、トンビ、サギなど、身近な鳥を観察してみましょう。ツバメもそろそろ海を渡ってやってくるころですね。ツバメの巣作りの様子を観察できるかもしれません。また、水辺に行けば、カモメやカモなども観察できそうです。海に行くときは、トンビにお弁当を取られないように気をつけてくださいね。
「トリ」のつく言葉
「トリ」のつく言葉をさがしてみましょう。「取り返しがつかない」「取るものもとりあえず」「色とりどり」「ハットトリック」「取り混ぜる」「取り巻く」「取り付く島もない」「うっとりする」「アトリエ」「取り越し苦労」……。みなさんは、いくつ思いつくでしょうか。
「トリ」を使ったダジャレもいろいろできそうです。「とりあえず、鳥を取りかえる」「色とりどりの見取り図」「鳥の取り扱いがうまいのが取り柄だ」などなど。みなさんも考えてみてください。
牛乳パックの巣箱作り
鳥をより身近で観察するために巣箱を作ってみましょう。牛乳パックで簡単に作れます。牛乳パックの一面を、鳥が入れる大きさぐらいに繰り抜きます。中には、パンやビスケットなど、鳥が喜びそうな食べ物を入れておきます。巣箱は、針金などで木に取り付けます。牛乳パックであることが鳥にわからないように(たぶん、わからないと思いますが(笑))、枝などでうまく隠して目立たないようにしましょう。中に草を入れておいてもよいでしょう。あまり頻繁にのぞきに行くと、警戒して鳥が寄ってこないので注意してください。どんな鳥がやって来るか楽しみですね。美しい鳥のさえずりにうっとり……なんていうこともあるかもしれません。