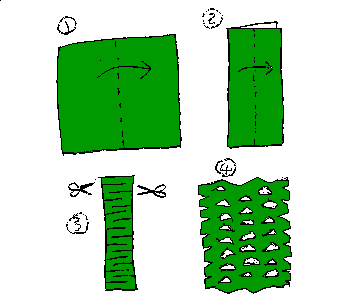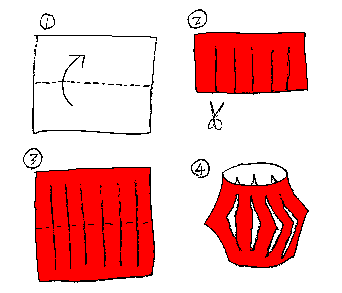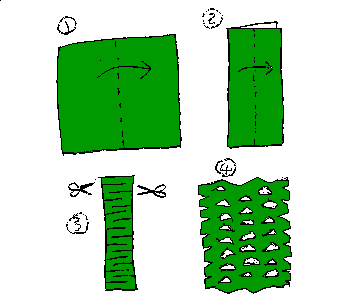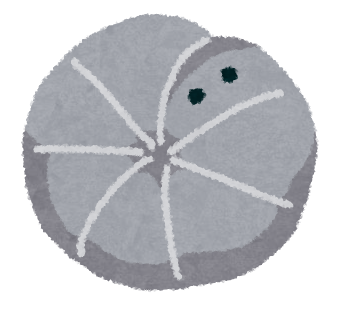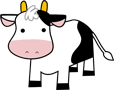7月の実行課題集 1
7月の実行課題集 1
七夕に願いをこめて


なぜたなばたと読むの
七夕は日本独自の風習と中国の二つの伝説が結びついたものです。
一つ目はみなさんもよく知っている、「織姫と彦星」の伝説です。古代中国の、一年に一度七月七日の夜にだけ二人は天の川を渡って会うことが許されているというお話です。
二つ目は、同じく中国から伝わった「乞巧奠」の風習です。これは織姫が機織りが非常に巧みであったことから、機織りはもちろん、裁縫や書道などの上達を願う習わしです。
三つ目は、日本独自の風習で神を迎える儀式です。「棚機女」という選ばれた乙女が、水辺の機屋にこもって豊作をもたらす神様の着物を織り、お供えして、収穫の無事を祈りました。この機織り機のことを「棚機」といいました。棚機はお盆を迎える準備として、七月七日の夕方に行われていたため「七夕」を「たなばた」と読むようになりました。
「七月七日って、何もしなくても、いいものがもらえるんだよね」(そりゃ、棚ぼた。)
どうして笹に飾るの
笹のできる竹は、天に向かってまっすぐのびて成長していく植物で、歌にもあるように葉が風にゆれてサラサラと音がします。このサラサラとした音が天からご先祖様を呼ぶとされていて、笹は神聖な植物だと言われています。天やご先祖様に願いがきちんと届くように、七夕には笹が使われているのです。色とりどりの短冊に願い事を書いて、かざりつけてみましょう。
「うちは笹がないから、お正月に使った樅の木でいいや」なんていうのは駄目ですよ。しかも、樅の木はお正月じゃないし。
七夕飾りを作ろう
笹には短冊だけでなくいろいろな飾りをつけますが、その一つ一つにも意味があります。
◎ちょうちんかざり
折り紙で筒を作ります。筒とはちがう色のもうひとつの折り紙を半分に折り、一センチ程度の間隔で切れ目を入れて開きます。先に作った筒に上下の端を合わせてのりで貼ってできあがり。これには「願い事を書いた短冊を明るく照らす」という意味があるそうです。
◎あみかざり
折り紙を縦に二回折り、左右から互い違いに同じ間隔で切れ目を入れていきます。紙を広げるときれいに伸びる網ができます。これは「海で魚がたくさんとれて、作物もよく実るように」という意味があります。
◎ふきながし
織姫の織糸を表し「機織りや芸事の上達を願う」という意味だそうです。
「七夕飾り 作り方」で検索すると、ほかにもいろいろ見つかるでしょう。
 7月の実行課題集 2
7月の実行課題集 2
雨上がりは公園へ


生き物探検隊
梅雨で、まだまだ雨の多い季節ですね。雨上がりに公園へ行って、生き物をさがしてみるのはいかがでしょうか。様々な生き物たちに会えるかもしれません。
湿った所にある少し大きめの石を持ち上げて裏を見てみましょう。湿った所が好きな「ダンゴムシ」や「ミミズ」に「ナメクジ」など、様々な生き物を見ることができます。
「ダンゴムシ」は落ち葉が大好物です。たくさんの落ち葉を食べて、土にもどすという大切な働きをしています。
「ナメクジ」に塩をかけると小さくなってしまうことは、みなさん、知っていますね。体の90パーセントが水分でできているので、塩をかけられると水分をすいとられてしまい、小さくちぢんでしまいます。ちぢんでも、ほとんどの場合は元気に回復するそうです。「ナメクジの力をなめんなよ。」と言われそうです。でも、ひどい時には死んでしまうこともあるそうなので、ほどほどにね。
ダンゴムシの観察
注意:必ずおうちの人の許可をもらいましょう!
・コーヒーやジャムのびんに湿った土を3センチくらい入れる。
・石などでかくれる場所を作る。
・落ち葉をたくさん入れる。
・ダンゴムシを数匹入れる。
・ガーゼやあみでふたをして、輪ゴムでしっかりとめる。(しっかりとめないと、大変なことになります。)
ダンゴムシは日なたがきらいなので、風の通る薄暗い場所に置きましょう。
カタツムリはどこに
カタツムリは、古くからある建物によくいるので、神社やお寺などの湿ったところを探してみましょう。
雨の日でなくても、カタツムリはいます。朝早く、まだ日が昇らないけれど空が明るくなってきたころ、岩でのんびり朝寝をしていることがあります。
大きいカタツムリを見たら、年輪を数えてみましょう。殻のところに黒い筋のようなものがあればそれが年輪です。冬にはカタツムリの殻があまり成長しないので、そこだけ黒っぽくなっているのです。
カタツムリのほとんどは右巻きですが、中に、1種類だけヒダリマキマイマイという左まきのカタツムリがいます。
カタツムリを見つけたら、水槽に土を入れて湿らせて飼ってみましょう。カタツムリは、オスとメスの区別がありません。やがて土の中に、白い小さな卵が見つかるかもしれません。
「あ! 卵が」「見つかったの?」「見つからなかった」「なあに、それ」「見つカッタツムリ」
 7月の実行課題集 3
7月の実行課題集 3
雨の日も家で楽しく


家の中でボウリング
外で遊べなくてつまらないときは、おうちにあるペットボトルを使ってボウリングをしましょう。500ミリリットルのものがちょうどよいでしょう。本当のボウリングは10本のピンがいりますが、数は自由でいいですね。廊下などにお水を入れたペットボトルを三角形に並べたら、さあ始まりです。ボールもあるものでオーケーです。
おすすめは、ペットボトルに絵の具をたらしてきれいな色にしたり、シールやリボンで飾ったりすることです。楽しさが倍増します。また、ピンに点数をつけて競うのも楽しいですよ。さあ、だれがチャンピオンになるかな?
ボウリングは、紀元前5000年のエジプトにもありました。もともとは、ピンを悪魔に見立てて、それを倒したら災いから逃れることができるという宗教的な儀式でした。
日本では、江戸時代の終わりごろ、長崎に初めてボウリング場ができました。そのころのボウリングは、倒れたピンを立てるピンボーイという人がいました。
その後、アメリカで、機械によってピンを立てる仕組みが作られ、その最新機械が日本に導入されたころ、日本でもボウリングが大きなブームになりました。
セロファンで作る影絵
手で作った狐や鳩を壁に映して影絵をしたことはありませんか? インドネシアや藤城清治さんの美しい作品を見た人もいるでしょう。みなさんも、そんな影絵を作ってみましょう。
用意するもの 厚紙 セロファン紙 カッター 割り箸 のり セロハンテープ
作りたいものの絵を厚紙に描き、きれいに切りましょう。裏に割り箸をつけたらできあがり。
また、おうちの方に手伝ってもらい、目や口などいろいろな部分をくりぬいて、そこにセロファンを貼るとさらによいでしょう。
できあがったら部屋を暗くして、懐中電灯やスタンドの光で白い壁にに映してみましょう。たくさん作って、劇をしてもいいですね。光のかげぇん(加減)でいろいろに見えますよ。
ペープサートの劇
画用紙などの少し厚い紙に、お話に出てくる人や動物の絵を書いて、張り合わせ、棒につけます。絵は裏表に書くのです。それを動かしたり裏返したりして、劇をします。
用意するもの 画用紙などの少し厚めの紙・サインペンなど・割り箸・セロハンテープ
お話を決めたら、親子で作る人形を分担しましょう。後ろ姿も描くのがミソです。
余裕があれば背景の絵なども用意すると本格的になります。
使うお話は、よく知っている絵本や昔話でもよいし、好きなテレビ番組のものでも楽しいですね。鬼退治のお話にポケモンが登場するなんていうのもできますよ!
 7月の実行課題集 4
7月の実行課題集 4
土用の丑


丑の日は暑気ばらい
「土用」というのは、季節の変わり目の前、「四立」と言われる「立春、立夏、立秋、立冬」の前の約18日間のことです。「丑の日」の「丑」は十二支の丑のことで、年を数えるだけではなく方角や月、日、時間を数えるためにも使われます。約18日間の土用の期間のうち、12日周期でやってくる丑の日が「土用の丑の日」になるわけです。
江戸時代から「丑の日にちなんで『う』から始まる食べ物を食べると夏負けしない」と言われていました。夏場は鰻の売れ行きが落ちることを鰻屋から相談された平賀源内が、「本日土用丑の日」と書いた張り紙を店に貼ったことから評判を呼び、鰻屋は大繁盛になりました。これをほかの鰻屋もまねをするようになり、「土用丑の日は鰻の日」という風習につながったのです。
丑の日でも牛を食べるということがなかったのは、昔は四つ足のものを食べる習慣があまりなかったからです。
今だったら、「そろそろ土用の丑の日だから、今度の土曜日に牛丼でも食べに行こうか」と勘違いする人もいそうです。
「う」のつく食べ物
2014年に、ニホンウナギが絶滅危惧種に指定されました。輸入物のウナギもありますが、やはり日本産のウナギでないと暑気ばらいにはならない気がします。
そこで、今年は鰻ではなく「う」から始まる食べ物について家族でさがして、食べてみるといいでしょう。
・うどん ・うめぼし ・うずらの玉子 ・ウインナーソーセージ ・ういろう ・うじきんとき ・うのはな ・うぐいすまめ ・瓜 ・うまか棒(!?) ・薄皮まんじゅう(!?) ・うつぼ(!?) 等々、いろいろな「う」のつく食べ物があります。
この中で、鰻に代わって暑気ばらいに効く最強の組み合わせは、薄味のうどんに、梅干しとうずらの玉子を入れて、「う・まい」と言いながら食べることです。(本当にうまいかなあ。)
ほかにもある土用
土用には食べ物のほかにも、「土用の虫干し」や「丑湯」などの風習があります。
「土用の虫干し」とは、梅雨の時期に湿りがちな衣類や、書物、調度品などを風のよく通るところで陰干しし、カビや害虫の発生を防ぐことです。おもちゃやぬいぐるみなどを干すのもいいですね。
「丑湯」とは、土用の丑の日に疲労回復や夏バテ防止のために、桃の葉などの薬草を入れたお風呂に入る風習のことです。毎日入浴できなかった時代には「丑湯」は特別だったようです。みなさんも、ハーブや薬草を入れて丑湯を楽しんではいかがですか。