先頭ページ
前ページ
次ページ
最終ページ
| |
則 |
| |
アジサイ |
の |
池 |
の広場
|
| |
ほり内 |
/ |
ぬり |
中1 |
 |
| |
言葉は、ものすごく大事である。この話は昨日(12月13日)にあった、「進化のプリズム」という番組で、未来の学校というテーマで、出演者がこんな事 |
| を行っていた。 |
| |
「最近ITといっていて騒がしいが、ようするにそれは、いつものやっていたコミュニュケーションの形が変わっただけでべつに、何もかも変わるわけが |
| 無い。」 |
| |
それだけ言葉は重要な役割を果たしていたと考えられる。そもそも言葉というのは古く旧石器時代に生まれたものと考えられる。それだけ言葉は、人間と |
| 密接な関係にあったと考えられる。しかし言葉は、人間にあわせて変わっていくのが常。まず、日本語、英語、フランス語、ドイツ語などの国ごとの言葉に |
| なり、つぎに、地方の方言になる。 |
| |
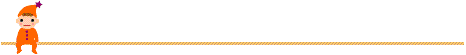 |
| |
それと同じように、規則やルールも時代にあわせて変わったほうがよいと思う。 |
| |
その理由は第一に、規則を変えたほうが分かりやすいからだ。例えば、昔の学校の校則にあったような、腕時計をして来てはいけない、というのもわざわ |
| ざかけてある時計を見なくても、手元にある腕時計のほうが分かりやすいから、別によい、というようになっている。このように校則や規則というのは、わ |
| かりやすいほうへ、どんどん変わっていくのである。 |
| |
第二に、変えないと困るからだ。ここで取り上げる校則は、帽子のことだ。昔は、中学生は、丸坊主が普通だったから、別に、帽子を被っても気にならな |
| かったが、今、カリスマ美容師といわれるように、中学生でも、髪型を気にするようになったから、帽子なんか、あると髪型が崩れてしまい困るという人が |
| 出て来て廃止になった。このように、変えないと困るものはどんどん廃止にしたほうがいいのだ。 |
| |
確かに、規則を変えずにそのままにするのもいいが、「できあがった規則をなんとか守ろうとすることよりも、実態に合わせて規則を変えていくことが、 |
真に規則を生かす道である。」という名言のように、規則はどんどん変えていかなければならない。 |
| |
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
ホームページ