印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■7月21日(月)は休み宿題
■通信生で2ヶ月以上未提出が続いた場合は担当交代に
■通学生で1ヶ月以上欠席が続いた場合は通信受講に切り替え
■日本の生徒の学力とPISAで要求される学力
■PISAの学力から類推されること
■ふとしたことから(パンダ/なるこ先生)
■書を読むのみに非ざるなり(あこ/やよい先生)
■正しい昼寝のしかた(!?)(たんぽぽ/たま先生)
|
|
||
|
言葉の森新聞
2008年7月2週号 通算第1038号
https://www.mori7.com/mori/ |
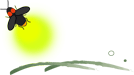
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■7月21日(月)は休み宿題 |
|
7月21日(月)は、休み宿題です。先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室までお電話をして説明をお聞きください。(平日午前9時〜午後7時50分。電話0120-22-3987) 電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」か課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 「授業の渚」 http://www.mori7.com/nagisa/index.php 「ヒントの池」 http://www.mori7.com/mine/ike.php |
|
|
||||
| ■通信生で2ヶ月以上未提出が続いた場合は担当交代に |
|
通信生で、2ヶ月以上未提出が続いた場合は、翌月から担当の先生が交代します。 ただし、やむをえない事情がある場合はご相談ください。 |
|
|
||||
| ■通学生で1ヶ月以上欠席が続いた場合は通信受講に切り替え |
|
通学の生徒で、1ヶ月以上欠席が続いた場合は、翌月から通信による受講に切り替えます。 ただし、やむをえない事情がある場合はご相談ください。 |
|
|
||||
| ■日本の生徒の学力とPISAで要求される学力 |
|
日本の教育産業、学習塾や予備校などの世界は競争が激しいので、勉強についてある目標を持つと、その目標に向かって極めて効率的な指導システムを完成させます。 そして、現在、日本の教育産業が何を目標としているかというと、当然受験に合格するための勉強です。受験勉強に合う学力をつけるために、高度にシステム化した勉強が行われているというのが、日本の教育の現状です。 ところで、その受験勉強が目指す学力の内容は何かと言うと、ここで一つの問題が出てきます。受験というものは、短時間で大量の試験を採点するという必要から、考える問題ではなく、記憶を再現する問題を中心にせざるを得ないところがあります。 もちろん、考える良問はありますが、採点者が採点に頭を使うような問題ではなく、ある程度自動的に採点できるような仕組みの問題を作らざるをえません。そういう日本の受験の内容にあった教育がされていたために、OECDの学習到達度調査(PISA)で、日本の生徒の思考力、記述力、読解力が不足しているという結果が出たのだということです。 それは、ある意味で当然と言えば当然のことです。日本では、PISAで要求されるような学力を目指す教育を行っていなかったから、PISAで低い結果が出たということです。もし、日本の受験の内容がPISA的なものであれば、ほぼ二、三年で日本の生徒の学力は、国際的にトップレベルになると思います。日本の教育産業は、それだけのシステム力を持っているからです。 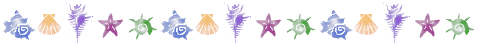
|
|
|
|
|
||||
| ■PISAの学力から類推されること |
|
OECDの学習到達度調査(PISA)でわかったことは、今の日本の子供たちの勉強には、国際的に見ると欠けていると思われるものがあるということです。 しかし、これはたまたま日本と諸外国の生徒の学力を比較したからわかった弱点です。このような比較がなければ、日本の国内では何の問題もなくこれまでと同じような教育が行われていたことでしょう。 同様なことは、まだ比較をされていない分野でも、実はあるはずです。子どもたちが将来成長したときに、自分が受けてきた勉強に意味があったと思うのは、その勉強が自分の人生に生かされていると感じたときです。受験勉強には役立ったが、人生にはあまり役立たなかったと感じるのであれば、その勉強はあまり意味があったとは言えません。 そして、現在の受験勉強は、ますます人生から乖離しているように思えます。その一つのわかりやすい例は、読書です。今の受験勉強では、読書というものが評価されるのは、国語の成績に関係したときだけです。読書によって、読む力、考える力、感じる力を育てたどうかということは、受験勉強の評価には入りません。 だから、学校の成績では同じぐらいのA君とBさんが、実は、非常に大きな読書力の差を持っているということはあります。その差は、大学入試の段階ではまだはっきりとはわかりません。しかし、子供たちが将来社会に出てから、徐々にその差が明らかになってきます。 勉強は、入試に合格するためにあるのではなく、自分の人生を豊かにするためにあります。中学生や高校生のみなさんは、将来の自分にとって役に立つ学力は何かということを考えて勉強を進めていってください。 |
|
|
||||
| ■ふとしたことから(パンダ/なるこ先生) |
 私は毎週、皆さんから送られてくる作文を添削して返却する際、封筒には特殊切手を貼っています。切手はいつもまとめて何十枚かずつ購入しているのですが、この特殊切手、ほぼ2、3週間に1回の割合で新しいものが発行されていることを知っていましたか? もともと私は、切手収集の趣味はないので、「きれいだなぁ」「使うのがもったいないなぁ」と思いながらも、記念に保存することなく、いつも作文返却用に全部使いきってしまうのですが(笑)、ともかく、毎回様々な行事や文化、そしてアニメなどを題材とした美しい切手を購入して、皆さんへの封筒に貼ることがひとつの楽しみになっています。 私は毎週、皆さんから送られてくる作文を添削して返却する際、封筒には特殊切手を貼っています。切手はいつもまとめて何十枚かずつ購入しているのですが、この特殊切手、ほぼ2、3週間に1回の割合で新しいものが発行されていることを知っていましたか? もともと私は、切手収集の趣味はないので、「きれいだなぁ」「使うのがもったいないなぁ」と思いながらも、記念に保存することなく、いつも作文返却用に全部使いきってしまうのですが(笑)、ともかく、毎回様々な行事や文化、そしてアニメなどを題材とした美しい切手を購入して、皆さんへの封筒に貼ることがひとつの楽しみになっています。 一番最近購入したのは、5月23日に発行された「第1回野口英世アフリカ賞記念」の切手です。もちろん、皆さんの手もとにも2、3通は届いていますよね。10枚つづりで購入したこの切手は、野口英世の肖像が5枚とアフリカ地図と顕微鏡の絵に野口英世のサインが書かれているものが5枚という組み合わせでした(切手を貼るとき、きちんとチェックしていないので、皆さんにはどちらか一方のデザインしか届いていないかもしれませんが、あしからず)。そしてどちらのデザインにも料金表示の下に、この切手の名称が小さく印刷されています。 一番最近購入したのは、5月23日に発行された「第1回野口英世アフリカ賞記念」の切手です。もちろん、皆さんの手もとにも2、3通は届いていますよね。10枚つづりで購入したこの切手は、野口英世の肖像が5枚とアフリカ地図と顕微鏡の絵に野口英世のサインが書かれているものが5枚という組み合わせでした(切手を貼るとき、きちんとチェックしていないので、皆さんにはどちらか一方のデザインしか届いていないかもしれませんが、あしからず)。そしてどちらのデザインにも料金表示の下に、この切手の名称が小さく印刷されています。 ところが、ふと思いました。「はて、このアフリカ賞ってなんだろう?」 野口英世はたしか黄熱病のワクチンを開発したからアフリカなのでしょうけれど、アフリカ賞って何? 恥ずかしながら、私はこの切手の名称である「野口英世アフリカ賞」の意味がわからなかったのです。これはまずいと思い、さっそくこの賞について調べてみました。 ところが、ふと思いました。「はて、このアフリカ賞ってなんだろう?」 野口英世はたしか黄熱病のワクチンを開発したからアフリカなのでしょうけれど、アフリカ賞って何? 恥ずかしながら、私はこの切手の名称である「野口英世アフリカ賞」の意味がわからなかったのです。これはまずいと思い、さっそくこの賞について調べてみました。 「野口英世アフリカ賞」の正式名称は、「野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対する賞」というのだそうです。アフリカでの感染症などの疾病対策のために活動し、その功績がアフリカに住む人々の保健と福祉の向上に貢献した人に授与される賞で、2006年に創設され、今年5月、横浜で開催された第4回アフリカ開発会議において、第1回の授賞式が行われたということです。 「野口英世アフリカ賞」の正式名称は、「野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対する賞」というのだそうです。アフリカでの感染症などの疾病対策のために活動し、その功績がアフリカに住む人々の保健と福祉の向上に貢献した人に授与される賞で、2006年に創設され、今年5月、横浜で開催された第4回アフリカ開発会議において、第1回の授賞式が行われたということです。 野口英世については、たくさんの著書や伝記が出版されています。学校の図書室にも必ず1冊はありますよね。言葉の森でも小学校高学年向けですが、推薦図書として「人間 野口英世」(秋元寿恵夫著 偕成社文庫)を紹介しています。世界的に偉大な医者であり、細菌学者であった野口英世は1876年、福島県の現在の猪苗代町に生まれました。1歳の時、いろりに落ちて左手にやけどを負い、その後15歳で左手の大手術をうけたことをきっかけに医学の道を志すことになります。20歳の若さで医師の資格を取り、その後細菌学の研究に取り組むのですが、その活躍の場は中国、アメリカ、ヨーロッパ、南米と世界に渡りました。そして梅毒や黄熱病の研究によって、多くの人々の命を救うことになったのです。しかし1928年、黄熱病の研究のためにおもむいた西アフリカのガーナにおいて、自ら黄熱病に感染し、研究半ばで51年の生涯を閉じました。 野口英世については、たくさんの著書や伝記が出版されています。学校の図書室にも必ず1冊はありますよね。言葉の森でも小学校高学年向けですが、推薦図書として「人間 野口英世」(秋元寿恵夫著 偕成社文庫)を紹介しています。世界的に偉大な医者であり、細菌学者であった野口英世は1876年、福島県の現在の猪苗代町に生まれました。1歳の時、いろりに落ちて左手にやけどを負い、その後15歳で左手の大手術をうけたことをきっかけに医学の道を志すことになります。20歳の若さで医師の資格を取り、その後細菌学の研究に取り組むのですが、その活躍の場は中国、アメリカ、ヨーロッパ、南米と世界に渡りました。そして梅毒や黄熱病の研究によって、多くの人々の命を救うことになったのです。しかし1928年、黄熱病の研究のためにおもむいた西アフリカのガーナにおいて、自ら黄熱病に感染し、研究半ばで51年の生涯を閉じました。 今年は、ちょうど野口博士の没後80年にあたります。アフリカでは今もHIV/エイズ、マラリア、結核、ポリオなどの感染症がまん延しており、多くの人が亡くなったり苦しんでいます。HIVについては、毎日8800人が感染し、6600人の感染者が死亡しているとも言われるそうです。これはとてもショッキングなことです。日本で平和に暮らしている私達にとっては想像を絶するものですが、アフリカではこうした感染症の他にも、戦争やかんばつなどの被害により、人々の生活は日々脅かされているのです。こうした現状をふまえて、アフリカにおいてもその功績が称えられている野口博士を記念した賞が、アフリカの人々に希望をもたらし、人類の繁栄と世界の平和に貢献することを目指して創設されたわけです。 今年は、ちょうど野口博士の没後80年にあたります。アフリカでは今もHIV/エイズ、マラリア、結核、ポリオなどの感染症がまん延しており、多くの人が亡くなったり苦しんでいます。HIVについては、毎日8800人が感染し、6600人の感染者が死亡しているとも言われるそうです。これはとてもショッキングなことです。日本で平和に暮らしている私達にとっては想像を絶するものですが、アフリカではこうした感染症の他にも、戦争やかんばつなどの被害により、人々の生活は日々脅かされているのです。こうした現状をふまえて、アフリカにおいてもその功績が称えられている野口博士を記念した賞が、アフリカの人々に希望をもたらし、人類の繁栄と世界の平和に貢献することを目指して創設されたわけです。 世界では、時々刻々と様々なことが起きています。まずは、こうした事実を私たちはしっかりと認識しなければいけないと思います。それについて、自分に何ができるのか、何をすべきなのかは、すぐに答えが出ないかもしれませんが、「知る」ということなら、今すぐにでもできることはたくさんありますよね。きっかけはどこにでもあります。私の場合、今回は切手でした。そんな身近なものでも、これまで知らなかった大きな世界を知るきっかけになるのです。ささいなことでも、ふと疑問に思ったり、気になったりしたら、ぜひ皆さんも調べてみてください。心にひっかかった好奇心のかけらを見過ごさないで下さいね。 世界では、時々刻々と様々なことが起きています。まずは、こうした事実を私たちはしっかりと認識しなければいけないと思います。それについて、自分に何ができるのか、何をすべきなのかは、すぐに答えが出ないかもしれませんが、「知る」ということなら、今すぐにでもできることはたくさんありますよね。きっかけはどこにでもあります。私の場合、今回は切手でした。そんな身近なものでも、これまで知らなかった大きな世界を知るきっかけになるのです。ささいなことでも、ふと疑問に思ったり、気になったりしたら、ぜひ皆さんも調べてみてください。心にひっかかった好奇心のかけらを見過ごさないで下さいね。参考資料:政府インターネットテレビ22ch「野口英世アフリカ賞〜ドゥ!JAPAN」(2008年2月12日) |
|
|
||||
| ■書を読むのみに非ざるなり(あこ/やよい先生) |
 「書を読むのみに非ざるなり」 この言葉は、多くの志士を輩出した松下村塾で吉田松陰が言った言葉です。 気概があって節操がかたく、正しいことを行うこと、またそういう人物になることが目指していることであり、いたずらに書物を読んでいるだけではない、という意味です。 吉田松陰という人は小さな頃から厳しく育てられ、スケールの大きな思想を持った人でした。また、それを伝える教育者でもあり、兵学にも通じていました。彼の生き様を語ると、この新聞にはおさまらなくなってしまいますので、それはまたの機会にしたいと思います。 今回は、松陰の言葉を少し紹介したいと思います。 「すべて酸辛(さんしん)」……才能を伸ばし、人としての徳を身に付けることは、つらく、苦しい。 「一日この世にあれば」……人は一日この世の中にいれば、一日分の食事をし、一日分の衣服を着、一日分家や学校にいる。とすれば、一日分の学問、一日分の事業に励まなければいけない。 「能はざるに非ざるなり。為さざるなり。」……できないのではない。やらないのである。  まだまだ多くの言葉が残されていますが、この幾つかの文言を並べただけでも、彼の考え方が垣間見えると思います。彼は、つらいことがあっても力にかえて乗り越えてきました。怠けたい、きついからやりたくないと思う心は誰にでもあります。けれどそこで、何のためにがんばっているのかを考えてほしいと思います。すべてはみなさんを豊かにするための要素なのですよね。 楽しいことから学ぶこともたくさんあります。しかしだからといって、苦しいことから逃げていてはとても大切なことを逃してしまう可能性があります。高く跳びあがるためには、しっかりと低くしゃがまなければならないのと同じで、悩んだり、壁にぶつかることもみなさんの糧となるのです。 国語の勉強は答えがあいまいで、直接的に物事をゴールに導いてくれるテクニックとは言えないかもしれません。実際、教えている生徒から「何の役に立つのー? 」と言われることもよくあります。しかし、私達は「いたずらに書物を読んでいるだけではない」のです。本や文章を読むことで、気持ちを読み取ったり、誰かに気持ちを伝える方法を考えたりします。また、多くの知識を身に付けたり、心を豊かにしたりすることもできます。国語をどこまで広がりのある学問にできるかはみなさん次第なのです。 国語を実りあるものにするには、他の分野の知識や考え方も必要です。松陰もあらゆる方面に通じていたからこそ、広く深い思想を持つことができたのです。 みなさんが今いやいやながら頑張っている勉強とはそういうものなのです。  とはいっても、先生だってきついときにはゴロゴロしたりするけどね(笑)。 |
|
|
|
|
||||
| ■正しい昼寝のしかた(!?)(たんぽぽ/たま先生) |
 いつの頃からか、「昼寝」の習慣がついてしまいました。こう言ってしまうと、なんだか怠け者のように思われないかと、以前は気になったものですが(今は平気です)、皆さんはどう思いますか? 私はいつも午前3時〜4時に起きるのですが(夜は早寝です)、昼食後に一息つくと、眠くてたまらなくなってしまいます。以前は睡魔と闘いながら、必死で体を動かして気合いを入れて乗り切っていましたが、これはもう無理(だって、眠いんです)。年のせいでしょうか?(笑) そこで思い切って昼寝をすることにしました。ただ、ゆっくり眠る時間はないので、10〜15分程度、座って机に顔を伏せて眠っています。目覚めた後は、気分爽快。一日すっきりと過ごすことができるようになりました。体調もよくなり、風邪を引いたりすることも少なくなったように思います。 「昼寝は脳をリラックスさせる」と、その効果は注目されています。昼寝が認知症発症率を低下させるという研究データが厚生労働省の研究班によって報告されていますし、文部科学省でも同様に、昼寝についての研究がまとめられています。以下は、文科省「快適な睡眠の確保に関する総合研究班」がまとめた「正しい昼寝の方法」の一部です。 『研究班は、学生10人に昼寝後15分で起きてもらい、コーヒーの摂取や洗顔など、目覚めに良いとされる行為を試してもらった。効果を確かめるため、脳波を測定して眠気の残り具合を調べた。その結果、「昼寝の直前にコーヒーを飲み、目覚めたら通常より明るい照明を浴びると最も眠気が取れた」という。』(日経BPnetより) 同記事には、目覚まし効果のあるカフェインを含む飲料(コーヒー、お茶、紅茶、ココアも可)を飲んでから寝るとよいと書かれています。カフェインの効果が表れるのは、摂取してからおよそ30分後といわれていますから、昼寝の前にコーヒーを飲んでおけば、目が覚める頃にすっきりするというわけです。私も実行していますが、やはりコーヒーを飲まないときより、飲んだときの方が頭がさえているような気がします。 また、目覚めたら、まず明るい光を浴びることも効果的です。太陽(明るい照明)の光はメラトニンという物質を抑制し、昼と夜の区別をつけます。「光療法」は、昼夜逆転生活の人や時差ぼけの人など睡眠障害の人に効果があることがわかっています。 実行するのに引け目を感じる人もいるかもしれませんが、要は寝起きにぼーっとしてしまわないよう、すっきり目覚めるようにすればいいということです。梅雨の雨音が子守唄になって、午後の授業で居眠りをしてしまうよりも、できるなら昼寝をすることをお勧めします。 
|
|
|
||||