印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■2025年10月保護者懇談会資料
■第4週は清書。幼稚園生は作文(作文クラス)
●清書の意義と方法
●清書の投稿
|
|
||
|
言葉の森新聞
2025年10月3週号 通算第1871号 https://www.mori7.com/mori |
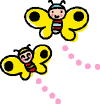
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■2025年10月保護者懇談会資料 |
|
●紙ベースの勉強が基本。デジタルの知識は頭の表面にしか残らない デジタル教科書は、ビジュアルでわかりやすいという長所がありますが、そこで得た知識は頭に残りません。 身につく知識は、紙ベースで得たものです。 なぜかというと、人間が何かを身につけるときは、その情報とともに手触りも身につけるからです。 言葉の森で使っている国数英の問題集は、デジタル化はいつでもできますが、そういうことはせずに紙の問題集としています。 ●学力の基本は日本語力。日本語力の本質は読書と作文(低学年は暗唱) 今、学校や学習塾で行なわれている勉強の多くは知識の勉強です。 知識で評価がつけられるために、子供たちは知識の詰め込みの勉強をせざるを得ません。 しかし、本当にあとに残る学力は知識ではなく考える力です。 その考える力の基本は、日本語力です。 日本語力を育てる勉強は、作文と読書と暗唱です。 ●読書は、読みやすい絵本や学習まんが的なものに流されずに字の多い本を 子供たちが学校や図書館で借りてくる本を見ていると、軽いものが多すぎる気がします。 本を読んでいるからいいと思わずに、本の内容を見る必要があります。 読む力のある子供たちは、字の多い本をしっかり読んでいます。 絵本や学習まんがや図鑑のような本に長されずに字の多い本をしっかり読むようにしていきましょう。 小学校高学年からは、物語文の本に流されずに、説明文意見文の本を読む力をつけていきましょう。 ●作文をきっかけにした親子の対話が子供の語彙力と感想を書く力を伸ばす 小学校34年生の作文の課題に、「似た話を聞く」というものがあります。 これをきっかけにして、お父さんやお母さんが体験談を話してあげてください。 高学年になると、作文の課題は、「人生とは」とか「友情とは」とかいう抽象的なものになります。 ここで親子が楽しく対話をすると、子供の思考力、語彙力が著しく伸びます。 こういう勉強は、ほかでは得られないものです。 ●高校での文系、理系の選択は理系。受験に関係のない科目もしっかり学ぶ 日本では、高校2年生になると文系理系の選択をするところが多いです。 基本は理系を選ぶことです。 高校での勉強は、大学入試のためにやるのではなく、自分自身の成長ためにやるものです。 数学は、これからの社会では、どこでも必要になります。 文系の科目は独学でできますが、理系の科目は授業として強制されなければなかなかできません。 文系の学部や職業を選ぶ人でも、理系の勉強をしておくことが大事です。 ●受験勉強の基本は塾やに行くことではなく、過去問を解いて傾向を考えること 塾や予備校のサービスが豊富なので、勉強というと人に教わるものと考えがちですが、本当の勉強は自分でするものです。 その勉強の基本は、志望校の過去問を解いてみて、その傾向と自分の弱点を分析し、自分で勉強の方針を立てることです。 小学校時代は、塾で教えられる勉強の方がそれなりに能率がいいです。 しかし、高校生になったら、自分で計画と立てて行う勉強はいちばん能率のいい勉強になります、。 ●高校生は今ある職業で未来を考えるのではなく、まず自分の学力をつけること 子供たちは、将来の職業を考えるときに、今の世の中を基準にして考えがちです。 しかし、今ある職業の多くは、将来はなくなります。具体的には書きませんが(笑)。 だから、具体的な職業を考えるのではなく、自分を成長させることを第一に考えることです。 そして、自分が今好きなことは、今の世の中では仕事に結びつかないとしても、その好きなことをずっと続けていくことです。 ●数学と英語は本気でやれば1ヶ月で成績が上がる。国語は半年、作文はそれ以上 成績を上げるのは、時間がかかると思われがちですが、数学と英語は、本気で夏休みの1ヶ月でも勉強すれば驚くほど成績が上がります。 国語は、本気でやっても半年かかります。 作文は、もっとかかります。 しかし、今ある勉強の差は、今だけのものです、 大事なことは、本気でやるかどうかだけです。 ●低学年の勉強の基本はしつけ、そして明るい褒め言葉 低学年の勉強では、知識的なことよりも、まず家庭学習の習慣をつけるようなしつけ的なことを優先することです。 たくさんの勉強をする必要はないので、決まった時間に決まったことをするとか、授業には欠席をしないとか、遅刻しそうなときは連絡を入れるとか、そういう基本的なことを身につけさせることが大事です。 そして、いつも明るい褒め言葉で、子供を励ましていくことです。 |
|
|
||||
| ■第4週は清書。幼稚園生は作文(作文クラス) |
|
幼稚園年中と年長の生徒は、第4週も普通の作文を書く練習です。自由な題名で作文を書いてください。 小学1年生以上の生徒は、清書を行います。 |
| ●清書の意義と方法 |
|
清書とは、これまでに書いた作文の中で内容がよかったものを書き直すことです。 内容がよいとは、個性、感動、共感などがあるということです。 書き直すときは、次の点に留意してください。 (1)漢字で書けるところは漢字で書く。 (2)たとえや自作名言を工夫できるところがあれば工夫する。 (3)似た話や続きの話を書くことによって字数を増やす。 (4)作文用紙の空いているところに絵などをかいてもよい。 |
| ●清書の投稿 |
|
清書した作文は、小学生新聞や一般紙などに投稿してみましょう。 手書きの清書の原本を、新聞社に投稿したり、コンクールに応募したりする場合は、清書のコピーの方を先生に送ってください。 新聞社に投稿する際は、作文用紙の欄外又は別紙に次の事項を記載してください。 (1)本名とふりがな(2)学年(3)自宅の住所(4)自宅の電話番号(5)学校名(市区町村名から)(6)メールアドレス。 投稿する際は、ペンネームを本名に訂正しておいてください。作文の中に友達の名前が固有名詞で入っている場合は、イニシアルなどに直しておいてください。投稿する作文の内容は、保護者がチェックしてあげてください。 同じものを複数の新聞社やコンクールに送らないようにしてください。これは二重投稿といって、もし両方に掲載されてしまった場合、掲載先に迷惑をかけることになります。 ●小学生新聞の投稿先 ■104-8433 東京都中央区築地3-5-4 朝日小学生新聞「ぼくとわたしの作品」係 ■100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日小学生新聞「さくひん」係 ●新聞社に送る清書は市販の原稿用紙に 新聞社に送る清書は、市販の原稿用紙に書いてください。 その理由は、清書は個人で送るものなので、自分で用意した原稿用紙に書くのが、社会的なルールとなるからです。 ※清書した作文を投稿しない場合でも、額などに入れて家の中に飾っておきましょう。 |
|
|