昨日1453 今日1882 合計24095□
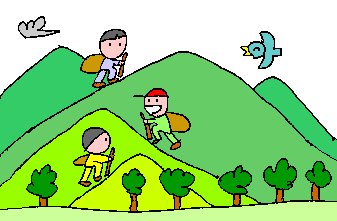 作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1・2・3年生 高校1・2・3年生
心の栽培日記 ノンキィ
日本人は異質で高度な文明に触れたとき、それを驚異的なスピードで取り入れることで欧米に追いついてきた。このような日本人の能力は欧米諸国から物まねであると批判されたが、真似る姿勢こそが独創性を発揮する大前提であり、日本人は物まねだということに過度のコンプレックスを抱く必要はない。
人類の文明は、いつの時代も誰かが誰かの模倣をすることで発展してきた。私の住む町京都は、千年の都として栄えただけに様々な伝統工芸が発達している。京友禅や京扇子、清水焼に西陣織。平安や室町の時代に生まれたそれらの技術が、何百年のときを経て今なお日本中、そして世界中で広く知られている。模倣の影のない伝統工芸など、存在しない。師から弟子へと、絶えることなく受け継がれ、真似をされてきたからこそ価値があるのである。現代の日本では何かを真似ることは負の印象を伴いがちである。けれど私は、真似事から始まる心の庭造りを、積極的に進めていきたい。(主題)
模倣の真価を知るためにはまず、真似事がマイナスのイメージを払拭させる理由を知らなければならない。今日の世界では、多くのIT企業が勢力を増し、人よりも独創的かつ斬新な発想を生み出すものが成功するという考えが広く社会に浸透している。従来の発想を180度転換した画期的な製品が次々登場する。このような新たな革新をもてはやす風潮が、“真似”という行為に二流のレッテルを貼ってしまった。けれど、考えてみて欲しい。二十世紀中頃から急速に進歩するこれらの科学技術は、本当にゼロからスタートしたのかどうか。そんなはずはない。初めて火を使用してから、人類はより精巧な石器を求め、生活の改善を図ってきた。風車や蒸気機関、蓄音機。それらは全て、後の世代の人々が元来のものを模倣し、その上に改良を重ねたものではなかったか。i−Podもウィンドウズもソーラー電池も、皆それらの模倣品ではないのか。真似をすることが私達の文明の歩みを止めずにいる。庭に花の種を植えるとき、その種子をも創造することが出来るだろうか。真似事は何の恥でもないことを、私達は認めるべきである。(方法一)
一方で真似事は、人が何かを得るときの基礎を固める目的以外には何の力も発揮しない。何かを模倣によって手にしたら、次はそれに自力で水をやり、肥料をやって育てていく必要がある。オランダの著名な画家ゴッホは、東洋の浮世絵に高い関心を示し、それを題材とした絵画を何点も残した。私も以前美術の鑑賞の時間にそれらを見たことがあるが、絵の枠組みという点ではほとんど模写といっても良いぐらいだった。ただ、決定的な相違点はその色使いにあった。ゴッホは日本の版画に魅力を感じ、それを自分色に染めて新たな世界を作り出した。どちらがより良いというのではなく、広重の繊細な色使いもゴッホの情熱的で大胆なそれも、それぞれの輝きを放っていた。スポーツをするときもそうだ。大まかなやり方を他から盗むだけでは何事も上達しない。逆上がりも二重跳びもクロールも、その後どれだけ練習し模倣物を我が身に刷り込むかが鍵なのだと思う。真似をして、それで終わりではない。その先に続く道をも背負う覚悟がなければ、せっかくの芽は、伸びることもなく枯れてしまう。(方法二)(伝記)
けれど、ただ単に模倣といっても、法の網にかかるような行為は絶対に回避しなければならない。そう、著作権問題である。私達の幸福が、他の人々の不幸に支えられているのであってはならないように、最低限度守らねばならない約束が社会にたくさん存在する。だが、そもそもそのような規則は真似事を簡単だと思い込む人の軽率な行動を規制させるためのものだろう。他人の庭の花を勝手にもぎ取っていく非常識な人が大勢存在するからなのだろう。種を少し分けてもらうくらい、腹を立てる人はいないはずである。人類の文明にはいつでも模倣の影が伴っていた。そして、きっとこれからも共に発展していく。真似事というレッテルに怯えている場合ではない。正しい模倣をパートナーに迎え、大輪の花を咲かすまで歩みを止めずに生きてゆきたい。(主題)(名言)
日本人は異質で高度な文明に触れたとき、それを驚異的なスピードで取り入れることで欧米に追いついてきた。このような日本人の能力は欧米諸国から物まねであると批判されたが、真似る姿勢こそが独創性を発揮する大前提であり、日本人は物まねだということに過度のコンプレックスを抱く必要はない。
人類の文明は、いつの時代も誰かが誰かの模倣をすることで発展してきた。私の住む町京都は、千年の都として栄えただけに様々な伝統工芸が発達している。京友禅や京扇子、清水焼に西陣織。平安や室町の時代に生まれたそれらの技術が、何百年のときを経て今なお日本中、そして世界中で広く知られている。模倣の影のない伝統工芸など、存在しない。師から弟子へと、絶えることなく受け継がれ、真似をされてきたからこそ価値があるのである。現代の日本では何かを真似ることは負の印象を伴いがちである。けれど私は、真似事から始まる心の庭造りを、積極的に進めていきたい。(主題)
模倣の真価を知るためにはまず、真似事がマイナスのイメージを払拭させる理由を知らなければならない。今日の世界では、多くのIT企業が勢力を増し、人よりも独創的かつ斬新な発想を生み出すものが成功するという考えが広く社会に浸透している。従来の発想を180度転換した画期的な製品が次々登場する。このような新たな革新をもてはやす風潮が、“真似”という行為に二流のレッテルを貼ってしまった。けれど、考えてみて欲しい。二十世紀中頃から急速に進歩するこれらの科学技術は、本当にゼロからスタートしたのかどうか。そんなはずはない。初めて火を使用してから、人類はより精巧な石器を求め、生活の改善を図ってきた。風車や蒸気機関、蓄音機。それらは全て、後の世代の人々が元来のものを模倣し、その上に改良を重ねたものではなかったか。i−Podもウィンドウズもソーラー電池も、皆それらの模倣品ではないのか。真似をすることが私達の文明の歩みを止めずにいる。庭に花の種を植えるとき、その種子をも創造することが出来るだろうか。真似事は何の恥でもないことを、私達は認めるべきである。(方法一)
一方で真似事は、人が何かを得るときの基礎を固める目的以外には何の力も発揮しない。何かを模倣によって手にしたら、次はそれに自力で水をやり、肥料をやって育てていく必要がある。オランダの著名な画家ゴッホは、東洋の浮世絵に高い関心を示し、それを題材とした絵画を何点も残した。私も以前美術の鑑賞の時間にそれらを見たことがあるが、絵の枠組みという点ではほとんど模写といっても良いぐらいだった。ただ、決定的な相違点はその色使いにあった。ゴッホは日本の版画に魅力を感じ、それを自分色に染めて新たな世界を作り出した。どちらがより良いというのではなく、広重の繊細な色使いもゴッホの情熱的で大胆なそれも、それぞれの輝きを放っていた。スポーツをするときもそうだ。大まかなやり方を他から盗むだけでは何事も上達しない。逆上がりも二重跳びもクロールも、その後どれだけ練習し模倣物を我が身に刷り込むかが鍵なのだと思う。真似をして、それで終わりではない。その先に続く道をも背負う覚悟がなければ、せっかくの芽は、伸びることもなく枯れてしまう。(方法二)(伝記)
けれど、ただ単に模倣といっても、法の網にかかるような行為は絶対に回避しなければならない。そう、著作権問題である。私達の幸福が、他の人々の不幸に支えられているのであってはならないように、最低限度守らねばならない約束が社会にたくさん存在する。だが、そもそもそのような規則は真似事を簡単だと思い込む人の軽率な行動を規制させるためのものだろう。他人の庭の花を勝手にもぎ取っていく非常識な人が大勢存在するからなのだろう。種を少し分けてもらうくらい、腹を立てる人はいないはずである。人類の文明にはいつでも模倣の影が伴っていた。そして、きっとこれからも共に発展していく。真似事というレッテルに怯えている場合ではない。正しい模倣をパートナーに迎え、大輪の花を咲かすまで歩みを止めずに生きてゆきたい。(主題)(名言)
講評 nara
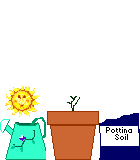 なるほど、「種」のイメージを得たことで、この作文の色合いがはっきりしてきたようだね。第一方法、第二方法、そして主題の各段落を、「種・栽培・花」などに関わる文でまとめたのは、なかなかのテクニックだ。単発の比喩ではなく、このように各段に絡められているのは、いい比喩が見つかった証拠だ。
なるほど、「種」のイメージを得たことで、この作文の色合いがはっきりしてきたようだね。第一方法、第二方法、そして主題の各段落を、「種・栽培・花」などに関わる文でまとめたのは、なかなかのテクニックだ。単発の比喩ではなく、このように各段に絡められているのは、いい比喩が見つかった証拠だ。


 真似をするということがなぜマイナス評価を受けるようになったのだろう。よく言われるのは、日米の貿易摩擦(特に自動車)が契機だということね。第一方法でも述べられているように、そもそも真似がそれほど悪いことではないのは、歴史を振り返れば明らかなことだ。まとめにある著作権問題も含め、真似によって経済的なトラブルが発生するときが「真似はよくない」となりやすいようだ。この経済に重きをおくことは、現代の特徴だね。
真似をするということがなぜマイナス評価を受けるようになったのだろう。よく言われるのは、日米の貿易摩擦(特に自動車)が契機だということね。第一方法でも述べられているように、そもそも真似がそれほど悪いことではないのは、歴史を振り返れば明らかなことだ。まとめにある著作権問題も含め、真似によって経済的なトラブルが発生するときが「真似はよくない」となりやすいようだ。この経済に重きをおくことは、現代の特徴だね。
となると、真似によって得られたものが、直接的かつ利己的な利益の追求(金儲け)につながるときに、真似が持つプラスの意味合いが否定されるのではないか、と考えることもできそうだね。日本人が「エコノミックアニマル」と呼ばれたことも、関連づけができそうだ。
 ゴッホもスポーツも独創性が評価されているけれど、それは独善ではない。独創性はどうやって生まれるか、ということを無視して、できあがったものだけをもてはやすのは、あまりにも近視眼的なとらえ方だね。言葉の森の課題週「ネコヤナギ3.2週」の長文が参考になると思うので、是非目を通しておいてね。
ゴッホもスポーツも独創性が評価されているけれど、それは独善ではない。独創性はどうやって生まれるか、ということを無視して、できあがったものだけをもてはやすのは、あまりにも近視眼的なとらえ方だね。言葉の森の課題週「ネコヤナギ3.2週」の長文が参考になると思うので、是非目を通しておいてね。
 これは2週目の長文だね。1週目で登録されていたので、訂正しておくよ。
これは2週目の長文だね。1週目で登録されていたので、訂正しておくよ。
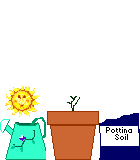 なるほど、「種」のイメージを得たことで、この作文の色合いがはっきりしてきたようだね。第一方法、第二方法、そして主題の各段落を、「種・栽培・花」などに関わる文でまとめたのは、なかなかのテクニックだ。単発の比喩ではなく、このように各段に絡められているのは、いい比喩が見つかった証拠だ。
なるほど、「種」のイメージを得たことで、この作文の色合いがはっきりしてきたようだね。第一方法、第二方法、そして主題の各段落を、「種・栽培・花」などに関わる文でまとめたのは、なかなかのテクニックだ。単発の比喩ではなく、このように各段に絡められているのは、いい比喩が見つかった証拠だ。

 真似をするということがなぜマイナス評価を受けるようになったのだろう。よく言われるのは、日米の貿易摩擦(特に自動車)が契機だということね。第一方法でも述べられているように、そもそも真似がそれほど悪いことではないのは、歴史を振り返れば明らかなことだ。まとめにある著作権問題も含め、真似によって経済的なトラブルが発生するときが「真似はよくない」となりやすいようだ。この経済に重きをおくことは、現代の特徴だね。
真似をするということがなぜマイナス評価を受けるようになったのだろう。よく言われるのは、日米の貿易摩擦(特に自動車)が契機だということね。第一方法でも述べられているように、そもそも真似がそれほど悪いことではないのは、歴史を振り返れば明らかなことだ。まとめにある著作権問題も含め、真似によって経済的なトラブルが発生するときが「真似はよくない」となりやすいようだ。この経済に重きをおくことは、現代の特徴だね。となると、真似によって得られたものが、直接的かつ利己的な利益の追求(金儲け)につながるときに、真似が持つプラスの意味合いが否定されるのではないか、と考えることもできそうだね。日本人が「エコノミックアニマル」と呼ばれたことも、関連づけができそうだ。
 ゴッホもスポーツも独創性が評価されているけれど、それは独善ではない。独創性はどうやって生まれるか、ということを無視して、できあがったものだけをもてはやすのは、あまりにも近視眼的なとらえ方だね。言葉の森の課題週「ネコヤナギ3.2週」の長文が参考になると思うので、是非目を通しておいてね。
ゴッホもスポーツも独創性が評価されているけれど、それは独善ではない。独創性はどうやって生まれるか、ということを無視して、できあがったものだけをもてはやすのは、あまりにも近視眼的なとらえ方だね。言葉の森の課題週「ネコヤナギ3.2週」の長文が参考になると思うので、是非目を通しておいてね。 これは2週目の長文だね。1週目で登録されていたので、訂正しておくよ。
これは2週目の長文だね。1週目で登録されていたので、訂正しておくよ。
毎月の学年別「森リン大賞」作品集森リンの丘
自動採点ソフト「森リン」で上位になった作文を掲載しています。
しかし、子供たちの実力はそれぞれ個性的です。上手に書けている子の作文を見せて、自分の子供の作文と比較しないようにお願いします。
|
作文教室受講案内
無料体験学習
作文講師資格 |
| ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |
| お電話によるお問合せは、0120-22-3987(平日9:00-19:30) |
