昨日1453 今日1914 合計24127□
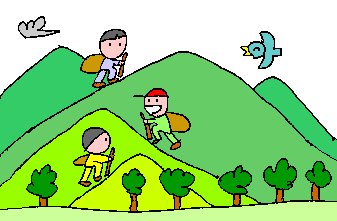 作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1・2・3年生 高校1・2・3年生
もう三十年も前の(感) セコイア
当時の日本の工業製品は、まだ性能的にも機能的にもかなりお粗末で、欧米に対抗できるのは価格だけと言われていた時代である。自動車も例外ではなかった。それが今では、「made in Japan」といえば、性能の良さ、信頼性の高さの代名詞にさえなっている。技術後精神国だった日本は、欧米に追いつこうと懸命にキャッチアップを続けた結果、わずか30年で追いつき、追い越してしまったのである。にもかかわらず、現代の日本人は、この驚異的な速さのキャッチアップを可能にしてきた自らの潜在能力に誇りを持っていない。それは、「もの真似上手」という批判を浴び続けてきたからである。そして真似することが独創性の欠如であるように言われてきた。しかし、かつての日本では学ぶということは、徹底して「真似る」ことだったのである。そして基本技術を十分にマスターした上で、やがては学んだものと離れて、まったく独創的な方式を確立し、新たな流派を形成していった。日本人は「もの真似上手」と言われることに過度のコンプレックスを抱く必要はないのである。(要約)私は、「真似」することに自信を持って生きていきたい。(生き方の主題)
その方法としては第一に、自分の得意なところを知ることである。人とは違う自分の個性を生かしていくためにも、まず自分の得意なスポーツ・勉強・趣味などを知ることは大切なことだ。例えば、絵なら最初は有名なレオナルドダビンチやゴッホ、ピカソなどの画家が描いたのを「真似」することから始めればよい。自分が絵を描くことが楽しくて好きになり、もっと描いてみたいと思ったなら、自分に合った描き方を選んでいけばいいと思う。油絵や鉛筆で白黒にして描くなど、いろいろな描き方がある。私と妹も絵をよく描くが、全然違うやり方をする。私は白黒で、妹は色鉛筆を使ってカラフルに描く。(体験実例)また、ライト兄弟は人類初動力飛行を行った人として世界中で有名である。彼らは元自動車屋だったが、のちに航空研究家になった。しかし、彼らが飛行機をつくれた秘密は、鳥にあった。鳥が空を飛ぶ様子を粘り強く観察し、そして「真似」をしたのだ。(伝記実例)
また第二の方法としては、自分の苦手なところも知ることである。(複数の方法二)自分の得意な所だけではなく、苦手な所を前から知っておくことは必要だ。そうしたら、もし苦手な所を間違えても落ち込まなくても済むだろう。与謝蕪村のこういう俳句がある。「遠近(おちこち)に 滝の音聞く 若ばかな」(詩の引用)滝のザーという大きな音、青緑の若葉などのきれいな風景が身に見えるように一瞬にして頭に浮かんでくる。俳句の基礎である5・7・5のルールに合わせて詠んでいるだけだが、それに与謝蕪村の素晴らしい感性が一つになっているのがこの詩だ。だから、この詩を詠む、人々の心を捉えるのだと思う。
確かに、「個性」や「独創性」を重視することももちろん大切だ。(反対意見への理解)しかし、「雑草とは、まだ、その美点が発見されていない植物のことである。」という名言(言葉)もある。(名言の引用)雑草は、まるで「真似」をすることのようだ。(たとえ) 「自分らしさ」はすべて始めから出来てくるのではなく、「真似」することから始まるのである。だから、私は「真似」することにコンプレックスを抱かず、どうどうと自信を持って生きていきたい。
「まず、真似をしよう!!」(笑)(ユーモア表現)
当時の日本の工業製品は、まだ性能的にも機能的にもかなりお粗末で、欧米に対抗できるのは価格だけと言われていた時代である。自動車も例外ではなかった。それが今では、「made in Japan」といえば、性能の良さ、信頼性の高さの代名詞にさえなっている。技術後精神国だった日本は、欧米に追いつこうと懸命にキャッチアップを続けた結果、わずか30年で追いつき、追い越してしまったのである。にもかかわらず、現代の日本人は、この驚異的な速さのキャッチアップを可能にしてきた自らの潜在能力に誇りを持っていない。それは、「もの真似上手」という批判を浴び続けてきたからである。そして真似することが独創性の欠如であるように言われてきた。しかし、かつての日本では学ぶということは、徹底して「真似る」ことだったのである。そして基本技術を十分にマスターした上で、やがては学んだものと離れて、まったく独創的な方式を確立し、新たな流派を形成していった。日本人は「もの真似上手」と言われることに過度のコンプレックスを抱く必要はないのである。(要約)私は、「真似」することに自信を持って生きていきたい。(生き方の主題)
その方法としては第一に、自分の得意なところを知ることである。人とは違う自分の個性を生かしていくためにも、まず自分の得意なスポーツ・勉強・趣味などを知ることは大切なことだ。例えば、絵なら最初は有名なレオナルドダビンチやゴッホ、ピカソなどの画家が描いたのを「真似」することから始めればよい。自分が絵を描くことが楽しくて好きになり、もっと描いてみたいと思ったなら、自分に合った描き方を選んでいけばいいと思う。油絵や鉛筆で白黒にして描くなど、いろいろな描き方がある。私と妹も絵をよく描くが、全然違うやり方をする。私は白黒で、妹は色鉛筆を使ってカラフルに描く。(体験実例)また、ライト兄弟は人類初動力飛行を行った人として世界中で有名である。彼らは元自動車屋だったが、のちに航空研究家になった。しかし、彼らが飛行機をつくれた秘密は、鳥にあった。鳥が空を飛ぶ様子を粘り強く観察し、そして「真似」をしたのだ。(伝記実例)
また第二の方法としては、自分の苦手なところも知ることである。(複数の方法二)自分の得意な所だけではなく、苦手な所を前から知っておくことは必要だ。そうしたら、もし苦手な所を間違えても落ち込まなくても済むだろう。与謝蕪村のこういう俳句がある。「遠近(おちこち)に 滝の音聞く 若ばかな」(詩の引用)滝のザーという大きな音、青緑の若葉などのきれいな風景が身に見えるように一瞬にして頭に浮かんでくる。俳句の基礎である5・7・5のルールに合わせて詠んでいるだけだが、それに与謝蕪村の素晴らしい感性が一つになっているのがこの詩だ。だから、この詩を詠む、人々の心を捉えるのだと思う。
確かに、「個性」や「独創性」を重視することももちろん大切だ。(反対意見への理解)しかし、「雑草とは、まだ、その美点が発見されていない植物のことである。」という名言(言葉)もある。(名言の引用)雑草は、まるで「真似」をすることのようだ。(たとえ) 「自分らしさ」はすべて始めから出来てくるのではなく、「真似」することから始まるのである。だから、私は「真似」することにコンプレックスを抱かず、どうどうと自信を持って生きていきたい。
「まず、真似をしよう!!」(笑)(ユーモア表現)
講評 unagi
<1> 要約:要所がまとめられました。主題:「真似することに自信を持つ」
<2> 方法①「自分の得意とするところを知る」:絵画の巨匠たちやライト兄弟の伝記実例を上
手く取り入れて、方法①を説明しています。身近な例として、妹さんとの比較を書いたのも興味深いです。「粘り強く観察」というところがポイントとなるでしょう。
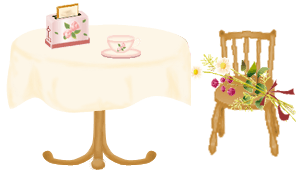
<3>方法②「苦手分野も把握する」:「落ち込まなくても済む」確かにそうですね。基本の形を押さえておけば落ち込んでも再起に活かせるという大きな意味で(ですね?)、詩の引用に成功しています。
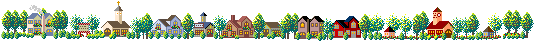
<4>反対意見でバランスを取ったあと、まとめに入ります。「雑草とは・・・。」適切な名言を引用しています。また、深い含蓄のある比喩を挿入していますね。「自分らしさはすべて・・・。」この一文が、唐突感を与えずに読み手に考え方をしっかりと伝える機能を果たしています。締めくくりにユーモアを加えることを忘れないその余裕がいいです。
<1> 要約:要所がまとめられました。主題:「真似することに自信を持つ」
<2> 方法①「自分の得意とするところを知る」:絵画の巨匠たちやライト兄弟の伝記実例を上
手く取り入れて、方法①を説明しています。身近な例として、妹さんとの比較を書いたのも興味深いです。「粘り強く観察」というところがポイントとなるでしょう。
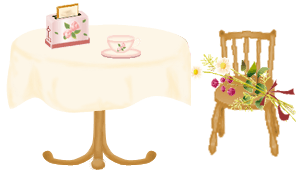
<3>方法②「苦手分野も把握する」:「落ち込まなくても済む」確かにそうですね。基本の形を押さえておけば落ち込んでも再起に活かせるという大きな意味で(ですね?)、詩の引用に成功しています。
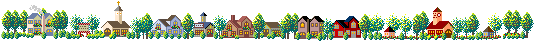
<4>反対意見でバランスを取ったあと、まとめに入ります。「雑草とは・・・。」適切な名言を引用しています。また、深い含蓄のある比喩を挿入していますね。「自分らしさはすべて・・・。」この一文が、唐突感を与えずに読み手に考え方をしっかりと伝える機能を果たしています。締めくくりにユーモアを加えることを忘れないその余裕がいいです。
毎月の学年別「森リン大賞」作品集森リンの丘
自動採点ソフト「森リン」で上位になった作文を掲載しています。
しかし、子供たちの実力はそれぞれ個性的です。上手に書けている子の作文を見せて、自分の子供の作文と比較しないようにお願いします。
|
作文教室受講案内
無料体験学習
作文講師資格 |
| ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |
| お電話によるお問合せは、0120-22-3987(平日9:00-19:30) |
