昨日2610 今日97 合計24920□
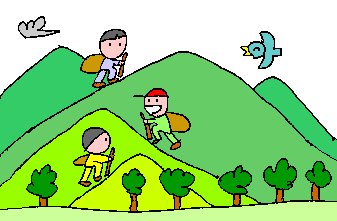 作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1・2・3年生 高校1・2・3年生
模倣 ビーバー
もう三〇年も前のことだが、一九六〇年代の中ごろ、ヨーロッパの街角で初めて日本車が走つているのを見たとき、涙が出るほど感激したことがある。当時の日本の工業製品は、まだ性能的にも機能的にもかなりお粗末で、欧米に対抗できるのは価格だけといわれていた時代である。それが、今では「メイド・イン・ジャパン」といえば、性能の良さ、信頼性の高さの代名詞にさえなっている。一言でいえば、最新技術を受け入れ、消化するだけの素地=潜在能力が、既に日本にあったということである。日本人が「もの真似上手」と言われることに、過度のコンプレックスを抱く必要はまったくないのである。(要約)私は、技術を真似するのがうまいというのは誇りに思うべきだと思う。私は、相手から学ぶという行為をうまく出来るような人間になりたい。
そうなるための第一の方法は、まず観察眼を養うことである。僕がまだ中学野球部に所属していた時、よく顧問の先生からこう言われた。「自分より上のものの技術、顧問の言っていることをしっかり頭に残してそこから応用しなさい。とにかく技術をみて盗め。」と。今思うと、これが一番効率のいいやり方だったのだ。例を挙げると、バッティングの時である。顧問の先生の手本を見ながらフォームを注意深く観察し、体の各部分がどのように動いているか、などをしっかり観察する。観察が一部一部できたら自分で動きを納得するまで再現してみて、そして完璧といわれるフォームに矯正していく。このやり方によってかなり球がバットに当たるようになったし、初期に比べれば不恰好でなくなった。このとき、人のやり方、基本のやり方を観察してマスターしていくというのはとても重要なことなのだなと実感した。この例から、観察眼が技術力アップには欠かせないのだということも実感できた。
第二の方法は、学校教育の一環に先人の知恵を模倣し自分流にアレンジしてみる、というものを加えることだ。ガウスなどの数学者の伝記の一部を見てみると、先人の発見した定理や公式などを何か別の定理や公式などに変えることは出来ないかといろいろ試してみて、結局発展をさせているという歴史上の事実が多くある。はじめは独創性の強い物から始まったものかもしれないが、発展をさせることで数学界に大きな影響をもたらしている。このような史実から、自分流に改良していくという模倣の一部である行為が偉大な発見に役立っている、ということも分かる。模倣力があるというのは真似してばかりというマイナスイメージだけでなく、物事の発展にも役立っているというプラスのイメージもあるのだ。
確かに、真似だけでは進展なしでつまらないし、「創造する力」というものも人間としての基本要素であると思う。しかし、「辞書のような人間になることではなく辞書をうまく使えるような人間になることが勉強の目的である。」という言葉に表されるように、自分が独創して周りに技術を広めるだけでなく、自分が独創された原型からそれを模倣し新しい物を作り出す、つまり名言の中で言う「使う」の部分こそがこれから必要になってくるであろう。だから私は、これからの世の中に必要になってくる模倣力を鍛え、うまく使えるような人間になりたいと思う。
もう三〇年も前のことだが、一九六〇年代の中ごろ、ヨーロッパの街角で初めて日本車が走つているのを見たとき、涙が出るほど感激したことがある。当時の日本の工業製品は、まだ性能的にも機能的にもかなりお粗末で、欧米に対抗できるのは価格だけといわれていた時代である。それが、今では「メイド・イン・ジャパン」といえば、性能の良さ、信頼性の高さの代名詞にさえなっている。一言でいえば、最新技術を受け入れ、消化するだけの素地=潜在能力が、既に日本にあったということである。日本人が「もの真似上手」と言われることに、過度のコンプレックスを抱く必要はまったくないのである。(要約)私は、技術を真似するのがうまいというのは誇りに思うべきだと思う。私は、相手から学ぶという行為をうまく出来るような人間になりたい。
そうなるための第一の方法は、まず観察眼を養うことである。僕がまだ中学野球部に所属していた時、よく顧問の先生からこう言われた。「自分より上のものの技術、顧問の言っていることをしっかり頭に残してそこから応用しなさい。とにかく技術をみて盗め。」と。今思うと、これが一番効率のいいやり方だったのだ。例を挙げると、バッティングの時である。顧問の先生の手本を見ながらフォームを注意深く観察し、体の各部分がどのように動いているか、などをしっかり観察する。観察が一部一部できたら自分で動きを納得するまで再現してみて、そして完璧といわれるフォームに矯正していく。このやり方によってかなり球がバットに当たるようになったし、初期に比べれば不恰好でなくなった。このとき、人のやり方、基本のやり方を観察してマスターしていくというのはとても重要なことなのだなと実感した。この例から、観察眼が技術力アップには欠かせないのだということも実感できた。
第二の方法は、学校教育の一環に先人の知恵を模倣し自分流にアレンジしてみる、というものを加えることだ。ガウスなどの数学者の伝記の一部を見てみると、先人の発見した定理や公式などを何か別の定理や公式などに変えることは出来ないかといろいろ試してみて、結局発展をさせているという歴史上の事実が多くある。はじめは独創性の強い物から始まったものかもしれないが、発展をさせることで数学界に大きな影響をもたらしている。このような史実から、自分流に改良していくという模倣の一部である行為が偉大な発見に役立っている、ということも分かる。模倣力があるというのは真似してばかりというマイナスイメージだけでなく、物事の発展にも役立っているというプラスのイメージもあるのだ。
確かに、真似だけでは進展なしでつまらないし、「創造する力」というものも人間としての基本要素であると思う。しかし、「辞書のような人間になることではなく辞書をうまく使えるような人間になることが勉強の目的である。」という言葉に表されるように、自分が独創して周りに技術を広めるだけでなく、自分が独創された原型からそれを模倣し新しい物を作り出す、つまり名言の中で言う「使う」の部分こそがこれから必要になってくるであろう。だから私は、これからの世の中に必要になってくる模倣力を鍛え、うまく使えるような人間になりたいと思う。
講評 nane
要約うまい。ただし、ここは状況実例でまとめてもいいからね。
▲僕→私(僕は学生用語なので)
第二段落のバッティングの実例は具体的でよくわかる。このあたりを中心に【清書候補】。
第三段落の、改良が大きな発見や発明につながる、という例を見つけておこう。例えば、ひらがなは、漢字の模倣として生まれたが、表音文字という点で漢字にはない長所も持つようになった、など。
結びの「辞書を『使う』」に着目したところは、考える力がある。この部分も清書に盛り込もう。
傑作。

要約うまい。ただし、ここは状況実例でまとめてもいいからね。
▲僕→私(僕は学生用語なので)
第二段落のバッティングの実例は具体的でよくわかる。このあたりを中心に【清書候補】。
第三段落の、改良が大きな発見や発明につながる、という例を見つけておこう。例えば、ひらがなは、漢字の模倣として生まれたが、表音文字という点で漢字にはない長所も持つようになった、など。
結びの「辞書を『使う』」に着目したところは、考える力がある。この部分も清書に盛り込もう。
傑作。

毎月の学年別「森リン大賞」作品集森リンの丘
自動採点ソフト「森リン」で上位になった作文を掲載しています。
しかし、子供たちの実力はそれぞれ個性的です。上手に書けている子の作文を見せて、自分の子供の作文と比較しないようにお願いします。
|
作文教室受講案内
無料体験学習
作文講師資格 |
| ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |
| お電話によるお問合せは、0120-22-3987(平日9:00-19:30) |
