昨日2610 今日314 合計25137□
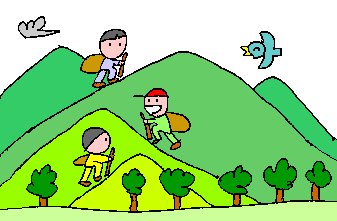 作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1・2・3年生 高校1・2・3年生
昔話の研究を(感) セコイア
昔話の研究をすることは、そこに隠された民衆の知恵のようなものを感じ取ることにより、現代に生きる我々に対しても思いがけぬ示唆を与えてくれる。日本の昔話にはよく老人が登場することに気付かされるであろう。「姥捨て山」という物語では、老人の知恵の必要性を示している。老人は何もできない、能率的でないから駄目だと言う。しかしこれを逆転して考えてみると、老人は何もしないし非能率的だから価値があるということにもなる。実際、我々把握策働き、のウルツや進歩を追及してきて、本当に幸福になったであろうか。物質的豊かさと精神の貧しさに病んでいないだろうか。また「貧乏神」という昔話では、思いやりの大切さや貧乏なことについて教えている。昔話に見られる類話の多様性は、人生の問題の解決法の多様性を示している。昔話を読むことは、現代の我々の生き方と直接につながってくるのである。(要約)私は、昔話から生き方を学びたい。(生き方の主題)
そのための方法としては第一に、子供時代に昔話をたくさん読むことである。(複数の方法一)小さい頃読んだ話は、私たちが大人になってもなかなか忘れない。さらに、自国の文化を知るという点でも大切だ。またヨーロッパなどの海外の有名な本を読むのは、大きくなってからでも十分間に合う。私も小さい頃「花咲かじいさん」「桃太郎」「浦島太郎」「かさ地蔵」などの物語を読んでもらっていた。日本の昔話ではないが、「マッチ売りの少女」から、この世には飢えている人々がたくさんいることといかに私たちが恵まれているかを教えられた。
また第二の方法としては、老人に対する偏見をなくすことである。(複数の方法二)現代人は、科学が進歩している生活の中でスムーズに暮らしている。しかし、老人はコンピューターやDVDなどの新しいものが上手く使えない。だから、昔の人は知恵が無いというわけではないのだ。今の便利で快適な暮らしが出来るのも、昔の人のおかげである。彼らは知恵をしぼって、どのようにしたら不便で貧乏な暮らしから逃れられるかということを考えてきたのだ。だから、今の生活がある。これは少し「かさ地蔵」のような話だと思う。おじいさんは、貧しい生活をしていたが、雪に埋もれそうな地蔵様に傘をかぶせてあげる。そしてその夜、傘を持ったお地蔵様がお礼にたくさん食べ物(米やもち)を持ってきてくれたということだ。おじいさんは、もう貧しいという心配事を解決してしまった。(伝記実例)だから、私たちは普通の日常生活の中でもお年寄りの話を聞くなど大切にしなければならない。「我と来て 遊べや親の ない雀」これは、小林一茶が書いた、私のお気に入りの詩である。この詩を書いたのはたぶん、一茶がボーと外を見ていた時だと思う。老人もそんなことをよくするが、小林一茶が素敵な詩を書いたように、老人もいろいろな役割を果たしていると思う。(詩の引用)
確かに、現代の最先端の技術や医療、また知識はもちろん大切だ。私たちは、それらなしでは生きていけないかもしれない。(反対意見への理解)「悪書を読まないことは、良書を読むための最初の条件である」という名言(言葉)もある。(名言の引用)まず私たちは、昔話を読んでそこからいろいろな人々の生き方を学んで勉強すればよい。私は、幼稚また小さい子向けと思われている昔話から生き方を学びたいと考える。(生き方の主題)
「私たちももう一回昔話を読み返そう。」(笑)(ユーモア表現)
昔話の研究をすることは、そこに隠された民衆の知恵のようなものを感じ取ることにより、現代に生きる我々に対しても思いがけぬ示唆を与えてくれる。日本の昔話にはよく老人が登場することに気付かされるであろう。「姥捨て山」という物語では、老人の知恵の必要性を示している。老人は何もできない、能率的でないから駄目だと言う。しかしこれを逆転して考えてみると、老人は何もしないし非能率的だから価値があるということにもなる。実際、我々把握策働き、のウルツや進歩を追及してきて、本当に幸福になったであろうか。物質的豊かさと精神の貧しさに病んでいないだろうか。また「貧乏神」という昔話では、思いやりの大切さや貧乏なことについて教えている。昔話に見られる類話の多様性は、人生の問題の解決法の多様性を示している。昔話を読むことは、現代の我々の生き方と直接につながってくるのである。(要約)私は、昔話から生き方を学びたい。(生き方の主題)
そのための方法としては第一に、子供時代に昔話をたくさん読むことである。(複数の方法一)小さい頃読んだ話は、私たちが大人になってもなかなか忘れない。さらに、自国の文化を知るという点でも大切だ。またヨーロッパなどの海外の有名な本を読むのは、大きくなってからでも十分間に合う。私も小さい頃「花咲かじいさん」「桃太郎」「浦島太郎」「かさ地蔵」などの物語を読んでもらっていた。日本の昔話ではないが、「マッチ売りの少女」から、この世には飢えている人々がたくさんいることといかに私たちが恵まれているかを教えられた。
また第二の方法としては、老人に対する偏見をなくすことである。(複数の方法二)現代人は、科学が進歩している生活の中でスムーズに暮らしている。しかし、老人はコンピューターやDVDなどの新しいものが上手く使えない。だから、昔の人は知恵が無いというわけではないのだ。今の便利で快適な暮らしが出来るのも、昔の人のおかげである。彼らは知恵をしぼって、どのようにしたら不便で貧乏な暮らしから逃れられるかということを考えてきたのだ。だから、今の生活がある。これは少し「かさ地蔵」のような話だと思う。おじいさんは、貧しい生活をしていたが、雪に埋もれそうな地蔵様に傘をかぶせてあげる。そしてその夜、傘を持ったお地蔵様がお礼にたくさん食べ物(米やもち)を持ってきてくれたということだ。おじいさんは、もう貧しいという心配事を解決してしまった。(伝記実例)だから、私たちは普通の日常生活の中でもお年寄りの話を聞くなど大切にしなければならない。「我と来て 遊べや親の ない雀」これは、小林一茶が書いた、私のお気に入りの詩である。この詩を書いたのはたぶん、一茶がボーと外を見ていた時だと思う。老人もそんなことをよくするが、小林一茶が素敵な詩を書いたように、老人もいろいろな役割を果たしていると思う。(詩の引用)
確かに、現代の最先端の技術や医療、また知識はもちろん大切だ。私たちは、それらなしでは生きていけないかもしれない。(反対意見への理解)「悪書を読まないことは、良書を読むための最初の条件である」という名言(言葉)もある。(名言の引用)まず私たちは、昔話を読んでそこからいろいろな人々の生き方を学んで勉強すればよい。私は、幼稚また小さい子向けと思われている昔話から生き方を学びたいと考える。(生き方の主題)
「私たちももう一回昔話を読み返そう。」(笑)(ユーモア表現)
講評 unagi
<1>要約をクリアしました。生き方の主題:「昔話から生き方を学びたい」
<2>方法①「子供時代に読んでおく」:自国の文化を知るために子供のうちに、という意見を説く段落です。具体的な作品名を挙げて分かりやすく説明することができました。惜しい点を1つだけ。この文脈からいくと『マッチ売りの少女』ではなく日本の昔話から学んだことを挙げるか、もしくは「海外の有名な本」を「(国内外を問わず)昔話以外全般の作品」という意味の内容を当てたほうが矛盾が無いです。

<3>方法②「老人への偏見をなくす」:「彼らは知恵をしぼって・・・。」説得力があります。また、良い俳句を引用していますね。「一茶がボーと外を・・・。」きっとそうでしょう。

<4>反対意見をクリアしました。名言から主題への流れもスムーズな運びとなっていますね。最後のユーモアは「私たちももう一回・・・。」なかなか楽しいと思いますよ。
<1>要約をクリアしました。生き方の主題:「昔話から生き方を学びたい」
<2>方法①「子供時代に読んでおく」:自国の文化を知るために子供のうちに、という意見を説く段落です。具体的な作品名を挙げて分かりやすく説明することができました。惜しい点を1つだけ。この文脈からいくと『マッチ売りの少女』ではなく日本の昔話から学んだことを挙げるか、もしくは「海外の有名な本」を「(国内外を問わず)昔話以外全般の作品」という意味の内容を当てたほうが矛盾が無いです。

<3>方法②「老人への偏見をなくす」:「彼らは知恵をしぼって・・・。」説得力があります。また、良い俳句を引用していますね。「一茶がボーと外を・・・。」きっとそうでしょう。

<4>反対意見をクリアしました。名言から主題への流れもスムーズな運びとなっていますね。最後のユーモアは「私たちももう一回・・・。」なかなか楽しいと思いますよ。
毎月の学年別「森リン大賞」作品集森リンの丘
自動採点ソフト「森リン」で上位になった作文を掲載しています。
しかし、子供たちの実力はそれぞれ個性的です。上手に書けている子の作文を見せて、自分の子供の作文と比較しないようにお願いします。
|
作文教室受講案内
無料体験学習
作文講師資格 |
| ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |
| お電話によるお問合せは、0120-22-3987(平日9:00-19:30) |
