昨日1453 今日2521 合計24734□
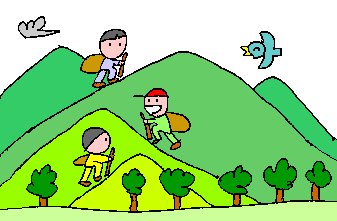 作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1・2・3年生 高校1・2・3年生
生きる基盤 れもん
酒鬼薔薇事件や、長崎の佐世保事件。現代の日本では、ほんの最近起きた、これらの事件が忘れられるほど、また新たな凶悪事件が多発している。凶悪事件の犯人の低年齢化、これは今に始まったことではない。戦後の日本の民主主義の発展と共に、核家族化が進み、人間性や文化など、いわゆる長老の知恵のようなものが、反映されなくなった結果なのである。私の通っていた小学校には、図書の授業というものがあった。少し風変わりな先生が、わざと小学生相手に哲学的な難しい質問を投げかけ、私たちは相当困惑した思い出がある。そんな中でも、特に印象的だったのが、昔話を選択して読む授業のときに、低年齢の犯罪者は、だいたい幼い頃、極端に本を読まなかった人が多いということだ。想像力を駆使して、本の中の現実を疑似体験する一般図書も、勿論大切だが、本の中でも特に、昔話の分野には、特に道理に適った現実が描かれているという。私は、昔話を活かすような生き方をしたい。(生き方)
第一の方法としては、幼稚だからと昔話を拒絶せずに、その中から人生の教訓を見出す積極的な読み方をすることだ。昔話は確かに非日常的な世界を舞台に描かれているため、一見、取っ付きにくい印象もある。実際読んでみると、話の展開は予期していた通り順調に流れ、最後にひょっと不意をつかれる。昔話が幼稚だと言われる由縁は、そこから来ているのかもしれない。現代文学のような、複雑なひねりはなく、素直に教訓を示している。幼稚園の頃、繰り返し読んだ「かさじぞう」の話は、十年近く経った今でも鮮明に思い出せる。おそらくそれは、「かさじぞう」の教訓が、私の基盤の欠片となりえているからだろう。このように、昔話には単純だからこそ、示すことのできる、人生の教訓のようなものが凝縮されている。考えてみれば、道理も人間性も、人間なら単純に理解できるようなものである。しかし、私たちはそんな単純さに遠回りして気づくのだ。一度、昔話の中で、単純な教訓を経験しておくことで、人間らしく生きることができるだろう。(複数の方法Ⅰ)
第二の方法としては、昔話を生き方に直接、反映させ、受け継いでいくことだ。『古代への情熱』の著書シュリーマンは、子供のころに絵本で読んだトロイ戦争を信じ、独力でトロイの都を発掘した。昔話には時を越えた説得力があるように、私は感じる。昔話には、何百年、何千年前に生きた人々の人生から得た知恵が記されているのだ。それは、昔話に限ったことではない。ことわざや短歌など、日本に伝統的に根付いている文化にも同じことがいえる。しかし、そこで面白いのが、ことわざには両極端のものが存在するということだ。例えば、「三度目の正直」と「二度あることは三度ある」という二つのことわざだ。これらのことわざは、ただ単に、キレイ言だけでは終わらせずに、生きる上での矛盾や物事のつながりを、正直に示唆しているように思える。だからこそ、昔話やことわざには、生きる上で、身近な事柄として受け入れることができるのだ。(複数の方法Ⅱ)(伝記)
確かに、現代の最新の技術や思想を吸収することも大切だ。しかし、私たちの生命の根本に、昔話や昔の思想が息づいていることを忘れてはいけない。悪書を読まないことは、良書を読むための最初の条件である。まず、私たちは、積極的に文化と関わる機会を設け、昔の思想から、生きる基盤を学ぶべきである。私は、最先端のものだけに囚われずに、しっかりと頑丈な基盤を重んじて生きていきたい。(反対意見)(名言)(生き方)
酒鬼薔薇事件や、長崎の佐世保事件。現代の日本では、ほんの最近起きた、これらの事件が忘れられるほど、また新たな凶悪事件が多発している。凶悪事件の犯人の低年齢化、これは今に始まったことではない。戦後の日本の民主主義の発展と共に、核家族化が進み、人間性や文化など、いわゆる長老の知恵のようなものが、反映されなくなった結果なのである。私の通っていた小学校には、図書の授業というものがあった。少し風変わりな先生が、わざと小学生相手に哲学的な難しい質問を投げかけ、私たちは相当困惑した思い出がある。そんな中でも、特に印象的だったのが、昔話を選択して読む授業のときに、低年齢の犯罪者は、だいたい幼い頃、極端に本を読まなかった人が多いということだ。想像力を駆使して、本の中の現実を疑似体験する一般図書も、勿論大切だが、本の中でも特に、昔話の分野には、特に道理に適った現実が描かれているという。私は、昔話を活かすような生き方をしたい。(生き方)
第一の方法としては、幼稚だからと昔話を拒絶せずに、その中から人生の教訓を見出す積極的な読み方をすることだ。昔話は確かに非日常的な世界を舞台に描かれているため、一見、取っ付きにくい印象もある。実際読んでみると、話の展開は予期していた通り順調に流れ、最後にひょっと不意をつかれる。昔話が幼稚だと言われる由縁は、そこから来ているのかもしれない。現代文学のような、複雑なひねりはなく、素直に教訓を示している。幼稚園の頃、繰り返し読んだ「かさじぞう」の話は、十年近く経った今でも鮮明に思い出せる。おそらくそれは、「かさじぞう」の教訓が、私の基盤の欠片となりえているからだろう。このように、昔話には単純だからこそ、示すことのできる、人生の教訓のようなものが凝縮されている。考えてみれば、道理も人間性も、人間なら単純に理解できるようなものである。しかし、私たちはそんな単純さに遠回りして気づくのだ。一度、昔話の中で、単純な教訓を経験しておくことで、人間らしく生きることができるだろう。(複数の方法Ⅰ)
第二の方法としては、昔話を生き方に直接、反映させ、受け継いでいくことだ。『古代への情熱』の著書シュリーマンは、子供のころに絵本で読んだトロイ戦争を信じ、独力でトロイの都を発掘した。昔話には時を越えた説得力があるように、私は感じる。昔話には、何百年、何千年前に生きた人々の人生から得た知恵が記されているのだ。それは、昔話に限ったことではない。ことわざや短歌など、日本に伝統的に根付いている文化にも同じことがいえる。しかし、そこで面白いのが、ことわざには両極端のものが存在するということだ。例えば、「三度目の正直」と「二度あることは三度ある」という二つのことわざだ。これらのことわざは、ただ単に、キレイ言だけでは終わらせずに、生きる上での矛盾や物事のつながりを、正直に示唆しているように思える。だからこそ、昔話やことわざには、生きる上で、身近な事柄として受け入れることができるのだ。(複数の方法Ⅱ)(伝記)
確かに、現代の最新の技術や思想を吸収することも大切だ。しかし、私たちの生命の根本に、昔話や昔の思想が息づいていることを忘れてはいけない。悪書を読まないことは、良書を読むための最初の条件である。まず、私たちは、積極的に文化と関わる機会を設け、昔の思想から、生きる基盤を学ぶべきである。私は、最先端のものだけに囚われずに、しっかりと頑丈な基盤を重んじて生きていきたい。(反対意見)(名言)(生き方)
講評 nara
 『かさじぞう』か。この感想文でどういう昔話を引用するか、それもまた筆者の個性ということになりそうだね。小学生時代に、幼いれもんさんたちの頭を悩ませ続けた先生は、忘れられない存在だろうな。悩む(頭を使う)ことが大切なのだと教えてくれたのだろうね。
『かさじぞう』か。この感想文でどういう昔話を引用するか、それもまた筆者の個性ということになりそうだね。小学生時代に、幼いれもんさんたちの頭を悩ませ続けた先生は、忘れられない存在だろうな。悩む(頭を使う)ことが大切なのだと教えてくれたのだろうね。
 第一方法:非日常的だから、本質が見えやすいというのは、日常的な題材を扱ったものと比較するとわかりやすい。例えば、テレビドラマや小説なども身近な題材であればあるほど、自らと照らし合わせて「ありえない」「作りすぎ」と本質とは離れたところに目が行きやすい。舞台設定や題材が非日常だからこそ、細部にとらわれず核となるところをすくい上げやすいのだろうね。
第一方法:非日常的だから、本質が見えやすいというのは、日常的な題材を扱ったものと比較するとわかりやすい。例えば、テレビドラマや小説なども身近な題材であればあるほど、自らと照らし合わせて「ありえない」「作りすぎ」と本質とは離れたところに目が行きやすい。舞台設定や題材が非日常だからこそ、細部にとらわれず核となるところをすくい上げやすいのだろうね。
 第二方法:矛盾は人間の人間たりうる面なのかな。全く正反対の意味のことわざが存在していることもあれば、一つのことわざが反対の意味でとらえられることもある。しかし、それぞれが人間の本質を語っているからこそ、時代や社会を越えて引き継がれているということだね。生き方に直接反映させるというのは、具体的にはどうすることだろう。れもんさんは、今、どんな昔話をどのように直接反映させているのかな。
第二方法:矛盾は人間の人間たりうる面なのかな。全く正反対の意味のことわざが存在していることもあれば、一つのことわざが反対の意味でとらえられることもある。しかし、それぞれが人間の本質を語っているからこそ、時代や社会を越えて引き継がれているということだね。生き方に直接反映させるというのは、具体的にはどうすることだろう。れもんさんは、今、どんな昔話をどのように直接反映させているのかな。
 前に、「古典とは」という長文があったよ。古典とは常に新しいものだと、その長文では定義されていた。これを踏まえれば、最新の技術や思想というのは、「今」新しいものだと言えそう。昔話が引き継がれるのも古典と同じ考え方だろうし、最新のものの中には、「今だけ」のものもあれば「常に」の可能性を秘めているものもありそうだね。
前に、「古典とは」という長文があったよ。古典とは常に新しいものだと、その長文では定義されていた。これを踏まえれば、最新の技術や思想というのは、「今」新しいものだと言えそう。昔話が引き継がれるのも古典と同じ考え方だろうし、最新のものの中には、「今だけ」のものもあれば「常に」の可能性を秘めているものもありそうだね。
 『かさじぞう』か。この感想文でどういう昔話を引用するか、それもまた筆者の個性ということになりそうだね。小学生時代に、幼いれもんさんたちの頭を悩ませ続けた先生は、忘れられない存在だろうな。悩む(頭を使う)ことが大切なのだと教えてくれたのだろうね。
『かさじぞう』か。この感想文でどういう昔話を引用するか、それもまた筆者の個性ということになりそうだね。小学生時代に、幼いれもんさんたちの頭を悩ませ続けた先生は、忘れられない存在だろうな。悩む(頭を使う)ことが大切なのだと教えてくれたのだろうね。 第一方法:非日常的だから、本質が見えやすいというのは、日常的な題材を扱ったものと比較するとわかりやすい。例えば、テレビドラマや小説なども身近な題材であればあるほど、自らと照らし合わせて「ありえない」「作りすぎ」と本質とは離れたところに目が行きやすい。舞台設定や題材が非日常だからこそ、細部にとらわれず核となるところをすくい上げやすいのだろうね。
第一方法:非日常的だから、本質が見えやすいというのは、日常的な題材を扱ったものと比較するとわかりやすい。例えば、テレビドラマや小説なども身近な題材であればあるほど、自らと照らし合わせて「ありえない」「作りすぎ」と本質とは離れたところに目が行きやすい。舞台設定や題材が非日常だからこそ、細部にとらわれず核となるところをすくい上げやすいのだろうね。 第二方法:矛盾は人間の人間たりうる面なのかな。全く正反対の意味のことわざが存在していることもあれば、一つのことわざが反対の意味でとらえられることもある。しかし、それぞれが人間の本質を語っているからこそ、時代や社会を越えて引き継がれているということだね。生き方に直接反映させるというのは、具体的にはどうすることだろう。れもんさんは、今、どんな昔話をどのように直接反映させているのかな。
第二方法:矛盾は人間の人間たりうる面なのかな。全く正反対の意味のことわざが存在していることもあれば、一つのことわざが反対の意味でとらえられることもある。しかし、それぞれが人間の本質を語っているからこそ、時代や社会を越えて引き継がれているということだね。生き方に直接反映させるというのは、具体的にはどうすることだろう。れもんさんは、今、どんな昔話をどのように直接反映させているのかな。 前に、「古典とは」という長文があったよ。古典とは常に新しいものだと、その長文では定義されていた。これを踏まえれば、最新の技術や思想というのは、「今」新しいものだと言えそう。昔話が引き継がれるのも古典と同じ考え方だろうし、最新のものの中には、「今だけ」のものもあれば「常に」の可能性を秘めているものもありそうだね。
前に、「古典とは」という長文があったよ。古典とは常に新しいものだと、その長文では定義されていた。これを踏まえれば、最新の技術や思想というのは、「今」新しいものだと言えそう。昔話が引き継がれるのも古典と同じ考え方だろうし、最新のものの中には、「今だけ」のものもあれば「常に」の可能性を秘めているものもありそうだね。
毎月の学年別「森リン大賞」作品集森リンの丘
自動採点ソフト「森リン」で上位になった作文を掲載しています。
しかし、子供たちの実力はそれぞれ個性的です。上手に書けている子の作文を見せて、自分の子供の作文と比較しないようにお願いします。
|
作文教室受講案内
無料体験学習
作文講師資格 |
| ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |
| お電話によるお問合せは、0120-22-3987(平日9:00-19:30) |
