昨日2610 今日435 合計25258□
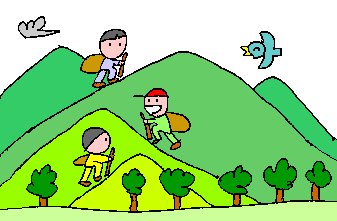 作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
作文教室の丘から 小学生、中学生、高校生の作文 (編集)
小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1・2・3年生 高校1・2・3年生
心の栽培日記 ノンキィ
人類の文明は、いつの時代も誰かが誰かの模倣をすることで発展してきた。私の住む町京都は、千年の都として栄えただけに様々な伝統工芸が発達している。それらの価値は、師から弟子へと絶えることなく受け継がれ、真似をされてきたからこそのものだと思う。何かを真似ることは負の印象を伴いがちである。けれど私は、真似事から始まる心の庭造りを、積極的に進めていきたい。
今日の世界では、人よりも独創的かつ斬新な発想を生み出すものが成功するという考えが広く社会に浸透している。このような新たな革新をもてはやす風潮が、“真似”という行為に二流のレッテルを貼ってしまった。けれど、二十世紀中頃から急速に進歩するこれらの科学技術も、決してゼロからスタートしたわけではない。初めて火を使用してから、人類はより精巧な石器を求め、生活の改善を図ってきた。風車や蒸気機関、蓄音機。それらは全て、後の世代の人々が元来のものを模倣し、その上に改良を重ねたものではなかったか。庭に花の種を植えるとき、その種子をも創造することが出来るだろうか。真似事は何の恥でもないことを、私達は認めるべきである。
一方で真似事は、人が何かを得るときの基礎を固める目的以外には何の力も発揮しない。オランダの画家ゴッホは、東洋の浮世絵に高い関心を示し、それを題材とした絵画を何点も残した。彼の作品は、絵の枠組みという点ではほとんど模写である。ただ、決定的な相違点はその色使いにあるのだ。ゴッホは日本の版画に魅力を感じ、それを自分色に染めて新たな世界を作り出した。どちらがより良いというでもなく、広重の繊細な色使いもゴッホの情熱的で大胆なそれも、それぞれの輝きを放っている。真似をして、それで終わりではない。その先に続く道をも背負う覚悟がなければ、せっかくの芽は、伸びることもなく枯れてしまう。
ただし、私達の幸福が、他の人々の不幸に支えられているのであってはならないように、最低限度守らねばならない約束が社会にたくさん存在する。知的所有権を保障することは、人間の基本的人権の尊重にもつながる。だが、そもそもそのような規則は真似事を簡単だと思い込む人の軽率な行動を規制させるためのものだろう。他人の庭の花を勝手にもぎ取っていく非常識な人が大勢存在するからなのだろう。人類の文明にはいつでも模倣の影が伴っていた。これからを生きる私も、正しい模倣をパートナーに迎え、大輪の花を咲かすまで歩み続けて行きたい。
人類の文明は、いつの時代も誰かが誰かの模倣をすることで発展してきた。私の住む町京都は、千年の都として栄えただけに様々な伝統工芸が発達している。それらの価値は、師から弟子へと絶えることなく受け継がれ、真似をされてきたからこそのものだと思う。何かを真似ることは負の印象を伴いがちである。けれど私は、真似事から始まる心の庭造りを、積極的に進めていきたい。
今日の世界では、人よりも独創的かつ斬新な発想を生み出すものが成功するという考えが広く社会に浸透している。このような新たな革新をもてはやす風潮が、“真似”という行為に二流のレッテルを貼ってしまった。けれど、二十世紀中頃から急速に進歩するこれらの科学技術も、決してゼロからスタートしたわけではない。初めて火を使用してから、人類はより精巧な石器を求め、生活の改善を図ってきた。風車や蒸気機関、蓄音機。それらは全て、後の世代の人々が元来のものを模倣し、その上に改良を重ねたものではなかったか。庭に花の種を植えるとき、その種子をも創造することが出来るだろうか。真似事は何の恥でもないことを、私達は認めるべきである。
一方で真似事は、人が何かを得るときの基礎を固める目的以外には何の力も発揮しない。オランダの画家ゴッホは、東洋の浮世絵に高い関心を示し、それを題材とした絵画を何点も残した。彼の作品は、絵の枠組みという点ではほとんど模写である。ただ、決定的な相違点はその色使いにあるのだ。ゴッホは日本の版画に魅力を感じ、それを自分色に染めて新たな世界を作り出した。どちらがより良いというでもなく、広重の繊細な色使いもゴッホの情熱的で大胆なそれも、それぞれの輝きを放っている。真似をして、それで終わりではない。その先に続く道をも背負う覚悟がなければ、せっかくの芽は、伸びることもなく枯れてしまう。
ただし、私達の幸福が、他の人々の不幸に支えられているのであってはならないように、最低限度守らねばならない約束が社会にたくさん存在する。知的所有権を保障することは、人間の基本的人権の尊重にもつながる。だが、そもそもそのような規則は真似事を簡単だと思い込む人の軽率な行動を規制させるためのものだろう。他人の庭の花を勝手にもぎ取っていく非常識な人が大勢存在するからなのだろう。人類の文明にはいつでも模倣の影が伴っていた。これからを生きる私も、正しい模倣をパートナーに迎え、大輪の花を咲かすまで歩み続けて行きたい。
講評 nara
 大きな学校行事も終了し、この1年、そして中学校生活を振り返るのに、いい時期だね。ここ1ヶ月ほどは変則的な進め方をしていたけれど、年末の休みを使って、元のペースに戻していこう。
大きな学校行事も終了し、この1年、そして中学校生活を振り返るのに、いい時期だね。ここ1ヶ月ほどは変則的な進め方をしていたけれど、年末の休みを使って、元のペースに戻していこう。
 大きな学校行事も終了し、この1年、そして中学校生活を振り返るのに、いい時期だね。ここ1ヶ月ほどは変則的な進め方をしていたけれど、年末の休みを使って、元のペースに戻していこう。
大きな学校行事も終了し、この1年、そして中学校生活を振り返るのに、いい時期だね。ここ1ヶ月ほどは変則的な進め方をしていたけれど、年末の休みを使って、元のペースに戻していこう。
毎月の学年別「森リン大賞」作品集森リンの丘
自動採点ソフト「森リン」で上位になった作文を掲載しています。
しかし、子供たちの実力はそれぞれ個性的です。上手に書けている子の作文を見せて、自分の子供の作文と比較しないようにお願いします。
|
作文教室受講案内
無料体験学習
作文講師資格 |
| ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |
| お電話によるお問合せは、0120-22-3987(平日9:00-19:30) |
