
ここからは、想像の話になります。
経済破綻があっても、自然災害があっても、生き残るだけならだれでも何とかできます。しかし、生き残るだけでは済まないのが、子供を持つ母親です。子供の成長のためには、一刻も早く元の安定した社会に戻す必要があるからです。
だから、地域の自治の中心になるのは、小さい子供を持つ母親です。しかし、母親は組織の運営のようなことには慣れていません。地域を単位とするような自治的な運動を運営するには荷が重いのです。
現在、既にある地域の自治会は、組織はそのまま生かせますが、日常的な活動以上のことをするには力不足のように思います。町内会のお祭りのようにある程度役割分担が決まっている仕事をするならいいのですが、前例のない新しいことをさまざまな意見を押し切って遂行することは難しいと思います。
地域の自治のリーダーとして新しい活動を切り開くことができるのは、その地域に住民として暮らしている中小企業の社長のような人です。それも、できれば創業者で、裸一貫からたたきあげて、多くの従業員を抱えるようになった人がいいでしょう。危機のときには、危機をのりこえてきた人がリーダーになる方がいいのです。しかし、そういう人ほど自分から進んで「自分がやる」とは言い出しません。リーダーになる素質のある人は、「リーダーなどだれでもできる」と思っていることが多いからです。だから、周りの人がそういう人物を見つける必要があります。
子供を持つ母親と中小企業の社長のような人物を中心に作られた地域自治の核に、行動力のある若者としてfacebookやgoogle+を活用できる高校生や大学生が参加すれば、国の政治や経済が破綻しても、地域の生活はすぐに復活するでしょう。治安も、防災も、環境も、福祉も、そして日常生活に必要な衣食住の保障も、また、教育も、文化も、地域の自治が動き出せば、公の行政サービスなど何もなくてもやっていけるのです。
そして、いったんこのような自治社会が生まれれば、その後国家の役割が再び必要になるとしても、それはもはやかつてのような利権にまみれたよそよそしい国家ではなく、真に国民の利益を考えた、静かだが頼りになる、国民と不可分の国家になっているだろうと思います。
------------------------------------------------------------
言葉の森では、今後、次のような教育プロジェクトを計画しています。
それは、自然災害や経済破綻が起きても大丈夫なように、ネットを活用した低価格の(場合によっては無料の)家庭学習をサポートする教育運動です。
通信教育の講座を受講している人は、感じがわかると思いますが、通信講座では毎月定期的に教材が送られてきます。このプロジェクトでは、毎月の教材のかわりに、インターネットで無料で教材をダウンロードできるようにしておきます。
そして、その教材を家庭でどう使いこなしていくかという家庭学習の方法をfacebookのグループの中で提供し共有してていきます。
自分の子供を教えることが中心ですが、教えることが上手な人は、近所の子供も教えられるようにします。すると、そこが小さな寺子屋のような場所になります。
寺子屋だから、勉強と躾の全体を見ていけるようなものにする必要があります。読解と作文については、言葉の森に既に教材とノウハウがあります。漢字の勉強、数学の勉強、英語の勉強なども、教材を準備すればすぐに指導することができるようになると思います。。
更に、子供には勉強だけでなく日常生活の躾のようなことも教えていく必要があります。それは、家庭での手伝いの中で身につけていくものになるでしょう。また、もうひとつ大事なのが季節ごとの行事です。行事と手伝いによって、子供は社会生活の知恵も身につけていくようになると思います。
今後、主にfacebookの中で、このような家庭教室、地域教室をサポートする教育プロジェクトを展開していく予定です。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookやgoogle+を作文の勉強に生かすという話の最終回です。
最初は作文の話から始まりましたが、それが教育全体の話になり、教育以外の生活の話にまで広がりました。そして、今回は自治の話です。いわば、日本の新しい国づくりの話と言ってもいいと思います。
なぜ、そういうところまで話を進めるかというと、今、日本を含め世界全体が政治的にも経済的にも危機の一歩手前にあるように思われるからです。
これは、たまたまやり方が悪かったからうまく行かなかったのではありません。欧米の文化から始まった近代の世界自体が行き詰まっていることの反映なのです。
この行き詰まりを打開することのできる文化を持っている国は日本です。日本は、欧米とは全く異なる文化圏で、江戸時代の300年間、豊かで平和で高度に発展した社会を作ってきました。江戸時代の日本の社会は、欧米よりもさまざまな面で優れた特徴を持っていました。
ただし、欧米の文化から離れていたために生じた弱点もありました。一つは、民主主義が不徹底だったこと、もう一つは、近代科学が未成熟だったことです。しかし、社会の底流では民主的な運営が行われていましたし、生活の中には科学的なものの考え方が広がっていましたから、いったん欧米の文化に遭遇すると、急速にそれらの政治制度や科学技術を自分たちの文化に移植することができたのです。
明治以降の日本の歴史は、欧米に追いつくための歴史でした。しかし、政治的にも経済的にも、欧米に追いついたころ、日本が直面したのは、欧米文化の限界でした。
今日、限界はさまざまなところで現れています。当面の第一の問題は、世界のほとんどの国で経済が行き詰まりを見せていることです。アメリカの経済には、もう自立して回復する力はないようです。今は、裏付けのないドルを印刷してお金を回していますが、借金を増やして時間かせぎをしているだけのように見えます。ヨーロッパも、ギリシアのあとに予想されるイタリアやスペインの破綻を救う余力はもはやないようです。日本もまた、毎年、展望もなく税収をはるかに上回る支出を続けています。
どこかの国が、「もうこれまでの借金は返せない」と言い出せば、そこから世界中のすべてのお金の動きが停止する可能性があります。
しかし、そこで破綻するのは、際限のない軍事費など無駄な支出を重ねてきた国家であって、個人としての国民ではありません。ほとんどの個人は、収入の範囲で支出をするという健全な生活を営んでいたのです。
だから、国の経済が破綻しても、個人が地域の中で協力する仕組みさえ作ることができれば、かえって国家が余計なことをしない分、ずっと暮らしやすい社会ができます。
そして、その社会は、暮らしやすいだけでなく、これまでなかったほど文化が豊かに花開く社会になるのです。
なぜでしょうか。これまでのグローバルな分業化された個人がばらばらに消費者であるような社会では、消費者のニーズは観念的に考えられた架空のものでした。自治的に運営される社会では、ニーズは、個人個人の真の要望に根差したものになるからです。
例えば、食品会社は、現在、最も安く仕入れることができる生産地から大量の原料を集め、輸送費をかけて運び、保存料で長持ちするようにし、着色料で見た目をよくし、広告宣伝費をかけて消費者に売り、売れ残ったものは廃棄します。(そうでないところももちろんありますが)
このとき、消費者のニーズは、安くて見た目がよくて長持ちするものをセンスのいいコマーシャルにつられて買うところにあると思われています。この架空のニーズに基づいて生じる、輸送費、着色料や保存料の費用、広告宣伝費、廃棄にかかる費用などすべてがGDPを押し上げています。
しかし、ここで豊かになったものは、お金に換算された売上や利益だけであって、見方を変えれば多くの人は逆に貧しくなっているのです。着色料や保存料の会社で働く人は、本当はそんなことのために働きたくはないはずです。広告宣伝会社で働く人も同様です。みんな、本当は相手が喜ぶことをして働きたいのに、分業化された社会の中では、往々にしてその反対のことをしなければお金が回ってこない仕組みになっているのです。
ところが、自治的な社会で、相手の本当のニーズがわかる中で仕事をするようになれば、だれもが相手が喜ぶようなことを自分の仕事の中心にするはずです。しかし、衣食住の直接的なニーズは、今の人類の生産力からすればすぐに埋められますから、多くの人は文化的に相手を喜ばす仕事に向かうでしょう。こうして、江戸時代がそうであったように、さまざまな文化が花開く豊かな社会になるのです。
世界の経済が破綻することは、これまでの無駄の多い社会の無駄の部分に乗っていた人にとっては大きな脅威になります。しかし、地道に働いていた人にとっては、地域で助け合う仕組みができれば、国の経済破綻は何の脅威でもありません。むしろ、新しい社会に移行するちょうどいいきっかけになるぐらいです。
しかし、そのためには、地域の自治の受け皿ができている必要があります。だから、日本の社会にとって今いちばん大事なことは、江戸時代のような地域自治の文化を作り出すことなのです。
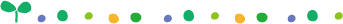
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookやgoogle+を作文の勉強に生かすという話の続きです。
ソーシャルサービスは、家庭における予習と自習、地域における発表、有志による教材作成などに生かせるという話を書いてきました。
そして、作文の勉強でできることであれば、ほかの勉強ではもっと簡単にできます。なぜなら、英語、数学、理科、社会などの勉強の多くは、知識を整理したり解法を身につけたりすることが中心になる勉強で、読解や作文の勉強ほど教えることが難しくはないからです。
ここまで来ると、教育全体を自分たちの手で作り運営するという話になってきます。
そして、これが江戸時代の寺子屋教育で行われてきたことなのです。
江戸時代は、公教育としての学校制度はありませんでした。庶民は、自分の家業を子供に継ぐために、教育を必要としました。武士階級は、やはり武士階級としての仕事を子供に継ぐために教育を必要としました。
その教育の多くは、読み、書き、算盤、そして倫理や道徳としての四書五経の習得でした。江戸時代の識字率が高かったのは、農工商に従事する庶民でさえ、家業に従事するために文字を読み手紙を書く必要があったからです。
したがって、そこで行われた教育も決して一律のものではありませんでした。一般教養として共通のものはありましたが、それぞれの仕事に特有な知識を読み書きの学習の中で学んでいったのです。
同様のことが、これからの社会でも行われるようになります。保護者は、子供たちに将来本当に役に立つことを学んでほしいと思っています。試験のための一夜漬けの知識を身につけてくれればいいと考えている親はいません。
しかし、今の教育体制の中では、子供にとって本当に必要なことは後回しになっています。子供たちに学ぶ意欲を持たせる方法は、競争を強化することではなく、学ぶ意味がわかるような教育を行っていくことです。
そういう当然のことができなかったのは、これまでの教育が行政のサービス、又は民間のサービスとして行われてきたからです。それは、明治時代から導入された学校制度が、欧米に追いつくための国家目標として取り組まれてきたためです。
もちろん、高度に専門化されたサービスが必要な教育の分野はあります。しかし、小中学校の義務教育では、教育は外部に委託するサービスとしてではなく、自治的な活動として行っていく方がずっと能率よく充実したものになるのです。
同様のことは、教育以外の分野にもあてはまります。治安、環境、防災、介護、福祉など、現在行政のサービスとして行われているもののほとんどは、江戸時代には庶民の自治活動として行われていました。巨大な江戸という都市の治安を守ったのは、警察のような行政機関ではなかったのです。(つづく)
話が、教育から社会の問題へと発展してきました。次回は、いよいよ最終回。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookやgoogle+を作文の勉強に生かす話の続きです。
前回までは、予習と自習と発表について書いてきました。
今回は、教材作成に生かすという話です。
感想文を書く際のもとになる文章を読ませる場合、親なら、子供にこういう文章をよんでもらいというというものもあると思います。
教材作成の専門家に任せるよりも、子供の成長を身近に見ている親の方が正しい判断ができるということも多いはずです。
そこで、親や先生やあるいは一般の人が、自分たちで子供向けの長文を作るというのが「オープン長文」という企画です。
教材作成を専門にしている人は、その教材がどのように使われたかを直接見ることはありません。しかし、親や先生であれば、子供がそれをどう消化したかを知ることができます。特に、感想文の課題の長文であれば、どのように理解して、どのような文章を書いたかということがわかります。それを、教材の改良にすぐに生かせるのが、自分たちで教材を作ることの利点です。
著名な人の書いた文章であれば、著作権の問題もあり、教材として気軽に使うことができませんが、自分たちで作った文章であれば、互いの了解のもとにすぐに改良をしていくことができます。
これは、国語の文章に限らず、他の教科にもあてはまります。
例えば、数学の問題です。今の学校や塾の勉強は、点数の差のつきやすい問題、つまりうっかり間違えやすい問題を中心に評価が行われがちです。みんなが百パーセントできるようになることを目的とした勉強ではなく、点数で差をつけることを目的とした勉強になっている面があります。
このことが、算数や数学を苦手と感じる子を増やしています。よくできる子に知的な刺激を与えるために難問を出すのはいいのですが、教える仕事だけを専門にしていると、難問を出して差をつけることがひとつの目標のようになってしまうことがあるのです。
しかし、親は違います。自分の子供が実力をつけることが目的ですから、教材の適不適が教材作成の専門家よりもはっきりとわかります。もし、親が教材作成に参加したり、注文をつけたりすることができるようになれば、子供たちの勉強の結果をすぐに次の教材作りに生かすことができます。
このようなことができるのが、やはりfacebookやgoogle+を利用したコミュニケーションの力です。例えば、
「この間の問題、どうだった」「うちには、ちょっと難しかった」「じゃあ、どこを改善しようか」「こっちはちょっと易しすぎたようだから、発展問題があるといいかなあ」「それも、作ろう」
と、このようなやりとりができるようになります。
このような形で、親が直接教材作成に意見を反映させられるようになれば、現在の中央集権型の時代後れになりがちな教育は、もっと子供たちの現実に結びついたものに変わっていくはずです。
全国の小中学校には、もうかなり以前から1クラス分の生徒が全員使えるだけのパソコンが整備されていますが、取り組みの遅れている学校がかなりあります。
また、本当は、中学校の技術家庭で、コンピュータ・プログラミングを教えることができれば、日本人のIT技術はもっと広がっているはずです。
こういうことも、子供の成長を身近に見ている親が教材作成に参加するようになれば、大きく改善されると思います。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookやgoogle+を作文の勉強に生かす話の続きです。
前回までは、予習と自習について書いてきました。
今回は、発表についてです。作文の勉強の結果を発表する際にも、facebookやgoogle+を活用することができます。
facebookやgoogle+で予習の話を交わしているうちに、同じ学年の子供の保護者の中に、互いに親しみがわいてきます。毎週、同じような課題を、同じように工夫しながら予習するので、お互いに相手の苦労もわかるようになるのです。
そこで、そういう共通の基盤を前提にして、子供たちの清書の発表会をします。
昔、江戸時代の寺子屋でも、年に何回か席書き(せきがき)という発表会のようなものがありました。通り道にゴザをしいて、普段練習している手習いの成果を発表し、それらを展示しておくのです。通行人は思い思いに子供たちの発表を見に来ます。子供にとって、普段の学習の成果をみんなの前で発表するというのは晴れがましいものです。このようにして、練習と発表のサイクルの中で、勉強の意欲を高めていったのです。
作文の場合も同じようにできますが、江戸時代の席書きが主に習字であったのに対して、作文の場合は600-1200字の文章です。清書をそのままfacebookやgoogle+にアップロードしたのでは、あまり面白くありません。
そこで、発表会は、文章だけでなく、その作文の内容に関連した音楽や画像や朗読なども入れるようにします。作文というよりも、文章を中心とした総合表現芸術というようなものです。その発表会の作品を見て、ほかの生徒や保護者が思い思いにコメントを入れることもできます。
発表会で大事なことは、子供たちの作品を比較しないということです。評価をするにしても、それぞれの個性を評価することが中心で、優劣をつけるような評価は限定的なものにとどめておく必要があります。
facebookやgoogle+を利用するので、ネットワークの上だけでも発表会を行うことができますが、本当は、発表はリアルな関係の中でした方が励みになります。
そのために、予習が学年別・課題別であったのに対して、発表はできるだけ地域別に行うようにします。予習は、全国の小学3年生の8月1週の課題などと時間的に限定したものでしたが、発表は、○○市の□□町周辺の生徒というようにしていきます。したがって、地域ごとにいろいろな年齢の子供が参加する形になります。
このように、子供の教育を要にして地域につながりができるというのが、子供たちの成長にもプラスになります。今は核家族化が進んでいるために、子供たちは、親子という限られた人間関係の中で過ごすことが多くなっています。また、学校や塾も、同学年の子を中心に組織されているので、ここでも人間関係は単調なものになりがちです。
子供は、地域の中で、近所のおじさんやおばさんに囲まれて、年下の子や年上の子との関わりの中でバランスよく成長していくものですが、現代の社会ではその機会はきわめてすくなくなっています。そこで、作文の勉強という学ぶ機会を利用して、地域の多様な人間関係の中で育つ環境を作っていくのです。
日本の教育は、現在多くの点で行き詰まっているように多くの人が感じています。
しかし、それは教育に限ったことではありません。教育も、政治も、経済も、文化も、あらゆる面で、日本が明治以降、取り入れたきた欧米の近代文明が制度疲労を起こしているのです。
日本の社会は、もう既に、近代西欧文明の長所も弱点もほとんど経験しました。あとは、これを日本が本来持っていた伝統の中で昇華していくことです。
その伝統の多くは、これまで遅れていた時代と見なされていた江戸時代の中にあります。単なる復古ではない、伝統と進歩の創造的な結合を作り出すことがこれからの課題です。
それは、比喩的に言えば、民主主義の実現した江戸時代、又は近代科学を取り入れた縄文時代というようなものになると思います。(つづく)
次回は、教材の作成についてです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookやgoogle+を作文の勉強の予習に生かす方法の続きです。
前回は、小学3、4年生が感想文を書くための自習として音読の説明をしました。
音読で読解力がつくというのは、何度も繰り返し音読することよって、文章の内容が自分のものとして把握されるようになるからです。
では、なぜ音読であって黙読でないかというと、黙読のような声に出さない勉強は反復することがきわめて難しくなるからです。
音読には脳を活性化する働きがあるという人もいますが、それはただ脳波の動きが大きくなっているというだけで、それだけでは音読に効果があるということはできません。
音読のいちばんの効果は、反復と継続ができるということです。だから、逆に言うと、読書のように新しい文章を次々と読むような場合、音読はあまりいい読み方とは言えません。それよりも黙読の方がずっと能率が上がります。音読は、繰り返し読むようなもののときに役立つのです。
さて、感想文のもとになる長文を子供が毎日音読し、それを授業の前にお父さんやお母さんに説明したとします。それから、家庭での対話が始まります。
親が、その長文の内容と似た話をしてあげると、子供の理解は更に深まります。そして、親の話してくれた似た話に触発されて、子供自身も似た話を思いつくようになります。
感想文を書く際に大事なことは、いかにもとの文章を自分にひきつけて読むかということですから、似た話を通して読む読み方は、感想文に最も生かせる読み方になります。
ところが、小学校3、4年生にとって感想文が難しいのは、まだ人生の経験が少ないために、文章を読んで内容は理解できたとしても、それを自分の身近な話に結びつけるだけのぴったりした似た話が子供の中にないからです。そのときに、身近にいる親が似た話を聞かせてあげると、子供の似た話の見つけ方が柔軟になります。
小さい子供は、理屈で説明してもなかなか理解できませんが、実例を示してあげるとすぐに同じような実例を思い出すことができます。
小学3、4年生では、感想文は上手に書けないのが普通です。しかし、このように書くための材料がそろえば、普通の作文と同じぐらいの字数はすぐに書けるようになります。
このお父さんやお母さんの似た話を聞かせてあげるときに使えるのが、やはりfacebookやgoogle+です。作文の準備の出来事をシェアしたように、感想文の場合は似た話をシェアできます。大人でも、真面目に考えすぎるために似た話がなかなか出てこない人がいます。そういう人も、ほかの人の似た話を聞けば、「そういうことなら、自分でもある」と思いつくのです。
さて、小学校低中学年までは、親子の対話は簡単にいつでもできましたが、子供が小学校高学年になると、だんだん対話の機会が少なくなってきます。
子供の関心は、家庭から学校へ、親から友達へと移っていきます。また、勉強も難しくなるので、親が気軽にアドバイスできないものも出てきます。
そして、特に父親は、子供との接点が、時間の面でも話の内容の面でも少なくなるので、たまに話をする余裕ができたときも、話題が出てこないことがあります。
すると、「どうだ。勉強むずかしいか」「まあまあね」「そうか」……というような展開で終わってしまうことも増えてくるのです。
本当は、こういう時期こそ、親子で知的な対話をすることが大事なのですが、親子に共通の話題がなく、勉強や成績の話だけになってくると、次第に子供も親と話すことを敬遠するようになってきます。
そのときに生きてくるのが、感想文のもとになる長文を読んでの話題です。そのためには、子供が小学校中学年のころから、親子で長文をもとにして話をする機会を作っておく必要があります。
小学校中学年までの間に、音読や長文の説明をする習慣を作っておけば、その延長で、小学校高学年になっても、中学生、高校生になっても同じような話題の共有ができます。中学生や高校生の感想文課題は、かなり難しいものですから、親としても話しがいがあるはずです。
たまに、保護者の方で、「私はそんなに教養がないので、子供と難しい話をすることができない」と最初からあきらめたことを言う人がいます(笑)。勉強は、子供だけがすればいいというのではありません。親であっても、やはり勉強して成長していくのです。そして、親には、子供には決して負けない人生の年輪があります。親が、自分の経験を通して話す意見が、子供にとっては最も心に残ります。そして、そのときにも、facebookやgoogle+を生かすことができるのです。(つづく)
※次回は、作文の発表についてです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookを作文の勉強の予習に生かす方法の続きです。
小学3、4年生は、題名課題で作文を書く練習が中心になります。そして、ときどき感想文課題が入ります。このように課題があらかじめ決まっていると、予習は更に充実したものになります。
例えば、小3の8月1週の作文の課題は「おふろ」です。この課題に合わせて、facebookの「言葉の予習室小3」には次のような記事を入れました。
====引用ここから。====
小3の8.1週の課題は、「●おふろ、ぎりぎりセーフ」これは、どちらかで書くということです。
おふろの話を書く場合、家庭での予習は、おふろで遊ぶことがいいと思います。
私の家でやっていたのは、これ。
1、泡でいっぱいになる入浴剤
2、又は、菖蒲湯のように、香りのする葉っぱを入れる
3、水鉄砲
4、水中メガネ
今、どの家のうちのなかのお風呂に入っていると思いますが、たまにはみんなで近所の銭湯に行ってみるといいかもしれません。
その行き帰りに、お父さんやお母さんが、昔のお風呂の話をしてあげると、似た例も話せて一石二鳥。
ほかにも、お風呂に関していいアイデアがあったら、どなたでもご自由にお書きください。
====引用ここまで。====
お父さんやお母さんによっては、おふろという課題で、自分の子供時代の面白い体験を話せる人も多いはずです。普通、そういう話は、偶然出てくることがあっても、意識的に話す機会がなかなかありません。
ところが、作文の課題が決まっていることによって、あらかじめ子供に聞かせるいい話を準備できます。
小学3、4年生の感想文課題のときは、準備がもう少し難しくなります。題名課題のときは、その題名に合わせて書くことを考えればよかったのですが、感想文課題の場合は、まず課題となる長文(1200-1600字程度)を読んで、その内容を自分なりに把握していなければなりません。
そこで、毎日の音読の自習が大切になってきます。
音読の自習は、朝ご飯の前にやるのが理想です。ゆっくり読んでも3、4分で終わってしまう自習なので、朝食前のように例外なく確保できる時間でないと続けにくいのです。音読や暗唱のような短い時間の毎日の自習は、朝食前に、読書のような時間をかける自習は夕方に、というように使い分けていくといいと思います。
朝ご飯の前、お母さんが支度をしているときに、子供が食卓で大きい声で音読をします。小学生の勉強は、勉強部屋のようなところではなく家族の中でやる方が能率が上がります。お母さんやお父さんは、聞くともなしにその長文を聞いているので、内容が何となく頭に入ります。
そして、感想文の課題の授業がある日の前までに一度、子供が親にその長文の内容を説明するようにします。何度も音読をしている長文は、すっかり頭に入っているので、子供はその長文を見ないでも内容をくわしく説明できます。
小学校中学年の子供が、何も見ずにこのようにすらすらと文章の内容を説明するのを聞いていると、お父さんやお母さんはちょっと感動すると思います。
文章の理解とは、このように内容が丸ごと頭に入り、自由に説明できることです。決して国語の問題を解くような、どこの指示語が何を指しているかというような理解の仕方ではないのです。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)

facebookを作文の勉強の予習に生かす方法です。
作文の勉強で大事なことは、書くことではありません。書く前に、書くための材料を増やしておくことです。材料がないのに表現力だけで書こうとしても長くは書けません。逆に、材料があれば、その材料に引っ張られてだれでも書けるようになります。
では、材料とは何でしょうか。
小学校1、2年生は、自由な題名で書く練習が中心ですから、書くことを決めておくことが材料になります。それは、毎回同じような「今日のこと」や「この前のこと」という題名でもかまいません。大事なことは、先生からの電話指導があるときまでに、何を書くか決めておくということです。
ところが、実際には小学校1、2年生の子で、先生が、「今日は何を書くの」と聞いても、「えーと」とそれから考え出す子がいます。これではいい作文は書けません。この場合の予習は、親が作文の授業がある前までに、「今度の作文は何を書くの」と聞いてあげることです。そして、そこから親子の対話が始まります。
子供が書きたいと思っている題名と、実際に書きやすい題名とは異なる場合があります。例えば、子供はよく、「明日○○するので、そのことを書きたい」と言います。しかし、明日のことは作文にはうまく書けません。作文の中心は、過去の体験です。ですから、親子の話のときに、子供から明日の話が出たら、親が優しく「明日のことは、それが終わってから次の週に書いたらいいんじゃない」と修正してあげるといいのです。
同じように、「テレビを見た」「映画を見た」「ゲームをした」という自分の行動が少ない話も、いい作文にはなりません。作文の材料で大事なことは、その子がどういう行動をしたかということですから、これも、親子の対話の中で優しく軌道修正してあげるといいのです。
そして、更に大事なのは、面白い作文を書くために、親が子供にいろいろなイベントを用意してあげることです。例えば、ひとりでお使いに行かせる、一緒に公園にセミの幼虫を見つけに行く、料理を作る、大掃除をする、旅行に行くなどのイベントです。お金や時間をかけて大げさにやる必要はありません。身近なところに子供が興味を持ついろいろな機会があります。
facebookでは、主にそういうイベントをシェアします。
言葉の森のfacebookに「言葉の森予習室小1」などという学年別のグループがあります。そこで、「我が家では、この前こんなことをしてみた」というような情報を交換します。実は、この、他の家の例というのが、かなり参考になります。
家庭における父親と母親の間でも、二人の興味や関心はかなり違います。父親は、母親の考え付かないような方法で子供を喜ばすことができ、母親もまた父親の考え付かないような方法で子供に接することができます。こういう違いがあるから、子供はバランスよく成長します。この違いは、二人よりも三人、四人と増えた方がもっといいのです。これが、facebookのグループで、イベントをシェアする意義です。
小学校3、4年生は、題名課題で作文を書く練習が中心になります。そして、ときどき感想文課題が入ります。このように課題があらかじめ決まっていると、予習は更に充実したものになります。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) facebook(29)