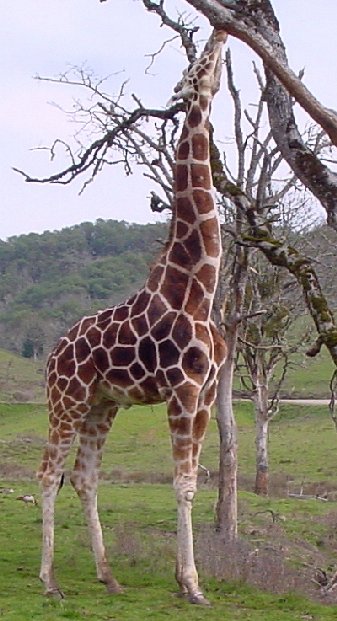
森リンは、作文小論文の自動採点ソフトとして2004年11月26日に特許を出願し取得しました(特許第4584158号)。
それまでの作文小論文の自動採点ソフトは、平均的な文章の平均値からどれだけ離れていないかということを評価の基準としていました。
その結果、うまくない文章はすぐにわかりますが、それがそのまま、うまくない文章の度合いが低いものほどうまい、とは言えないところに問題がありました。ややこしい書き方ですが。(^^ゞ
これは、美人コンテストのようなものを考えるとわかりやすいと思います。
人間の平均的な顔の数値を求めて、その平均値から外れていれば、確かに変な顔だということはわかります。しかし、最も平均値から外れていない顔が最も美しいかというとそうとは言えません。
従来の作文小論文ソフトがどうしてそういう発想で評価の基準を決めたかというと、プログラムを作る人が、うまいということの基準を決めることができなかったからです。
文章のうまさというものには、主観的な面があります。そこで、客観的な、誰もが納得するような基準として平均値を評価の尺度にしたのです
これに対して、森リンは文章のうまさという基準を先に考えました。それは、言葉の森が、これまでの作文指導の中で、上手な文章の蓄積というものを持っていたからです。
言葉の森の考える文章のうまさの基準は、まず第一に語彙が多様であるということです。
第二は、しかし、バランスがとれているということです。
そして、第三は、論説文として理路整然としているということです。
この三つは、それぞれ相反する面があります。
語彙が多様になりすぎると、バランスがとれなくなり、冗長な文章となってしまいます。
また、一般に易しい言葉だけでなく、難しい言葉もある方がいい文章とはいえますが、あまり難しい語彙がありすぎると重い文章になってしまいます。
理路整然としている文章はわかりやすい文章ですが、その度合いが過ぎると硬い文章になってしまいます。
また、森リンの評価は論説的な文章を対象としているので、小学校中学年までの事実中心の生活作文では評価がずれる面があります。更に、字数が短いと、森の点数の誤差が大きくなるので、1200字程度の長さは必要になります。
言葉の森で毎月発表している森リン大賞は、言葉の森の生徒が毎月の清書で書いた作文の中から森リンの上位の人を掲載しています。
ここには人間の評価は何も加えていませんが、上位の作品を見るとかなり妥当性があります。人間が評価して上位の作品を選んでもあまり変わりないと思います。
それなのに、採点にかかる時間は、人間の百倍ぐらい速いのです。
ところで、厳密にいうと森リンで評価しているのは、その作文の上手さというよりも、その作文に表れた、書いた人の作文力の評価です。だから、森リンの点数は、その人の学力と比例している面があります。
森リンの点数を上げるためには、小学生の場合は読書で、中学生や高校生の場合は問題集読書のような難しい読書で使える語彙をふやしていくことが大切です。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

新聞を読む学習法をまだやっていない人が今から新しく始める必要はありませんが、すでに家庭で新聞を読む習慣があるという人は、次のような読み方をしていくといいと思います
新聞というと、ニュースの時事的な記事を読むものだと思いがちですが、このニュースというものはあまり読む必要はありません。なぜなら、ニュースのほとんどは、1週間もたてば意味がなくなるものだからです
また、1ヶ月間や1年間のニュースをまとめた新聞ダイジェストのようなものも読む必要はありません。そういう時事的な知識が直接役に立つというようなことはほとんどないからです。
大きなニュースは、大きな文字のタイトルで書かれているので、つい読んでしまいがちです。また、テレビのニュースも同じように、そのときの最新の話題が大きな話題として放送されているとつい見てしまいがちです。しかし、それらのニュースは、そのときだけのもので、あとに残るものではありません。
新聞やテレビは、与えられたものを惰性で見るのではなく、ポイントを絞って見ることが大事です。
また、新聞の中の特定のコラム欄例えば天声人語や社説などを必ず読むというようなことを自分に課すのもあまりよいことでありません。そういう杓子定規の読み方は時間の無駄になることが多いからです。
では、新聞のどういうところを読むかというと、それは枠で囲まれた解説記事になっているところです。一般紙の場合は、日曜日の朝刊の1面の左上によく解説記事が載っています。そういう記事が、枠で囲まれた解説記事です。新聞の内側にも、そういう囲みの解説記事がいくつもあります。
ニュースは読まないが解説は読むというのが、新聞の最も役に立つ読み方です。
例えば、惑星探査機はやぶさが帰ってきたとか、小惑星イトカワの微粒子が発見されたとかというようなニュースは、興味を引きますが、特に熱心に読む必要はありません。
読むのは、はやぶさがどういう計画で、どういう意義があったのかというような解説の記事です。
この読み方をするためには、新聞は必ずしも毎日読む必要はありません。読んでみたい解説記事があればそれを切り取っておき、あとで時間のあるときにまとめて読むようにすればいいのです。
もし、保護者が、子供の新聞の読み方の手助けをするとすれば、保護者の方で、読んでおくといい解説記事を切り取っておくというやり方をしてもいいと思います。
ところで、こういう新聞の解説記事を1年間分まとめたようなものがあります。それが、毎年の入試問題の国語の説明文の文章です。
読む時間の密度の濃さという点から言えば、新聞の解説記事よりも問題集の問題文の方が読む力がつくと思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。質問と意見(39)

小学生の保護者から、「新聞を毎日読ませているのですが、それは勉強としてどうですか」という質問が何件かありました。
下記は、朝日新聞のサイトからの引用です。
====
新学習指導要領は、思考力などを育てるために従来よりも「言語活動」を重視している。現行の指導要領は児童や生徒の言語活動が「適正に行われるようにすること」と記しているが、新指導要領では、各教科の指導で言語活動を「充実すること」と踏み込んだ。小学5、6年の国語では、新学習指導要領は「読む力」を育てるための指導事項として「本や文章を読んで考えたことを発表し合い、自分の考えを広げたり深めたりすること」などを6点を列挙。具体的な方法の一つに「編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を読むこと」を挙げる。中学2、3年の国語でも指導方法の一つに新聞を例示している。
( 2010-08-08 朝日新聞 朝刊 教育2 )
====
こういう記事があったので、新聞の活用法に関する質問が増えてきたのだと思います。
私の新聞に対する考えは、次のようなものです。
1、新聞には、普通の読書ではあまり触れる機会のない説明的な文章が多いので、その点では役に立つが、子供は実際には漫画を読むだけになることが多い。
2、読む力の基本になるのは読書で、読書を主食とすると、新聞はおやつという位置づけである。
3、新聞の文章は総じてやさしく書かれているので、高学年の生徒が国語の勉強のために読むのであれば、入試問題集を読書がわりに読む方がよい。
4、大学生が、半年ぐらい集中して、新聞の解説記事を中心に隅から隅まで読めば、時事的な一般教養の力はほぼ完璧につく。
5、社会人は、新聞よりも、書籍やインターネットによって情報を得た方がバランスのとれた判断力が身につく。
勉強の基本は平凡です。読書をしっかりしていることが第一で、それ以外のさまざまに目先の変わったやり方は、すべて、半分遊びのようなものです。
新聞を読むことは、決してマイナスにはなりませんし、真面目に読めば、説明文の面白い記事がかなりあります。しかし、それで読書のかわりになると考えたり、国語の勉強にプラスになると考えたりすれば、それはやはり過大評価ではないかと思います。
まず地道に本を読むという時間をしっかり確保していくことが大事で、読書さえしていれば、ほかのことはしてもしなくてもどちらでもいいのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。質問と意見(39)

教室に通っている中学1年生の生徒が、「期末テストで、国語はクラスで1番になりました」と教えてくれました。(小学校2年生のとき、作文が苦手という理由で教室に入ってきた子です。)
この生徒は、毎月の読解問題を解くときでも、自分がAだと思っていたものの答えがBだと、必ず先生に理由を聞いていました。
理由を聞くぐらいなので、答えを選択するときも根拠を持って選んでいます。「ここがこうで、あそこがこうだから、これは違う」という具合の選び方です。
つまり、理屈が通った選択の仕方なのです。決して、
「全体の雰囲気で、こっちがよさそうだ」というような勘で選んでいるのではありません。
国語の成績がよくなる子と、よくならない子の差がここにあります。
雰囲気と勘で選択した子は、答えが×になっていても、「残念。はずれた」で終わりですが、理詰めで考えて選んだ子は、×になったときにその理由を聞いて、次回にそれを生かすことができます。
勉強というものは、答えが○だったらそれは実はやっただけ時間の無駄だったということです。答えが間違えたときに初めて、自分がまだ何かを学ぶ余地があるということがわかるのです。
だから、テストの成績が悪かった場合は、それをむしろ喜ばなければなりません。
さて、国語の問題を理詰めに解くにはコツがあります。それは、問題文を読んでいるときに、これはと思った箇所に線を引きながら読むことです。
印象に残った箇所に傍線を引くと、その文章を二度、三度と繰り返して読むときに、その傍線の箇所を中心にざっと眺めるだけで文章の全体が頭に入ります。
また、
選択式の設問では、どこを根拠として選択したのかがわかるように傍線や「○」や「△」や「?」という記号を設問の横に書いておきます。すると、答案が戻ってきたときに、自分の答えを検証することができます。
読書の場合は付箋、国語問題の場合は傍線というように、自分が読んだ跡を残しながら読むことが大事なのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

国語と算数は、小学校の時代から最も長い時間をかけて勉強をする教科になっています。これは、現代だけの特徴ではなく、江戸時代のころも、読み書きそろばんというものが学習の基本でした。
なぜ、国語と算数がそのように重視され教育の中心になっているかというと、ひとつにはその習得に時間がかかるからです。
それも、難しいから時間がかかるのではなく、学ぶことが多く、しかも平面的に多いのではなく積み重ねる体系として学ぶことが多いために時間がかかるという特徴があるからです。
もうひとつには、人間が社会生活を送る際に、国語と算数が役に立つ重要なツールとなっているからです。
つまり、人間が人間らしい生活を送るのに必要であり、しかも学ぶ努力が必要であり、さらにその学習が個人にとっても社会にとっても役に立つというのが、国語と算数の特徴なのです。
しかし、今の教育は、このような人間と社会の本質から論じられているわけではありません。
国語と算数は、既に教科として成立していることが前提になっていて、受験で学力の差を測るのに適しているために主要教科となっている面もあります。したがって、勉強の中身も、受験の問題を解くために学ばれている面が強いのです。
その結果、国語と算数は、勉強の方向が本来のあり方からずれ、無意味なところで難しい問題を解くことが目的化され、これらの教科の勉強のもともとの意味が忘れられている面があります。
では、国語と算数の本来の勉強の方向とはどういうものなのでしょうか。
国語と算数の勉強という各論を論じる前に、まず人間と教育一般について考えてみる必要があります。
動物は、生まれたときから完成された成長過程を約束されています。ただし、高等な動物になれば親の模倣という教育は必要で、その模倣が不適切であれば成長も偏ったものになります。
人間も、動物的な生活に限って言えば、親の模倣と自然な成長で間に合うはずですが、人間は動物のレベルを超えた社会生活を営む必要があるために、意識的な教育が必要になります。つまり、教育は社会生活を営む人間が、その人間自身とその社会にとって役に立つことを学ぶためにあるといえます。
その教育の分野は、大きく四つに分けて考えることができます。それは、認識における内向きの方向と、外向きの方向、身体における外向きの方向と、内向きの方向の四つです。
第一は、哲学です。これは、認識の創造ということで、世界の物事を新しい見方で構想する力を育てる分野です。
第二は、科学です。これは、世界の認識ということで、身の回りにある多様な現象を理解する力を育てる分野です。
第三は、工学です。これは、世界の加工ということで、現実を変革し加工する技術を身につける分野です。
第四は、心身です。これは、人間の幸福ということで、身体と精神の両面で幸福に生きる技術を身につける分野です。
これらの教育の四つの分野に、現在の教科をあてはめることができます。
哲学の分野には、国語、特に作文が入ります。また、算数の原理的な面もここに含まれます。
科学の分野には、現在の理科・社会など、体系的な知識を身につける教科がすべて含まれます。
工学の分野には、技術・家庭と、美術・音楽など芸術の技能的な面の学習が含まれます。また、国語の技能的な面、外国語などの語学、そして、算数の現実世界に応用する面が含まれます。
心身の分野には、保健・体育・道徳と、芸術における精神的な面の学習が含まれます。
未来の教育の四つの分野は、現代の教科の区分とも対応していますが、それらの教科の位置付けが異なっているので、当然、教科の性格も異なってきます。
哲学の分野に位置づけられる国語の場合は、ある課題について自分の創造的な考えを作り出し表現する力を育てることが学習の中心になります。
工学の分野に位置づけられる算数の場合は、ある課題について算数の知識や技術を現実の世界に応用することが学習の中心になります。
これまでの教育は、社会の有用な歯車となるためのものでした。そして、個人がその社会的役割を果たすことが、その個人の生活の利益とも結びついていました。
これまでの勉強は、社会からの要請が先にある勉強でした。しかし、これからの勉強は、個人が自己の向上のために行う勉強になります。そして、個人が自己の能力を開花させることが、社会に対する貢献にもつながるというものになっていきます。
そのような個人の向上心に基づいた教育においては、勉強は強制で行われるものではなく、また競争で意欲づけされるものでもなく、さらに受験の勝ち負けのために行われるものでもなく、自分自身の向上と社会への貢献のために行われるものになるでしょう。
すると、それら勉強をするための動機は、勝つ喜びではなく、学ぶ喜びに立脚したものになります。
これを四つの教育の分野に当てはめてみると、哲学の分野では創る喜び(創造)、科学の分野では知る喜び(理解)、工学の分野では作る喜び(加工)、心身の分野では感じる喜び(感受)が、それぞれ学ぶ動機となった勉強になります。
こう考えると、哲学としての国語は、材料となる様々な知識や経験を組み合わせて、言語による新しい作品を作り発表するということが勉強の主な方向になるでしょう。
それは、従来の日本の国語のように、文学作品を必要以上に詳しく鑑賞する方向の勉強とは違ったものになります。
一方、工学としての算数は、算数の知識と技術を生かし、それらを組み合わせて現実の課題を解くことが喜びとなるような勉強に進むと思います。それは、物理学や統計学やプログラミングのような方向です。
それは、従来の算数のように、算数の世界の中で難問を解くことが喜びとなるような方向とは違ったものになると思います。
これからの勉強は、勉強することが喜びとなるようなものになる必要があります。試験のためにしぶしぶやる勉強で、その苦痛の代償として褒美があったり、競争という刺激があったりするような勉強は、過去の勉強です。
それは、国語に関して言えば、書くことが楽しいという勉強であり、算数に関して言えば、解くことが楽しいという勉強になると思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

家庭で作文力つけるためには、どうしたらいいでしょうか。
作文力の土台にあるのは、読む力です。それは、読解力というよりも読書力に近いものです。なぜなら、国語の読解問題の成績がいい子が、必ずしも作文が得意なわけではないからです。
しかし、読書が好きで本をよく読んでいる子は、ほぼ例外なく作文も好きです。たとえ、今は作文があまり得意ではなくても、読書好きな子は少しのアドバイスですぐ上手になります。
しかし、もちろん読書だけではカバーできない作文力独自の分野もあります。その一つは、速く書く力と長く書く力です。これはある程度慣れによるものなので、実際に作文を書かないと身につきません。
もう一つ、書かないとわからないものは、誤字と誤表記のチェックです。それは、勘違いして覚えていることが多いので、実際に書いてみないとチェックできないからです。また自分でいいと思っている表現が、読む人にとってはそうでないということもよくあります。
ところが、家で作文を書く練習すると、数回で子供が嫌がるようになります。作文は、負担が大きくしかも成果が見えない勉強だからです。
これが、ドリルなど行う勉強との違いです。漢字ドリルや計算ドリルは、負担がそれほど大きくなく、やりとげたあとがページ数として残ります。作文はやりとげた感覚を持ちにくいのです。
また、親が作文の勉強で成果を出そうとして書き方の注意をすると、次から次へと注意が出てきて、親も子もくたびれる結果になることがよくあります。
更に、上手な子の作文を見せて、こんなふうに書けばいいなどと教えると、子供はかえってやる気をなくします。それは、子供にとっては多くの場合不可能なことだからです。
だから、作文は家庭ではあまり教えないのが基本です。楽しく読書をして読む力をつけていくことが、家庭での勉強の中心になります。
しかし、文章を書くことに何か意味を持たせれば、家庭でも作文の練習を続けることはできます。
その一つは、田舎のおじいちゃんやおばあちゃんに手紙を書く練習です。その手紙の構成は、書き出しがあいさつ、結びもあいさつ、しかし本部の中身は作文という形になります。
しかし、この場合にも大事なことは、子供が作文を書いたあとは極力直さずに褒めるだけにするということです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55)

小学校中学年で作文が苦手だという子のお母さんからから問い合わせがありました。家庭でできる作文の勉強にはどういうものがあるでしょうか、という質問です。
それは、ある意味でとても簡単です。読書と対話の時間を確保していくということだからです。そして、できればその子の書いた文章のいいところをどんどん褒めてあげることです。
普通、小学校低中学年では、作文は苦手になりません。書くことは楽しいことですし、また、この時期は、本を読むことも楽しいことだからです。
作文が苦手だと思っているのは、作文を比較されたことがあるからです。例えば、学校や塾で、「この上手な子のように書きなさい」などと言われたからです(笑)。
作文は、小手先の技術だけですぐうまくなるものではなく、その子のそれまでの読書、対話、経験、そして文章を書く機会の総合化されたものです。特に、読書量の差は大人が考える以上に大きいものです。
日常の会話は、どの子も同じような語彙を使って話していますが、抽象的な話題になると使える語彙の幅はかなり違ってきます。
小学校低中学年で作文が上手だと思われている子は、ひとことで言えば語彙の豊富な子です。語彙が少なければ、どんなによい経験をしてもそれをうまく表現することはできません。
ところが、語彙力は、漢字の学習のようにそれだけを単独で取り上げてできるものではありません。語彙力ドリルのようなもので身につけることはできないのです。
語彙力は、読書や日常の対話を通して、実際の文章の中でその語彙を味わって理解することによって身につきます。
この語彙力が最もよく表れているのが、森リンの点数です。特に、表現語彙の点数は、その子の語彙力とほぼ比例しています。そして、それは学力の可能性とも比例しています。
特に、中学生や高校生の論説的な文章では、森リンの点数はそのままその子の学力と同じと考えてもよいと思います。
では、家庭でこのような語彙力や作文力をつけるためには、どうしたらいいのでしょうか。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55)
はやぶさのカプセルにあった微粒子が、小惑星イトカワのものだったと発表されました。
燃えつきながら帰ってきたはやぶさ、ありがとう。

====毎日新聞より引用====
小惑星探査機:はやぶさ採取「イトカワ微粒子」 人類に巨大な一歩
7年間、計60億キロに及ぶ前人未到の旅に挑んだ小惑星探査機「はやぶさ」が、人類の宝ともいえる大きな「土産」を持ち帰っていたことが16日明らかになった。プロジェクトを率いた川口淳一郎・宇宙航空研究開発機構(JAXA)教授は「胸がいっぱい」と声を震わせ、関係者は称賛した。「500点満点」の成果を元に、今後は世界中の科学者が太陽系の誕生の秘密に迫る。【八田浩輔、足立旬子】
◇JAXA教授「夢超えた」
「帰ってきただけでも夢のよう。夢を超えたことで、どう表現してよいか分からない。点数はない。付けたくない」と川口さんは語った。
03年の打ち上げ当時、はやぶさが数多くの人類初の技術に挑むため、イトカワの試料の採取成功まですべて達成した場合「500点に値する」と話していたが、喜びを抑えきれない様子だ。
昨年11月中旬、はやぶさのイオンエンジンにトラブルが生じ、暗雲が漂ったが、奇跡的に復活した。川口さんは「想定を超える成功が重なった。7年間もさることながら、プロジェクトを始めて15年。その前から数えると四半世紀になる。感慨無量。苦労が報われ、よかったなと心から思う」と顔を紅潮させた。
会見には、藤村彰夫JAXA教授、微粒子を電子顕微鏡で分析した中村智樹・東北大准教授らも同席。藤村さんは「最初カプセルを開けた時に真っ青になった」と明かす。微粒子が0・01ミリ以下で、目に見えるものがなかったからだ。地球外物質と特定された1500個の微粒子の中には、地球上の物質に含まれるものもあれば、存在しないものもある。中村さんは「分析を進め、地球にほとんどない結晶を見つけた時は、ガッツポーズの瞬間でした」と語った。
18日の政府の事業仕分けでは、JAXAの運営費交付金削減も議論される。川口さんは「イノベーション(革新)には時間がかかる。将来への投資として近視眼的にならないでほしい」と注文を付けた。
◇「努力完結、素晴らしい」 関係者から続々喜びの声
はやぶさのカプセルからイトカワの物質が確認されたことに、関係者の間で「よくやった」と喜びの声が広がった。「宇宙戦艦ヤマト」など宇宙関連の作品をヒットさせている漫画家、松本零士さんは「人類によって地球が傷つけられている今、他天体の物質を探究することは、地球を守るためにも不可欠な活動。試料はとても小さいが、人類にとって巨大な一歩だ。日本がやりとげたことも素晴らしい」と喜んだ。
試料確認の立役者となったのは、はやぶさが宇宙空間で切り離したカプセルが、大気圏で燃え尽きずに帰還したからだ。カプセル開発の責任者、山田哲哉・宇宙航空研究開発機構(JAXA)准教授は「はやぶさの航行後、試料の分析へとバトンをつなぐことができ、ほっとしている。努力をしたかいがあった」と語った。
はやぶさを擬人化したゆるキャラ「はやぶさ君」の作者、小野瀬直美さんは「多くのトラブルを克服しながら、よく帰ってくれた。『あなたの帰りを待っている7年に分析技術も飛躍的に向上しました。小さな試料であっても、がんばって解析し良い成果が出るでしょう』と声をかけたい」とねぎらった。
はやぶさを主人公にした映像作品「HAYABUSA BACK TO THE EARTH」を制作したコンピューターグラフィックス(CG)ディレクターの上坂(こうさか)浩光さんは「ニュースを聞き、体が震えた。はやぶさの努力がすべて無駄にならず、完結できたことが素晴らしい」と声を弾ませた。
この作品は、全国30カ所以上で上映され、20万人を動員した。はやぶさ帰還と今回の成果を含めた完結編は、24日から東京都渋谷区のコスモプラネタリウム渋谷で一般公開される。【永山悦子】
====引用ここまで。====
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。科学(5)