
引力が距離の2乗に反比例するのは、表面積=4×π×半径の2乗だからです。
スマホでも、お菓子でも、漫画でも、距離が近くにあればあるほど手を出したくなる力が強くなります。
距離を離せば、それだけで引力は急速に弱くなります。
だから、例えば、いくらでも使っていいが、使ったら隣の部屋に置いておくというルールにするのです。
親が禁止するという外的な強制は、強制がなくなれば元に戻ってしまうので、根本的な解決になりません。
子供の自主性を育てるためには、物理的な法則を教え、その法則を生かす工夫をさせていくことです。
それは、人間の身体が物理的世界に属しているから、心の力だけではどうにもならないことがあるからです。
そういう工夫は、子供が、自分で自分をコントロールしなければならない年齢になったときに生きてくるのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
先日の保護者懇談会で意外に多かった質問が、子供が誘惑に弱いのでどうしたらいいかということでした。
誘惑に弱いのは、大人も同じです。
その大人の工夫の仕方を子供に教え、それによって子供が自覚的に誘惑と共存できるようにするといいのです。
誘惑に弱いというのは、生きる力があるからです。
最近、再開されたロボット犬アイボは、たぶん誘惑には負けません。
言葉の森のペット犬ゆめは、すぐ誘惑に負けます。
誘惑に弱い子は、人間的な子なのです。
静止摩擦力は、動摩擦力よりも大きいというのも、応用できる法則です。
作文を書くという重い作業をする前に、軽い作業が一つ入ると、やりやすさがかなり違ってきます。
だから、先生の電話指導があります。
それなのに、子供がゆっくり休んでいるときに、突然思いつきで、
「そんなにのんびりしているなら、宿題の作文書いちゃいなさい」
などと言うお母さんが意外と多いのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

先日、森林プロジェクトの会合で、作文教室を開いている先生からいろいろな話を聞くことができました。
その中で共通していた大事な指導のコツは、事前の予習を重視するということでした。
作文の勉強をしに来る生徒が、ただ単に教室に来れば指示が与えられて作文を書くだけというのでは、よい作文は書けないのです。
これまでの作文指導の多くは、ただ書かせて、書かれたものを赤ペンで添削し、その添削をもとに生徒がよりよい表現を考えるという、どちらかといえば復習的な勉強を中心としたものでした。
この作文の事後的な見直しというものは受験作文の練習をする時には大切ですが、通常の作文指導では重視していません。
それは第一に、書いた文章見直すというのは、子供にとっても、また大人にとっても退屈な作業だからです。
そして第二に、その退屈な作業の割に、添削された箇所を直して作文が上手になる度合いはかなり限られているからです。
作文で大事なところは、骨格となる構成と、肉付けとなる題材です。
この骨格と肉付けは、作文を書いた段階で決まってしまうので、事後的に直すのは表面に現れる表現だけになります。
骨格と肉付けが決まっているものを、表面だけ直しても上手になる度合いは限られています。(※)
そこで大事になるのが、事前の予習なのです。
※言葉の森は、作文を次の要素に分解して指導しています。
1.構成、2.題材、3.表現、4.主題、5.表記、6.字数、7.内容
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
作文に予習を取り入れるというのは、言葉の森が初めて行ったことだと思います。
それまでの作文指導は、事後的な添削が中心でした。
今でも、作文の指導というと、赤ペンの添削を思い浮かべる人が多いと思いますが、その添削というのは、作文指導のごく一部です。
そして、添削は、赤ペンを入れる先生の苦労のわりに、生徒にとって役に立つのはごくわずかなのです。
それは、生徒の文章力がまだ発展途上にあるからです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55) 作文教育(134) 森林プロジェクト(50)

世の中には答えがある限られた問題だけではなく答えのない無数の問題が存在しています。
子供たちが成長して社会で活躍するときに大事になる勉強法は、何よりもまず熱意を持って取り組めるかどうかということです。
その熱意は、子供時代からの熱意の持った経験の中で作られて行きます。
先日思考発表クラブの準備に時間がかかるという話を書きましたが、この時間のあかる準備を子供たちが喜んでやっているのは、その勉強に熱意を傾けるものがあるからです。
その熱意の源は、自分の発表と他の友達との交流なのです。
オンラインの教育は、前評判のわりに、現在あまりうまく進んでいないように見えます。
ひとつの弱点は、低コストで高品質なものを提供しても、子供たちは飽きるということがあるからです。
一方、先生と生徒の関わりを大事にする個別指導では、コストがかかるようになるという弱点があります。
また、生徒どうしの交流は、それなりに子供たちを喜ばせますが、交流だけが目的になると、参加者の中のより安易な共通点でまとまる面が出てきます。
大事なことは、子供たちの勉強を、発表する形の勉強につなげていくことと、その発表を通して他の友達との交流を図ることです。
これまでの勉強は、発表を前提にしたものではなく習得を前提としたものだったので、テストの評価のように一律の枠組みの中で行われていました。
このようなテストの点数の発表は、交流のきっかけにはほとんどなりません。
習得するだけの勉強は、これからは自学自習で行い、その一方で発表する勉強を少人数の交流の中で行うというスタイルのオンライン教育がこれから必要になってくると思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
途上国には、満足に学べない子供がいます。
しかし、それは途上国の問題です。
先進国には、学ぶことにあきた子供がいます。
それが、先進国の問題です。
途上国に、日本の教育を輸出するという話がありましたが、肝心の日本の教育が今行き詰まりつつあるのです。
これを打開する方法の一つが、熱意を持って取り組めるオンライン教育になると思います。
しかし、オンラインと熱意とコストというものは、今はまだうまく結びついていないのです。
その話を、今日の森林プロジェクト交流会で少しだけ話したいと思います。
熱中すると、時間のたつのを忘れます。
しかし、時間をかければ熱中したことになるかというと、そういうことはありません。
逆に、本人の意欲に関係なく時間だけかけるようにすると、かえって熱中する力がなくなってしまいます。
受験勉強は、最後の一年間の集中力がものを言います。
だから、それまでの普段の勉強は、普通にできているぐらいで十分で、その分熱中できる力を育てておくといいのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) ICT教育(1)
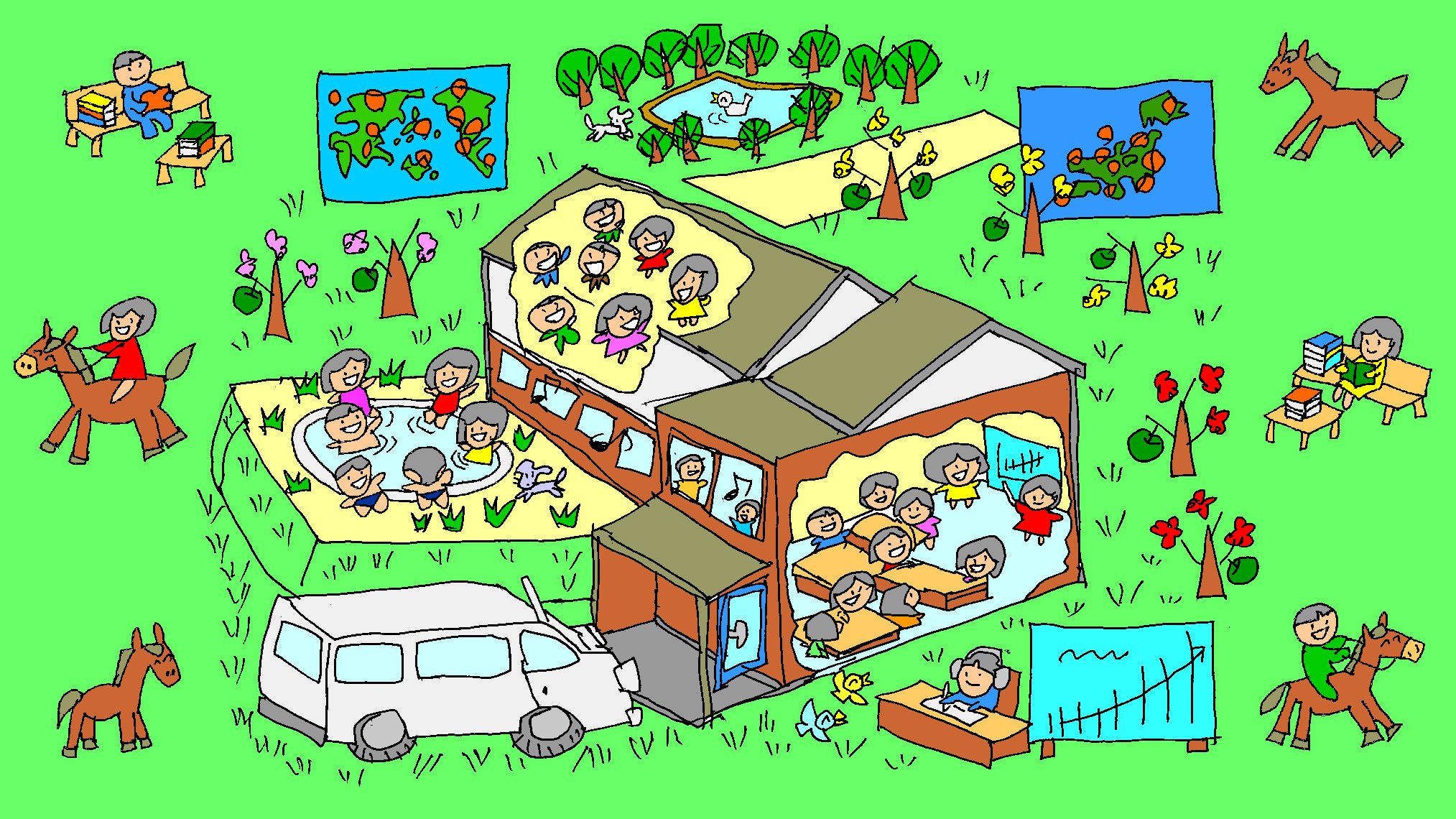
これまでの社会では、大量の情報を習得しそれらを統合し活用する能力が優れた能力だと見なされてきました。 人間には誰でもそのような能力がありますが、それは実は人間に向いている能力ではありません。
向いていないからできる人が少なく、だからこそその少数のよくできる人、又は努力した人が尊ばれてきたのです。
この時代は、まだこれからしばらく続くかもしれません。
しかし、変化の波は意外に早くやってきます。
ただし、教育の分野は時代から何歩も遅れて変化がやってくるので、しばらくは教育も昔ながらのものが価値あるものとして残るでしょう。
この能力を磨く方法のひとつが、暗唱という学習方法です。
この能力は、これからの社会では、最も重要な能力ではなくなりますが、それでも人間にはかなり役立つ能力として残ります。
だから、従来の教育は、それなりに必要なものとしてこれからも存続していきます。
しかし、これからの社会で、最も価値ある能力となるものは、この従来の能力ではありません。
ダイヤモンド・オンラインに、孫氏が記事を載せていました。
「AIが雇用を奪うとどうなるか【孫泰蔵】」
http://diamond.jp/articles/-/140483
この、人工知能の登場によって、これからの人間に必要とされる能力が大きく変わる、というのが、これからの子供の教育に関して考えなければならないことです。
漢字力や計算力は、学力の基礎ですから、これからも勉強の基本として残ります。
しかし、今、漢字が書けないと困るとか、計算が速くできないと困るということは、社会生活の中でほとんどなくありません。
これと同じことが、今までの大学入試で評価されるほとんどの知識で生じてくるのです。
では、これからは何が最も重要な能力となってくるのでしょうか。
従来の意味での知性の重要さは、これからも残るでしょう。
しかし、その知性のかなりの部分は人工知能によって代替されていきます。
人工知能に取って代わられない人間の能力としての個性と感性がこれから重要になってくるのです。
その中でも、特に重要なものが個性です。
世の中に、新しいものを生み出す独創力が、これから最も価値ある人間の能力となってくるのです。
その独創力は、どのようにして育つかというと、私は、熱中と難読からではないかと思います。
何かに熱中すれば、必ず自分の限界を超えるものに挑戦する場面が出てきます。
その挑戦の場面で、独創力が必要となり、挑戦の繰り返しによって独創的な力が育ちます。
そして、その独創力の素材となるものは、表面的な知識ではなく、より根源的な知識です。
その根源的な知識は、古典的な難解と言われる読書からもたらされます。
それは、難しい本というものは、根源的な知識に近づこうとしているからこそ難しくなるからです。
だから、子育ての中心は、子供自身が熱中できる遊び、本人の関心に基づく豊富な読書、そして感性を育てる両親や友達との対話、ということになってくるのだと思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
「AIが雇用を奪うとどうなるか」という記事を、孫泰蔵氏が書いていました。
これは、多くの人が既に言っていることですが、実際の教育の場では、「そんな先のことより、今の成績をどうにかしたい」という声の方がずっと多いと思います。
しかし、長期的な子育てを考えた場合、未来の社会の変化を想定しておくことは重要です。
これからの子育ての重点は、遊びと暗唱と読書と対話と、それらを統合する機会としての作文になると思います。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 未来の教育(31)

先日、思考発表クラブの懇談会で、保護者の方から、「毎回、面白い実験などを考えるのに、親も苦労している」との声が出ていました。
確かに、毎週の生徒の発表は、毎回力作で、どの子も生き生きと発表しているのですが、準備に時間がかかることが感じられるものがとても多かったのです。
思考発表クラブでやることは、読んでいる本の紹介と、次の週の作文課題の構想図の発表ですから、その他の発表は自由です。
ところが、以前、作文の構想図以外にも、理科実験や工作や算数数学の問題作りをやっていたことがあるので、その延長で、理科実験を自宅でやってくる子がかなりいます。
これらの自由な発表は、発表する生徒も楽しんでいますが、それを見ている生徒も、毎回ほかの人の発表を楽しみにし、それに刺激を受けているようでした。
ただし、あまり保護者が苦労しているというのも問題なので、この保護者の関わりをどうするかということを考えました。
まず、第一は、親が苦労を楽しむということです(笑)。
親が子の成長の関われる時間は、過ぎてしまえばほんのわずかな時間だったと思うようになります。
そのわずかな時間を、共通の知的な経験を通して過ごしたということは、親にとっても子供にとっても貴重な思い出になると思います。
また、そういう経験を通して、親も子も成長していくのです。
今は共働きの家庭が多く、両親の帰宅時間も遅いことが多いので、親子で共通の時間を過ごす機会は日曜日ぐらいしかないかもしれません。
しかし、その日曜日を、がんばって子供と一緒に過ごすようにするのです。
とは言うものの、すべて親のがんばりに任せるのでは限界があります。
そこで、第二に考えたことは、理科実験や工作の例を、「親子で遊ぼうワンワンワン」などで互いに紹介していくことです。
子供が楽しめる理科実験や工作などの本は、結構たくさん出ていますが、どの本も、実際に使えるのはあまり多くありません。
面白いものは、準備がかなり必要だったり、逆に、簡単にできるものは、結果が対して魅力的でなかったりということが多いのです。
それを、親子で遊んだり学んだりすることに関心を持つ多くの人の協力で、互いに情報を共有していけたらと思っています。
また、これに関連して、やはり思考発表クラブで、子供たちの紹介する本の情報が多くの人の参考になると思うので、この本の紹介も、Facebookグループの「読書の好きな子になる庭」などで生かせるようにしていきたいと思っています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
子供の遊びや読書に関する情報交換は、今子育て中の人ばかりでなく、もう子育ての終わった人も、これから子育てする人も(自分の子供時代を思い出して)共有できると思います。
11月の森林プロジェクトの交流会でも、このあたりのことを話す予定です。
今の親は、昔の親よりも忙しいと思います。
しかし、そこをがんばって親子の関わりの時間を増やしていくことが大事です。
昔、うちの子が通っていた保育園の園長先生は、「自営業者の子は預かりたくない」と、はっきり言っていました。
私はそのころ自営業者だったので(笑)、それはよくわかるなあと思いました。{納得するな)
親が忙しいと親子の関わりがどうしても薄くなり、そうすると、子供がバランスよく成長しないのです。
だから、どんなに多忙でも、子供が小さいときは親はがんばって一緒に遊んであげることです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) 子育て(117) facebook(29)

先日の小1~小3の保護者の懇談会で、次のような質問がありました。
「作文の構想図を子供がまだ書けないので、親が書いてやっているが、それでいいのか」ということでした。
小学1年生から3年生ぐらいの子は、まだ自分で要領よく構想図が描けない方が多いものです。
そのときは、親が子供と話をしながら構想図を書いてあげ、それを参考に子供が作文を書くということでいいのです。
しかし、その質問のお母さんは、「子供がこれまで曲がりなりにも自分で作文を書いていたのに、親が構想図を書いてやるようになってから、親の書いたものをそのまま写すようになっている」ということを問題にしているのでした。
けれども、私の答えはそれでいいということです。
「それでいい」という理由は、二つあります。
第一は、子供は学年が上がれば必ず自立するようになるからです。
親は、その子が自立するときの手本を教えていると考えるとよいのです。
勉強に限らずどんなことでも、誰でも最初の自信がないうちは、見ているだけのことが多いものです。
見ているうちに自分でもできそうだという自信がつくと、自然にやってみたくなるという流れがあるのです。
第二の理由は、勉強というものの考え方がこれから変わってくるからです。
それは、いい手本を見ることが勉強になるという考え方です。
例えば、算数数学の難問を解く場合、自分で何時間も考えるという方法と、すぐに解法を見て解き方を理解するという方法があります。
自分で考えるというのは、一見正道のように見えますが、難点は時間がかかることです。
ノーベル賞級の最先端の数学の世界であれば、自分で何ヶ月も何年も考えるというのは価値があることでしょう。
しかし、入試問題のレベルの算数数学で、自分で何時間も考えるという無駄な勉強だと考えた方がいいのです。
勉強は、答えや解法を見て理解して、すぐにできるようになることで基礎力がつきます。
その基礎力の土台の上に、自分で考える実力がついたところで、その子にとって答えのない世界で考える機会が出てきます。
その答えのない世界とは、遊びであったり、勉強であったり、又は将来の仕事であったりするのです。
したがって、親が子供の勉強や作文の手助けをするときは、親自身がそれを不本意な手助けだと思ってやるのではなく、逆に親が楽しめるくらい積極的にやっていくといいのです。
それは例えば、構造図を書くときに、ダジャレを使ったり、たとえを入れたり、親の感動的な体験実例を教えてあげたりすることです。
それを、子供に対する押し付けではなく、親が楽しむような余裕を持って行っていくのです。
余裕を持つということは、ほとんどアドリブで手助けをするということです。
もちろん余裕があれば、下準備をして手助けをしてあげることもいいのです。
しかし、準備しすぎるとつい子供にもそれに対応した努力を要求するようになりがちです。
それは、子供の自主性にとっては逆効果です。
子供が小学1年生や2年生のときは、親の子供に対する見方を次のように変えていく必要があります。
「今ここで親の最良の手本を見せておけば、その土台の上に、子供が高校生になったときにやがて親の今のレベルを超えるような考え方をするようになるはずだ」という見方です。
できるだけ視野を遠くに置いて、子供の成長を見ていくとよいのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
自分でやらなければ力にならないということは、そうだとも言えるし、そうでないとも言えます。
まだ実力がないうちは、本人が安心して取り組めるように、手本だけ見ていればいいというふうにしておくことです。
作文の場合、本人がなかなか書けないときは、お母さんがすぐに手伝ってあげることです。
その手伝い方を見ることが、子供の勉強になるのです。
私が、「子供が困っていたら、すぐに手伝ってあげるといい」と思っているのは、子供時代はいつも安心して暮らしていた方がいいと思うからです。
子供は自信がつけば、自然にひとりでやるようになります。
自信の源は、安心して暮らした子供時代にあるのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25) 勉強の仕方(119)

小6の思考発表クラブの懇談会で、次のような質問がありました。
ひとつは、「子供が物語文の本ばかり読んで、説明文の本を読まないので、図書館の物語のコーナー以外のところから本を探すようにアドバイスしたがどうか」というものです。
「図書館を利用して」「子供が自主的に選ぶようにする」というのは、とてもいい方法だと思います。
小学校高学年になると、子供自身に向上心が出てくるので、親が的確な方向を示してあげると、自分なりに工夫してやっていくようになります。
もうひとつは、「子供が読解の問題を解くときに、元の文章に何も書かずに読んでいる。もっと接続詞を囲むとか、同じ言葉が出てきたところに線を引くとかしたらいいのではないか」という質問でした。
このことに関しては、以前記事を書いたことがあります。
「問題文の接続詞を四角で囲む子――国語の勉強法は他の勉強法とは異なる」
https://www.mori7.com/as/2507.html
「国語は問題文に線を引いて読む」
https://www.mori7.com/as/2434.html
難関校の国語問題ほど長い文章を読ませることが多いので、普段から問題の文章には線を引いて読む習慣をつけておくといいです。
しかし、あまり詳しく線を引いたり記号をつけたりする必要はありません。
本当は、説明的な本をよむ場合には、本にも線を引いて読む習慣にするといいのですが、そうすると、ほかの人が読めなくなってしまいます。
将来は、kindleなどを子供に与えて、そこで自由に線を引いたりメモをしたりして読むようにするといいと思います。
そして、いずれkindleも、メモに音声入力機能がつくようになると思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
世間でよく行われている国語の勉強法には、回りくどいものが多いようです。
要約の練習をするのに、「一段落ずつまとめさせる」などというのもそうですし、今回の質問にあった「問題文を読むときに記号をつける」などというのもそうですし、作文を書く前に「構成メモを書かせる」などというのもそうです。
国語の成績のいい子は、たぶんそういう面倒なことはしていません。
回りくどい方法が多い理由は、国語の成績を上げる確実なノウハウがないことの表れです。
つまり、国語を教える先生は、することがないので(笑)、そういう面倒な手順を必要にさせて授業を進めているのです。
(学校などでよく行われている作文の前の構成メモと、言葉の森で行っている構想図(構成図)は、似ていますが意図と方法が違います。)
ところで、国語の勉強がそうなるのは、国語の先生の問題ではありません。
国語という教科自体が、答えのない部分がほとんどだという特殊な教科だからです。
だから、灘中灘高の橋本先生のような授業もできる半面、高校の国語の時間は休憩時間と考えている高校生も出てくるのです。
では、国語力はどうやってつけたらいいかというと、それは、読書と音読と暗唱と作文になると思います。
懇談会の時間は、5、6人で15分から30分程度でしたから、あまり長くはありませんでしたが、それでもいろいろな話が聞けてよかったです。
今後、思考発表クラブだけでなく、オンライン作文でも、自主学習クラスでも、懇談会を行っていきたいと思います。
言葉の森で受講している生徒の保護者のみなさんは、オンラインの企画はしたことがないという人がほとんどだと思いますが、今後はぜひオンラインの企画に参加してください。
今は、googleハングアウトですが、今後はZoomなども使っていく予定です。(skypeはまだ使いにくいところがあるので、今は部分的にしか使っていません)
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

子供が勉強している様子を見ると、すぐに気が散ったりぼんやりと考えていたりと、親から見て集中力のない様子が感じられるときがあります。
早く済ませればできるのに、長い時間をかけてやっているというのには、どういう原因があるのでしょうか。
第一は、早く終わると追加の勉強をさせられる可能性があるというケースです。
予定の勉強が早く終わったからといって、一度でもそこで追加する勉強をさせると、子供はそのことをよく覚えていて、なるべく早く終わらせないように時間をかけてやるようになるのです。
特に、作文の勉強は、そのときのテーマによってかかる時間がかなり違います。
しかも、作文は、ほかの勉強と比べるとかなり頭脳を使います。
作文の勉強のあとは、ほかの勉強はしないで、せいぜい読書ぐらいにとどめておくといいのです。
第二は、ページ数などを決めてやらせるのではな、く時間を決めてやらせるような勉強になっていることです。
時間が経てばおしまいという形にすれば、自然にその時間の範囲をなるべく楽に過ごすようになります。
親の立場としては、時間で決めた方が管理しやすいですが、子供にとってはその時間は一種の奴隷状態の時間です。
時間の枠を決められると、自分で工夫して能率よくやろうという気にはなれないのです。
第三は、これがいちばん多い原因だと思いますが、勉強する時間が長すぎるか、勉強する量が多すぎることです。
子供は、すぐに終えられるものだと思えば、早く終わらせて、あとは自由に遊びたいと考えるはずです。
ところが、目の前に膨大な量の勉強があったり、長い時間が待ち受けていたりすると、どうしてもすぐに取りかかる気にはなれないのです。
これも、特に作文の勉強の共通することですが、ひとまとまりの作文を書こうとすれば、大体1時間はかかります。
小学校高学年や中高生で、いい文章を書こうと考える生徒は1時間半かかります。
社会人の方が作文の練習をする初めのころは、大体3時間かかります。
作文の勉強は、今日は30分だけ書いて、明日は続きの30分を書くというわけにはいきません。
だから、作文の勉強を始める前は、多くの子が、ちょっと本を読んだり、ちょっと手遊びをしたりして、心の準備をしてから取りかかるのです。
作文の勉強の場合は、長くかかるのはやむを得ません。
その代わり、続きを翌日に持ち越すようなことはせずに、その日に書き終えるところまで行かなければ、「(つづく)」と書いてそれで終了にした方がいいのです。
この場合、「つづき」を書く必要はありません。
書く見通しを考えたことが勉強の中身ですから、最後まで書き上げられなくてもいいのです。
話は少し飛躍しますが、この書くことに時間がかかる問題を、将来は音声入力でカバーできるようにしたいと思っています。
やり方は、まず作文の構想図を10分か15分で書きます。
この構想図を書く過程が考える勉強ですから、作文の中身のいちばん大事なところです。
そのあと、その構想図をもとに音声入力をします。
音声入力は、考えながらゆっくり話すので、普段の会話の3分の1から5分の1のスピードです。
すると、10分で1000字程度の文章になります。
今は、人工知能で音声がかなり正確にテキスト化されるので、手直しは句読点をつけるぐらいです。
欧米の言語では既に句読点を自動的につける機能があるようですが、日本語にはまだ対応していません。
しかし、これは技術的には簡単なことなので、いずれ日本語の音声入力にも句読点が自動的につくようになると思います。
このようにすれば、考える時間も、手直しの時間も含めて、それまで1時間から1時間半かかっていた作文を30分弱で仕上げることができるようになります。
これは、いずれオンライン講座としてやっていきたいと思っています。
さて、話を戻して。
作文の勉強の場合は、ひとまとまりの作文を書くのに時間がかかるのは、今の段階ではやむをえません。
しかし、他の勉強に関しては、小学生のうちはあまり長時間勉強させないことが大事です。
なぜなら、長時間勉強に取り組む動機が、まだ小学生には自分の中にないからです。
子供が成長して中学3年生の受験期になったり、高校生になり大学入試に取り組む時期になったりすれば、誰でも自然に集中力を発揮するようになります。
その時期の自分の内側から湧き上がった集中力が本当の集中力で、小学生の間はもともとそういう集中力がないのが本来の姿です。
ですから、小学生の間の勉強はなるべく短時間で終わるものにして、親は、子供が勉強などに集中せずに気を散らす方がむしろ自然だと思って、もっと手を抜いた勉強の仕方をしていくといいのです。
ちゃんと育っている子であれば、必要なときには必ず集中力を発揮します。
今集中力がないのは、まだそういう場面やそういう時期でないからなのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
大人の場合、集中力がなくなるのは、つまらない仕事か、長くやりすぎたからかです。
それでも、やらなければならない仕事のときは、大人はうまく工夫しながら、そしてうまく手を抜きながらやり続けることができます。
子供が勉強に集中できないとしたら、そこには大人が仕事に集中できないときと共通する問題があると思ってあげることです。
そして、一度ボタンを押せばずっと集中できるロボットのような子よりも、すぐ集中が途切れる子の方が安心と思っておくことです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)