「教育激変」という本の中で、対談している池上彰さんと佐藤優さんが、それぞれ次のように述べています。
佐藤「誤解を恐れずに言えば、アクティブラーニングは基本的にエリート教育だと思うのです。自ら考えをまとめて説得力のある話しをするというのは、指導的な立場になる人たちにとって必要なスキルでしょう。」
池上「何度も言いますが、私は『自ら考えプレゼンする』といった力が、これからの世の中には必要で、それは必ずしも必要的な立場に就く場合ではなくても同じだと思うんですね。ただ、自分が教えている大学をみても、すぐにアクティブラーニングが可能な現場もあれば、かなり準備が必要なケースもあります。」
佐藤優さんは同志社大学の神学科で数人の学生たちに授業をしているそうです。
それが内容的にはアクティブラーニング的な授業になっているようで、5時間の授業を受けるために学生は30時間から35時間の準備をしなければならなくなっているそうです。
二人が述べているように、アクティブラーニングは優秀な生徒でないとその効果を発揮しない面があります。
子供たちが発表したり討論したりする形の授業も、内容が伴わければ形だけのただの雑談のような時間になってしまいます。
ひるがえって、言葉の森の作文の勉強を考えてみると、オンラインの少人数クラスの作文はまさしくアクティブラーニングの勉強なのだと思います。
作文は、書くことよりも、事前の予習で両親に取材をしたり自分の実例を考えたりしてくることが大事です。
今世間で行われている作文の指導や、市販されている作文のドリルは、すべて書くことを中心とし、書いたあとの添削を中心としたものです。
添削で作文が上達するのは、作文学習の初期のうちだけです。
作文は、事前の長文音読と構造図という予習によって上達するのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
通常の勉強は、習うことが勉強です。
だから、何の準備もなしに行って、そこで教わってくればいいのです。
作文は、何の準備もなしに行って、そこで書いてくればいいというのではありません。
少なくとも、それでは上達に時間がかかります。
事前に長文を読み、内容を理解し、両親に似た例を取材し、材料を準備してくることが勉強なのです。
作文と同じように、読書もアクティブラーニングです。
読書は、どこかに行って読書の練習をするような勉強ではありません。
家庭で読んでいる本をみんなの前で紹介し、質問や感想を述べ合う勉強です。
それが、今オンラインクラスでやっている読書紹介です。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。アクティブ・ラーニング(0)
読解検定を11月22日から28日の予定で実施しています。
試験の申し込み日に受検できなかった人は、他の試験日にふりかえて受検することができます。
今回の問題は、学年によってかなり難しいものもあったようです。
普段の勉強を見ていると国語力があると思われる生徒も、意外と低い点数でした。
検定結果は随時返却します。
結果が届きましたら、×になったところを見直して、理由を確かめておいてください。
この見直して理由を考えるというのが最も大事な国語力をつける勉強になります。
また、問題を見て正解が納得できないという場合は、保護者掲示板、又は、「国語の得意な子になる丘」掲示板、又は、同名のfacebookグループから、質問事項を入れておいてください。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0) 生徒父母連絡(78)
子供は、物を作るのが好きです。
本当は、大人もそうです。
その反対に嫌いなのは、物を作らされることです。
それは、大人も同じです。
物を作るのが好きなのは、そこに自分らしい工夫と発見と創造があるからです。
作らされるのが嫌いなのは、その反対だからです。
普段の勉強では、工夫と発見と創造は必要とされません。
むしろ、解法を読んで理解することが勉強の基本です。
答えのある勉強は、それでいいのです。
教えたやり方で解くというパターンを覚えることももちろん必要だからです。
しかし、自分らしいやり方で失敗することもそれ以上に必要なのです。
湯川秀樹氏が、好きだった数学をやめて物理に移ったのは、数学の試験で答えは合っていたものの先生の教えたやり方で問題を解かないために×になったからでした。
勉強の基本は、読み、書き、考える力をつけることです。
そして、答えのある世界では、答えにできるだけ早く近づくように先人の解き方のパターンを理解することです。
しかし、これから必要になる学力は、それらに加えて、自分らしい創造をする力です。
以上の三つの勉強の分野は、それぞれ、
作文読解クラス、
自主学習クラス、
創造発表クラスの勉強分野です。
創造発表クラスでは、従来の勉強ではない、創造的な勉強を中心にしていきます。
その勉強に向いているのは、小学校の教科で言えば、理科、図工、社会、数学、英語、国語の順です。
数学や英語や国語でも、創造的な勉強をすることはできますが、教科の体系が確立しているので、なかなか創造的なところまでは行けません。
理科と図工と社会は、教科の体系よりも、対象となる分野の方がずっと広いので、そこでさまざまな創造が可能になるのです。
理科実験は、小学校高学年でなければ難しい面もあるので、創造発表クラスでは低学年向けにせいかつ文化の分野を追加しました。
しかし、子供たちにとっては図工の分野の方がより面白く参加できるので、新たに図工の分野の参考図書を追加します。
図工は、STEM教育で言えば、サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・マセマティクスのうちのエンジニアリングの教育です。
物を作るときに必要な能力は、状況に合わせたさまざまな試行錯誤を工夫する力で、それはプログラミングに必要な能力と同じです。
今はまだプログラミングは、プログラミング言語を学ぶことが大きな目標になっていますが、将来は言語的なことはAIがカバーするようになります。
すると、プログラミング教育で人間が行うことは何かと言えば、それは工夫し創造することなのです。
工夫と創造には、ものづくりだけでなく、料理もファッションもあります。
スポーツも音楽もデザインも、本当の目標は創造です。
しかし、体系が確立しているものでは、個人の創造する余地はかなり上達してからでなければ出てきません。
だから、子供時代は身近な工作を通して、その創造の感覚を育てていくといいのです。
【図工の参考図書】
小学生の自由工作バーフェクト高学年編 成美堂出版編集部 成美堂出版


リサイクル・ネイチャー素材で作る 小学生のアイデア工作 改訂版 蓮見 国彦 (監修) 学研プラス
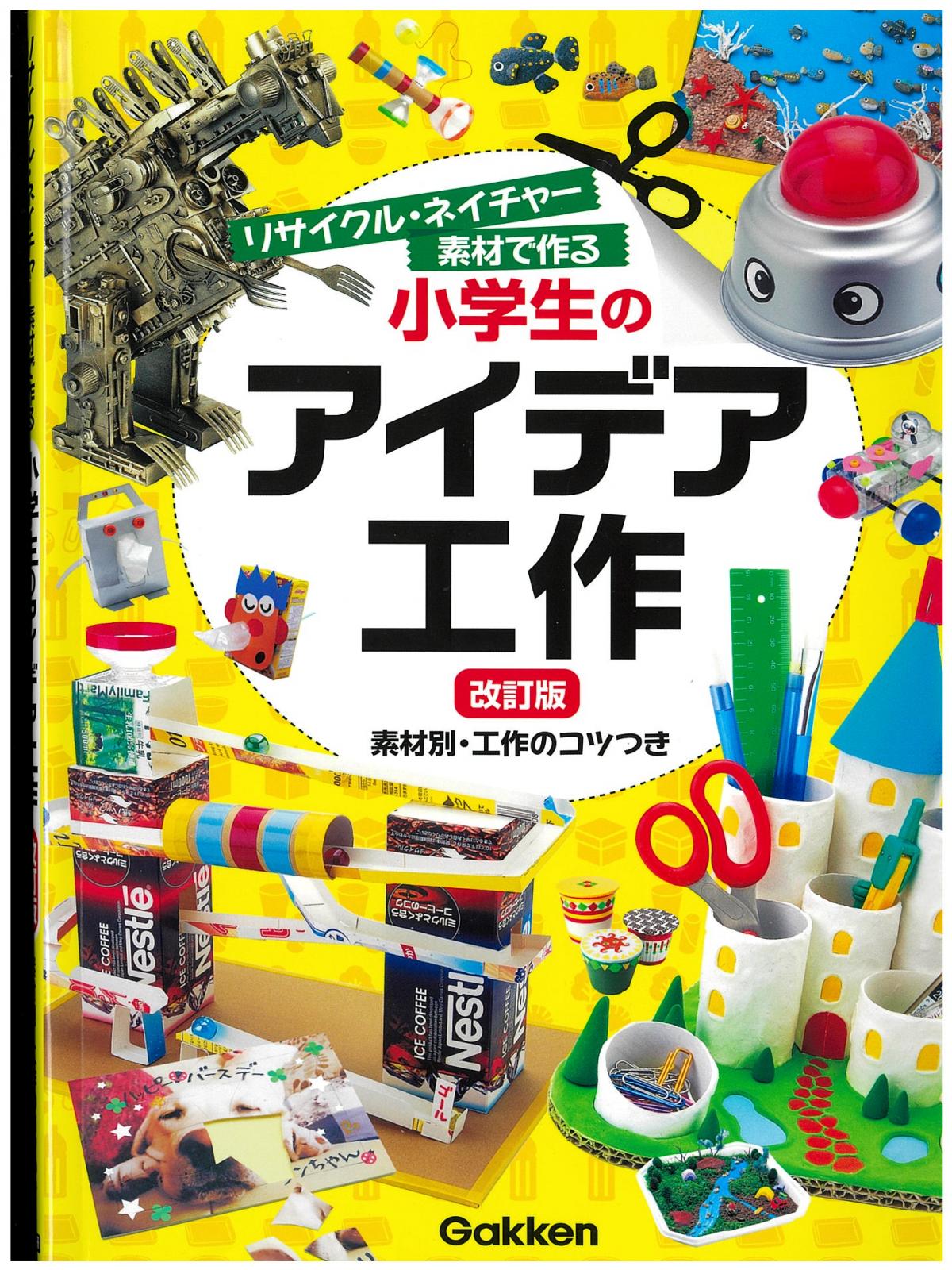

工作図鑑 かざまりんぺい 主婦の友社
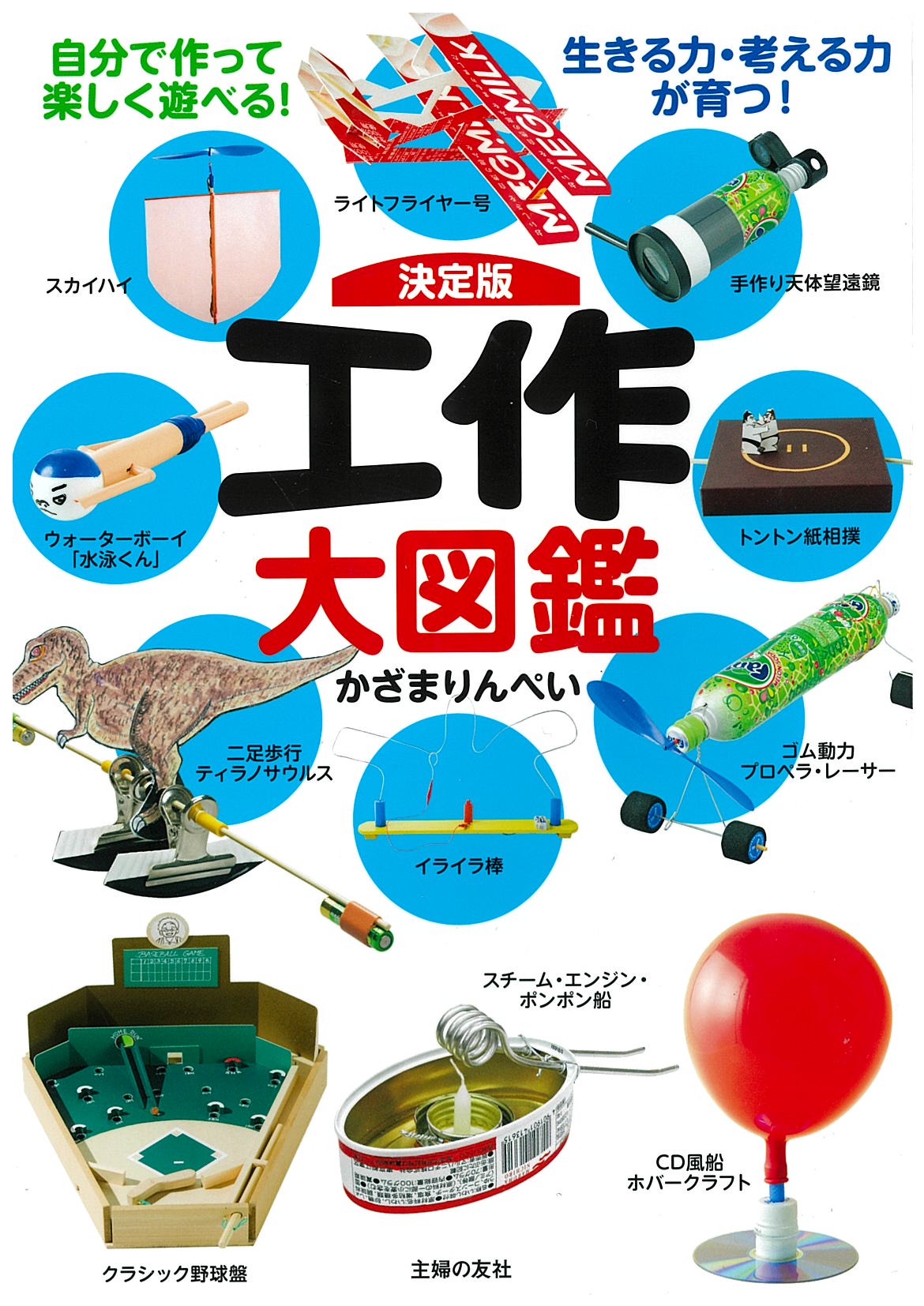
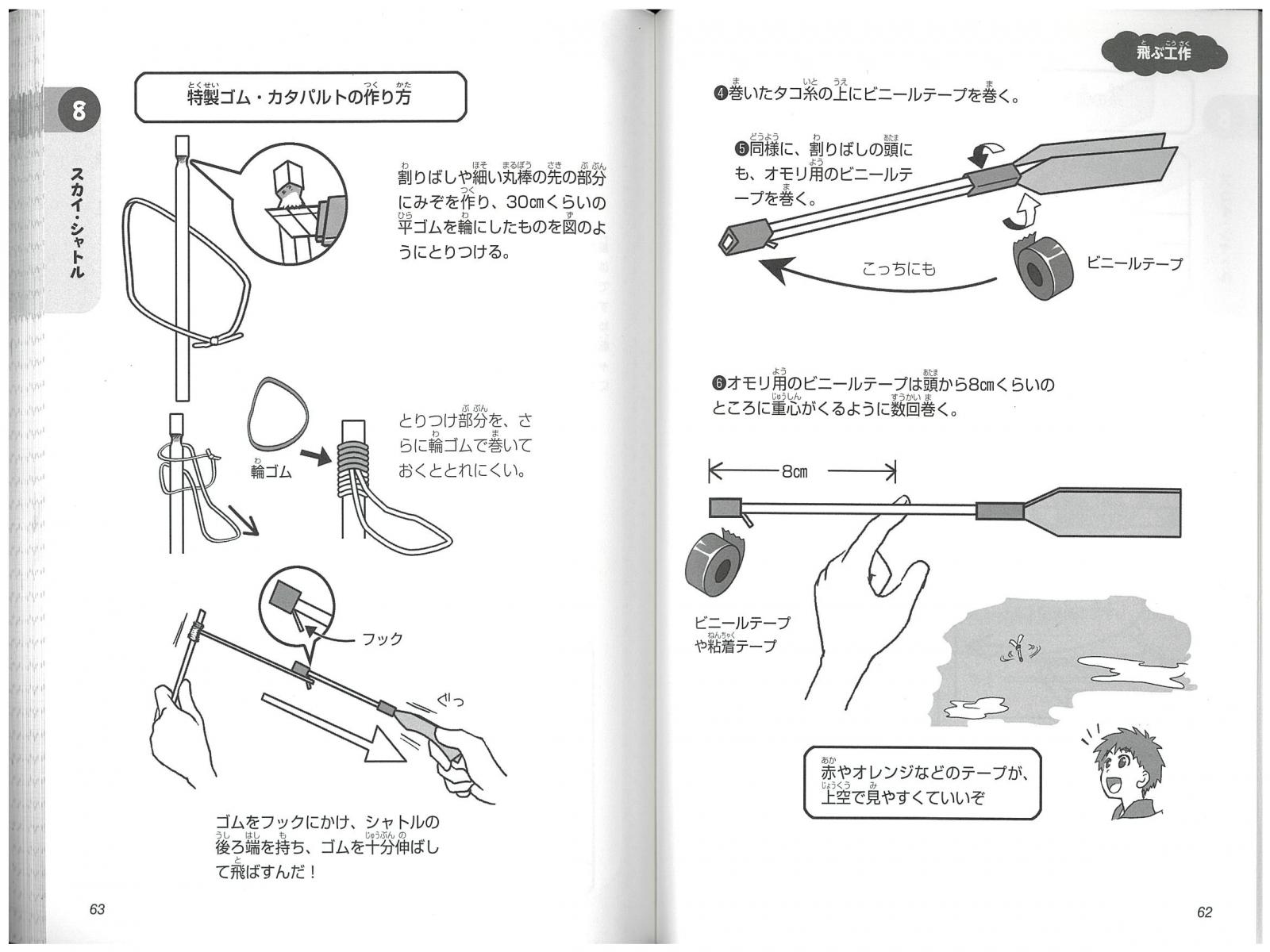
【
前回紹介した理科実験の参考図書】
実験おもしろ大百科 科学編集室 学研プラス
でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験 米村 でんじろう 主婦と生活社
理系アタマがぐんぐん育つ科学の実験大図鑑 ロバート・ウィンストン/西川由紀子訳 新星出版社
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
これからの子供たちの教育は、従来の枠では収まりません。
国語・算数・理科・社会・英語の主要五教科ができていればいいというのは、一昔前の話でした。
新しい教育の分野の一つはSTEM教育です。
しかし、その先にあるのは創造の教育なのです。
STEM教育にA(アート)を付け足してSTEAM教育という人もいますが、次に来るものはアートではなく心身です。
これは日本から発信する新しい教育概念になると思います。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) ()
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 読解力・読解検定(0)
小学生の勉強で大事なことは、毎日の学習習慣をつけることです。
宿題があるから勉強するとか、テストがあるから勉強するとかいうやり方ではなく、何があってもなくても毎日決まったことを決まったようにやる習慣をつけておくことが大事です。
それも決して長時間やるのではなく、短い時間でいいので決めたことを淡々と続けていくことが大切です。
たまに集中的に1時間も2時間も勉強するようなやり方では力はつきません。
しかし、毎日の習慣があればそれだけでいいというのではありません。
毎日の勉強の習慣がある生徒によく見られることで、作業的な勉強をしているだけということがあります。
よくある例が、問題集やプリントを1日何ページまたは何枚という形でこなしていくことです。
この勉強がよくないのは、できる問題だけできて、できない問題は結局できないままで終わってしまう場合が多いことです。
子供は、できる問題だけをやったとしても、それが勉強だと思っています。
親も、子供が机に向かっていれば、それが勉強だと思っています。
しかし、できる問題をいくらやってもその問題に慣れる以外の効果はありません。
勉強はできない問題ができるようになることと、そして、もう一つは読む力をつけることこの二つが中心なのです。
言葉の森の自主学習クラスでは、国語の問題集読書と算数の問題集練習を勉強の中心にしています。
国語の勉強は、問題集を繰り返し読むことと、60字の記述練習をすることです。
算数数学は、できないところがなくなるまで1冊の問題集を繰り返し書き直しすことです。
この二種類の勉強は、どちらも子供に任せていてはなかなかできません。
国語問題集は適当に読み流し、算数数学問題集はできる問題だけをやって済ませる子が多いからです。
そこで、先生がチェックする仕組みになっています。
しかし、先生がチェックするだけでは不十分なので、保護者懇談会などで先生と保護者の間の情報の交換ができる形にしました。
そうでないと、子供は特に算数の問題で、できなかったものもできたことにしてしまうことがあるからです。
中学生以上になればそういうことはありませんが、小学生の間は勉強の自覚がないので、形だけの勉強になってしまうこともまた多いのです。
ところで先日、保護者懇談会で、自主学習クラスのある日だけは一生懸命勉強をするが、他の日は宿題があるときぐらいしか勉強しないという声がありました。
勉強は、勉強する内容以前に、毎日やるという勉強の仕方の方が大事です。
自主学習クラスは、毎日やってもいいように受講料を低く抑えています。
言葉の森の作文の勉強をしている人であれば、月4回の学習で月額受講料が3,000円ですから、月曜日から金曜日まで週5日間行っても15,000円です。(計算をわかりやすくするため消費税を含まない金額)
このような価格で1時間、人によっては1時間以上何時間でも勉強する場所を提供してくれるところはありません。
そして、勉強の仕方は、自主学習と先生のチェックですから、一斉授業で先生に教わる勉強よりもずっと密度の濃い学習ができます。
また、勉強している間はカメラを机上に向けて取り組むようにするので、お互いの勉強をしている様子が伝わってきます。
すると、自然に自分自身の勉強もはかどります。
この自主学習の勉強とは別に読書紹介や暗唱発表もするので、読書や暗唱練習のきっかけにもなり、質問や感想を述べ合うことで生徒どうしの交流もできます。
自主学習クラスで勉強をしていれば、不登校で学校に行かない子であっても、勉強面では全く心配はいらないと思います。
先日の自主学習クラスで、中学生の生徒に最近の定期テストの結果を聞いたら、一人は全教科90点以上で、一人は数学が100点でした。
小中学校までは義務教育の基本的な勉強なので、やり方次第で誰でもできるようになります。
入試の場合も、基本は同じで、志望校の傾向に合わせた1冊の問題集を完璧にやるだけです。
まだ
自主学習クラスのよさが広くは伝わっていないので、今後フリーミアム参加をはじめとして、多くの人が見学や体験学習ができるようにしていきたいと思っています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
勉強の基本は自主学習です。
しかし、ひとりでやる自主学習では張り合いがなく、わからないことがあったときに聞ける人もいません。
だから、先生や友達と一緒にやる自主学習が、最も理想的な勉強になるのです。
自主学習で、勉強の自覚がまだない小学生のうちは、できない問題もできたことにしてしまう場合が出てきます。
そこで、勉強の進度に合わせたチェックテストと、毎月の定期的な保護者懇談会が必要になります。
チェックテストは2月から教材を変えて本格的に行っていきます。
毎月の保護者懇談会は今月からスタートしました。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0) 不登校(0)
「AIに負けない子供を育てる」という新井紀子さんの本に、子供の勉強に関する示唆的な話が載っていました。
富山県は全国学力テストでも上位の県です。
しかし、その富山県のある町で、小学校の成績がよい割に、中学での成績が伸び悩んでいるそうなのです。
その原因を探ってみたところ、それは小学校時代のプリント学習で穴埋め式の問題が出されすぎていたことにあったらしいのです。
穴埋め式の問題は作るのに手間がかかるので、先生の熱心さが表れやすいところですが、子供にとってはいくつかの単語から答えを類推できる勉強になってしまうので、本当の意味での読む力がつきません。
そのため、小学校時代の成績はよいものの、読み取る力が育っていないために、中学に入ってから学力が伸び悩むという関係になっていたようなのです。
小学校時代の成績のよさは、単純な知識や技能の成績のよさです。
中学、高校に上がってからの成績は、理解する力と考える力による成績です。
小学校時代に読む力や考える力をつけていないと、中学に入ってから成績が伸びず、それが高校生以降も続くのです。
では、小学校時代はどんな勉強をしたらよいかというと、それはいつも書いているように、小学生の間は読書を最優先し、その読書も説明文を含む読む力の必要なものに発展させていくことなのです。
読む習慣をつける最も簡単な方法は読書紹介です。
自分の今読んでいる本を他の人に紹介し、他の人から質問や感想を聞くということが、子供たちの毎日の読書の励みになっています。
読書紹介ができるのは、まだオンラインの生徒に限られていますが、いずれ全員ができるようにしていきたいと思っています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
国語のよくできる子は、国語の問題集など解いていません。
何もしなくても国語の成績がいいのです。
それは、なぜかというと、毎日の読書生活の中で、自然に読む力をつけているからです。
しかし、この自然についた読む力では、百点を取ることはできません。
国語で百点を取るためには、解く力も独自につける必要があるからです。
先日、本屋さんの子供の図書コーナーに行って少し驚きました。
人気のある本というのが、題名だけはちゃんとしているものの、中身がほとんど漫画のようなものばかりだったからです。
スマホ時代の子供たちに合わせるために、ビジュアルな要素を大きく出して、できるだけ文章を読まなくても内容がわかるようにしているのです。
こういう本は、いくら読んでも知識が増えるだけで、読む力はつきません。
子供時代は、その子の読む力に少し負荷がかかる程度の文章中心の本を読んでいく必要があるのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)
11.4週は、作文読解クラス、創造発表クラスとも、発表交流会です。
11.4週の自由課題の資料を資料室に入れました。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)
作文の通信教育では、提出率は低いのが普通です。
それは、すぐに書かずに、作文の勉強を後回しにしてしまうからです。
この気持ちは、作文の勉強をしたことのある人ならわかると思います。
作文に限らず通常の教科の通信教育でも、その日にすぐにやらずにあとでやろうと思って勉強をためてしまうということがあります。
作文の場合は、普通の教科に比べて勉強する負担が何倍も大きいので、いったん作品がたまってしまうと、それが毎週雪だるま式に増えてしまうのです。
1日にまとめて2つか3つ書けばいいと考えるのは、自分で作文の勉強をしたことがない人です。
600字から1200字の作文を書いた人なら分かると思いますが、1日に異なるテーマで2つ以上の作文を書くというのはかなり大変なことなのです。
勉強は、その日のうちにやるのが基本です。
テレビ英会話などでも、録画しておいてあとで見ることができるという状態を自分に許すと、その日のうちにやらない習慣ができ結局続けられないことになります。
勉強は、録画したり後回しにしたりしないことを前提に、すべてその日のうちにやらなければならないのです。
ところが、オンラインの少人数クラスの通信作文教室では、提出率はほぼ100%です。
ほぼというのは、当日特別の事情があって途中で退出する人がいることもあるからです。
オンラインの作文教室では、お互いの予習の発表のあと、その場で作文を書き始めます。
そして、15分から20分ぐらい経ったところで、先生がいったん作文の実習を止めて、どの辺まで書いたか確認しその後読書紹介を始めます。
その15分から20分の実習の時間に、一人ひとりの生徒を別のルームに呼んで、個別に前回の作文の講評を説明します。
だから、毎週の作文の授業で、全員が必ず作文を書く時間があり、その場でどこまで書いたかを確認できるのです。
オンラインの少人数の作文クラスは、まだ生徒数が70名程度で、言葉の通信生徒のごく一部ですから、そのよさがあまり知られていません。
また、まだ参加する生徒数が少ないために、学年が混在しているクラスがあり、生徒どうしの話の弾み具合がやや不足しているところがあります。
しかし、このオンラインクラスで勉強を続けていると、そのクラスの生徒どうしが互いに仲のよい友達のような関係になっていくのです。
このオンラインの少人数クラスの作文通信教育が、これからの子供たちの作文の勉強の主流になっていくと思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
作文は、いったん未提出の週があると、そこからどんどんたまっていきます。
私は、自分のうちの子には、休んで書けなかったようなときに、ほかの日にふりかえて書かせるというようなことは一度もしませんでした。
休んだときは、それはそれで休んだだけでおしまいにするのです。
そして、休まないときは、何が何でもその日のうちに書き上げるのです。
これが作文の勉強を長続きさせるコツです。
オンラインのクラスで、みんなが一斉に作文を書き始めます。
カメラを机上に向けていると、みんなの書いている様子がお互いにわかります。
そうすると、誰も、自分だけサボっているわけにはいきません(笑)。
それで、みんな作文が書けるようになるのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2)