 ホオノキ
ホオノキ
6月の学年別の森リン大賞を紹介しています。
https://www.mori7.com/oka/moririn_seisyo.php
今回は、中1の6月の課題です。
蜩(ひぐらし・かなかな)さんは、ニックネームからもわかるように、動物や植物が好きなのでしょうね。
ベニテングダケについての体験実例が個性的なので、ここで表現語彙の点数が高くなっています。
構成は、複数の理由をしっかり書き、そのあとに具体的な実例を書いています。
中学生の作文は、理由を書かずにすぐに実例を書いてしまう人が多いので、この構成の仕方をよく覚えておきましょう。
結びの「……という名言がある」という表現は、「……という言葉がある」と書くほうが一般的です。
無知であることのよい面というのは、面白い見方ですね。
6月の森リン大賞と上位入賞者(中1の部253人中)
捉われない発想(清書)
蜩
ひとつの美術作品にむかいあうときに、知識が頭の中にたくさんあればあるほど、一点の美術品をすなおに、自分の心のおもむくままに、見ることが困難になってくる。では、われわれは知る必要がないのか、勉強する必要もなく、知識をうる必要もないのか、というふうに問われそうだが、これもまたちがう。そのへんが非常に微妙なのだが、柳宗悦が戒めているのは、知識にがんじがらめにされ、自由で柔軟な感覚を失うな、ということだろう。私は余計な知識があると先入観を持ってしまい、自分の素直な気持ちで、ものを捉えられなくなると思う。
第一の理由に知識のせいで先入観を持ってしまうかもしれないからだ。 私は自然が好きだ。自然であれば、ほとんどのものが好きである。したがって、自然についてはそれなりに知識がついているつもりだ。しかし、その知識が覆ってしまう時もよくある。例えばキノコだ。キノコも、もちろん好きだ。しかし、毒キノコを絶対に生きものは食べないという先入観があった。ある日、テレビでキノコ特集の番組を見ていたときだ。そこにベニテングタケというキノコが出てきた。ベニテングタケはカサが赤色で白い点々があり、いかにも毒キノコというキノコだ。昔からハエトリタケとして利用されてきた猛毒キノコでもある。もちろんどんな動物も食べられない。それが私の先入観だった。しかし、ベニテングタケを食べる動物がいたのである。その動物は鹿だ。私はこれを知ったときは天と地がひっくり返った気分だった。この時、先入観に捉われているのだということを実感した。このように先入観で物事を見ていると、思わぬ事が起きた時に頭が混乱してしまうことがあるのだと思う。
第二の理由に、余計な知識を持たずに先入観を持たないほうが、新しい発想や発見があるからだ。なぜなら、昔は太陽は地球の周りを回っていると思われていた。しかしその常識にとらわれずに研究をした結果、地球が太陽の周りを回っていることが分かったのだ。最近では、高校生の自由研究でセミは大人になって数ヶ月生きているなど、世の中の常識がいつでも覆されているのである。先入観がなければ新しい発想が生まれてくる。私が小さい頃、仲間を線でつなごうというゲームをやっていた時だ。その中で魚とカニを結ばなかったらしい。なぜなら、魚は水の中にいるけれど、カニは陸にもいるからだったそうだ。このように先入観がなければ、さまざまな発想が生まれるのだと思う。
たしかに危険なことや、テストや授業の内容を理解してから取り組んだり、絵や作品などを作者の表現したかったことを予め知っておいてから先入観を持って見るのも、楽しいかもしれない。しかし「行動するためには、多くのことに無知でならなければならない。」という名言があるように、新しい発想を得たかったり、自分の思ったことで感じたい時には一度裸の心で向き合ってみるべきである。したがって余計な知識をつけずにものと向き合うことが大切である。先入観のない柔軟な人間になりたいものである。
知識語彙
69点
| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
|---|
| 1位 | ●捉われない発想(清書) | 蜩 | 88 | 1250 | 68 | 69 | 79 | 89 |
| 2位 | ●知識にとらわれず | あおはす | 87 | 1286 | 64 | 72 | 78 | 84 |
| 3位 | ●比喩の使い道 | あうさの | 85 | 1136 | 57 | 64 | 78 | 84 |
| 4位 | ●面~見テ 知リソ 知リテ ナ見ソ~ | あおふね | 85 | 1100 | 51 | 76 | 73 | 89 |
| 5位 | ●学習の仕方 | りんたろう | 84 | 1186 | 56 | 68 | 67 | 87 |
| 6位 | ●比喩の大切さ | かののん | 83 | 1016 | 52 | 67 | 75 | 90 |
| 7位 | ●とらわれないで! | あおさみ | 83 | 1461 | 52 | 58 | 71 | 83 |
| 8位 | ●比喩を使って表現する | あかさと | 82 | 1047 | 61 | 59 | 72 | 90 |
| 9位 | ●比喩って面白い? | あうるか | 79 | 915 | 44 | 66 | 65 | 96 |
| 10位 | ●先生という存在について | らーゆ | 78 | 1430 | 42 | 69 | 77 | 90 |
 ハギ
ハギ
2016年に発行された「小学校最初の3年間で本当にさせたい『勉強』」が第9刷になりました。
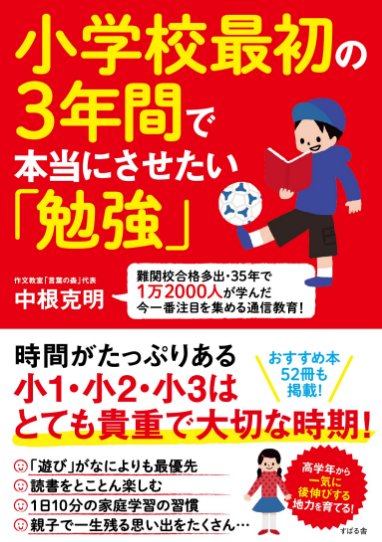
また、2020年に発行された「小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと」が第6刷になりました。
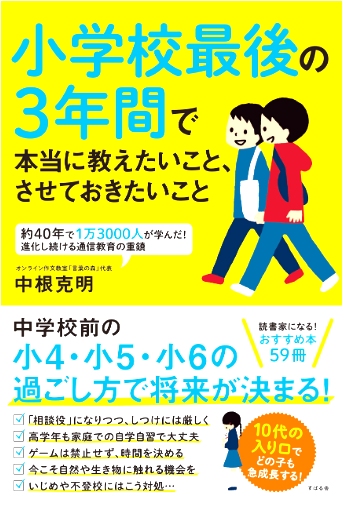
みなさん、ありがとうございました。
いずれの本も、今見ても内容的に古いところはありません。
子育ての基本は、昔から変わっていません。
さかのぼれば、貝原益軒の「和俗童子訓」のころから、子育ての基本は共通しています。
「
中学生になる前に、勉強に取り組む姿勢を作る」
(2015/11/04の記事)より引用
====
貝原益軒が81歳のときに著した教育論「和俗童子訓」では、「予(あらかじ)め」という考え方が中心になっています。問題が生まれてから対策を考えるのではなく、問題が生まれる前に対策を立てて実行しておくという考えです。
これは、中学生の勉強にもあてはまります。
中学生になる前、つまり小学生のまだ親の言うことをよく聞く時期に、親が指図して勉強をさせることだけに力を入れるのではなく、子供の自覚を促す勉強の仕方に力を入れるのです。
小中学生の勉強は、難しいと言ってもたかが知れています。特に小4までの勉強は、やれば誰でもできるようになる簡単な勉強です。この時期の勉強でよい点を取るようなことはどうでもいいことです。
だから、よい点を取ることに力を入れるのではなく、何のために勉強するのかという勉強に取り組む姿勢を伝えることに力を入れていくのです。
そのためには,例えばテストなどでも、点数を見るのではなく、その点数の中身を見ることです。
ひとつの例として言えば、次のようなことです。
子供がテストを見せて、「このテストの最後の方は、時間がないから適当に選んだら○になって百点になった」などと言ったとき(まれな例ですが)、親は、「それは、よかったね」などと言うのではなく、穏やかに次のように言うのです。
「勉強は、自分自身を向上させるためにやるのだから、時間がなかったりわからなかったりしたら、答えを適当に書かずに、ちゃんと×にしてもらうんだよ。悪い点数を取った方が自分のためになるんだからね」
こういう一言が、子供が中学生になったときに生きてくるのです。
====
今、言葉の森は、オンライン小人数クラスという新しい教育に取り組んでいます。
これが、言葉の森の「予め」の教育です。
オンライン小人数クラスの教育の中身は、作文、創造発表、プログラミングという、従来の教育では見落とされていた主体的・創造的な学力を伸ばす学習が中心です。
国語読解、算数数学、英語の教育は、自主学習の力を伸ばす教育です。
最近、探究学習という言葉が盛んになりましたが、言葉の森が昔から作文教育や創造発表教育で行っていたことは、その探究学習の先取りだったと言ってもいいと思います。
しかし、言葉の森の教育は、単なる探究学習ではありません。
オンライン少人数クラスの教育は、対面式の集団指導教育とも、単なる個別指導教育とも、動画配信の教育とも違います。
これからの教育で大事なことは、少人数の友達や先生とのコミュニティの中で学ぶということです。
だから、オンラインクラスでは、発表と対話の時間を授業の中に取り入れています。
こういう教育は、5人以内の少人数のクラスでなければできません。
単に知識を能率よく詰め込む教育ではなく、また、単に思考力と創造力を伸ばすだけの教育ではなく、そこにもうひとつ共感力を育てる教育ということが大事になってきます。
それは、なぜかというと、人間の生きる目的は、幸福、向上、創造、貢献だからです。
教育も、大きくは、その人間の生きる目的に沿ったものとして考えていく必要があるのです。