■受験作文の勉強法は、出題傾向に合わせた課題で10本書くこと
受験の作文では、誰もが不安になります。
それは、対策が立てられないと思うからです。
一般の入試では、準備ができていれば、大体の偏差値は予測できます。
しかし、受験作文の場合は、模擬試験の偏差値は、あてになりません。
作文の対策は、志望校の過去問の傾向を調べ、傾向に合わせた作文を10本書いておくことです。
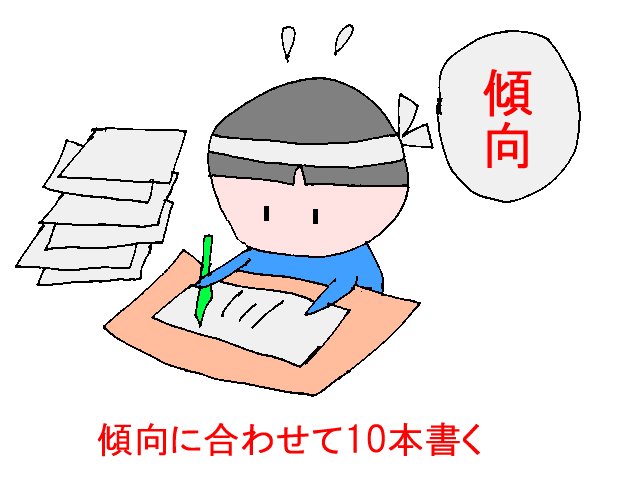 ■受験する学校の作文試験の過去問の傾向を知ることが出発点
■受験する学校の作文試験の過去問の傾向を知ることが出発点
受験勉強の鉄則は、志望校の傾向を知ることです。
国語の試験でも、難しい傾向か易しい傾向の学校かで対応が違います。難しい傾向の学校については、難しく考えて解かなければなりません。易しい学校の国語の試験では、普通に解くことが大事になります。
出題傾向の分野を準備しておくことが大切です。
作文試験の場合は、その傾向がさらにはっきりしてきます。
だから、過去問分析が大事になるのです。
 ■作文試験は、内容よりも、まず時間内に必要な字数を書く力をつけること
■作文試験は、内容よりも、まず時間内に必要な字数を書く力をつけること
作文試験では、指定の字数と時間に合わせた対策をしておくことが大事です。
作文試験の基本は、決められた制限時間内に必要な字数ぴったりに収める力をつけることです。
できるだけ、指定の字数の上限ぎりぎりまで書くことです。
時間内に必要な時数をまとめる力をつけるためには、練習量しかありません。
しかし、練習を重ねれば、誰でもできるようになります。
 ■特殊な学部の試験なら、その分野の本を10冊読んでおく
■特殊な学部の試験なら、その分野の本を10冊読んでおく
音楽系、芸術系、工学系、医療系などの分野では、特にその分野の知識を身につけておくことが必要です。
図書館や書店などで、受験する分野の本を10冊読み、その中で印象に残った本は繰り返し読み自分の血肉にしていきましょう。
数字や固有名詞などのデータを覚えておけば、面接試験のときにも役に立ちます。
 ■作文試験はその場で考えて書くのではなく、それまでに書いた文章を当てはめて書く
■作文試験はその場で考えて書くのではなく、それまでに書いた文章を当てはめて書く
作文試験は、その場で最初から考えて書くのではなく、課題のテーマに合わせて、自分がこれまで書いてきた文章の内容を当てはめて書いていきます。
だから、事前に、出そうな課題について10本の作文を書いておくことが大事なのです。
しかし、自分が予想してもいなかった課題が出たら、それは逆にチャンスです。書きにくい課題ほど、構成力が重要になるからです。
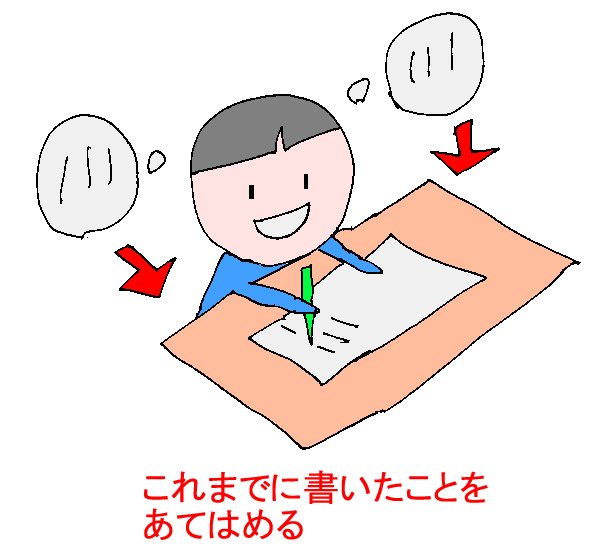 ■書き出しと結びが対応していて、題材に個性があり、結びに光る表現があれば合格作文になる
■書き出しと結びが対応していて、題材に個性があり、結びに光る表現があれば合格作文になる
作文試験の採点官は、内容までじっくり読んでいるわけではありません。
文章は、内容よりも、スムーズにわかりやすく筋道を立てて書いてあることが大事です。
さらにその上に、書き出しの意見と結びの意見が対応していて、題材に個性があり、結びに光る表現があれば、合格作品になります。
これは、練習次第で誰でもできるようになるのです。
 ■作文クラスの無料体験学習ができます
■作文クラスの無料体験学習ができます
作文クラスは、小1から高3まで、平日及び土日の7:00から20:00まで参加できるクラスがあります。
無料体験学習を希望される方は、お電話、又は、ホームページからお申し込みください。
045-353-9061(平日10:00~17:00、土日10:00~12:00)

受験作文で43年の実績
▼これまでの合格情報
https://www.mori7.com/beb_category.php?id=19
▼受験作文の過去問の解説
https://www.mori7.com/juken/juken_iwa.php
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 受験勉強の仕方(0)
 ニワゼキショウ
ニワゼキショウ
若者は、世の中に出ることが目標です。
社会に貢献することは将来の目標ですが、その前に、まず自分が世の中に出ることです。
そのための道はいくつかあります。
大きく分けると、エリート、スター、ヒーローです。
エリートは、既存の組織で上の人に引き立てられて、自分も少しずつ上に行く道です。
安心できる道ですが、時間がかかります。
スターは、みんなの人気に支えられて一気に上に行く道です。
短期間で頂点に立つこともありますが、その頂点を支えているのは、大衆の人気というあてのないものです。
年齢を重ねても、人気を蓄積することはできません。
ヒーローは、自分の力で世の中に出る道です。
不確かな選択ですが、その苦労が自分を成長させます。
そして、いろいろな失敗や成功があっても、結局、時間がたつほど、自分の中に蓄積が生まれます。
だから、若者は、ヒーローを目指すべきです。
苦しいのは、最初のうちだけです。
その苦しいのを、楽しい苦労だと思ってがんばればいいのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41)
 チガヤ
チガヤ
子供が本を読んでいれば、お母さんお父さんは安心するかもしれませんが、その本の中身が大事です。
小学校低学年の子で、いつまでも絵本のような本を読んでいる子がいます。
ほのぼのとした内容で、いい本なのですが、それだけで終わっていては、読書力はつきません。
小学校低学年の子は、字の多い本を読む必要があるのです。
小学校高学年や中学生、高校生で、いつまでも物語文の本を読んでいる子がいます。
物語文は、楽しく面白く読めますが、それだけで終わっていては、思考力はつきません。
小学校高学年以上の子は、説明文、意見文の本を読む必要があるのです。
ところが、説明文、意見文の本を読むと、途端に読書量が低下する子がいます。
その理由のひとつは、読む力がついていないからです。
もうひとつは、読み方のコツを知らないからです。
物語文は、ストーリーに引っ張られて最初から最後まで読むことができます。
しかし、説明文、意見文は、ストーリーがないので、途中で読むことに飽きると、そこで止まってしまうことが多いのです。
説明文意見文の読書で大事なことは、面白くないところは飛ばし読みをして、面白いところだけを読むことです。
そして、できるだけ、いいと思ったところに傍線を引いて読むことです。
しかし、漠然と飛ばし読みをすると、どこまで読んだかわからなくなるので、結局最後まで読み切ることができなくなります。
付箋読書という方法は、説明文意見文の本を読むのに役立ちます。
この方法で読めば、複数の本を並行して読むことができます。
また、読みかけでしばらく読まなかった本でも、すぐに再開することができます。
▽「付箋読書の仕方」
https://www.mori7.com/as/1367.html
しかし、私は、いくらこういうことを説明しても、やる子はほとんどいないだろうという気がします。
人間は、習慣をなかなか変えられないからです。
例えば、話は変わりますが、玄関では靴をそろえて脱ぐということや、席を立つときは椅子をしまって立つというようなことは、簡単なように見えますが、定着させるのに子供でも1年近くかかります。
大人は、たぶん、ほぼできません(笑)。
そこで、将来的に考えているのは、読書クラスです。
難読クラスと言ってもいいと思います。
難読検定とセットにする予定です。
そのクラスでは、学年相応の難しい本をばりばり読んで、読んだあと、みんなでディスカッションをするのです。
ただ、そのための読書のリストを作るのに時間がかかるので、スタートは少し先になります。
いい本でも絶版になることがあるので、kindle化された本が中心になります。
そのうち、本のリストを作るための研究会を立ち上げたいと思っています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)
 オルレア
オルレア
これは、面白い本なので、小学校高学年から中学生や高校生の子供たちにおすすめです。
もちろん、保護者の方にもおすすめです。
「
空想教室」
私の感想は、「もうこんな本が出てきたんだなあ」ということです。
私は、昔から、ずっと人間の勉強の目的は、独立して自分らしく生きることにあると思ってきました。
ただ、そういうことを言っても理解してくれる人はいないだろうとも思っていました。
しかし、時代は、少しずつ変化しています。
言葉の森は、受験対策もしています。
特に、作文小論文試験では、毎年多くの子が参加し、志望校に合格しています。
しかし、大学入試に合格することは、その先の長い人生を考えたらどうでもいいことです。
確かに、今の会社の就職試験は、大学の名前で学生を評価しています。
だから、いい大学に入っていれば、とりあえず安心です。
しかし、これからは、就職は、人生の到達点ではなくなります。
人間は、一生、自分らしい人生を創造して生きていくのです。
このことは、なるべく若いうちに気づいておくことが大事だと思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)