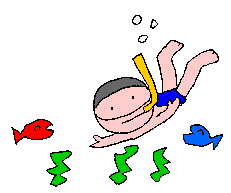
素読の反復による学習効果は歴史的にすでに実証されています。
しかし、理論的な裏付けがないので、音読や暗唱は、形式的、権威主義的なものになりがちでした。例えば、四書五経、憲法前文、平家物語、寿限無、枕草子などの暗唱は文化的な暗唱であって、決して教育的な暗唱ではありません。なぜならば、その暗唱によってどういう力がつくかということが明らかになっていないからです。
暗唱については、二つの理論が考えられます。
第一は、左脳の言語処理機構に流入する言語情報の多様性が増すことです。通常の文章の読み方では、入力される言葉は、目で見える範囲の数語のつながりだけです。ところが、暗唱では、目に見えないところから言葉を持ってくるのでその言葉が持つ意味の広がりが増えるのです。暗唱で入力される言葉は、主にイメージやメロディーを処理する右脳からやってくるので、言葉の持つ多様な意味がそのまま言語処理機構に流入してきます。このため、暗唱を続けていると発想が豊かになるのです。
第二は、同じ文章を反復することによって、神経細胞に入る情報が重複する機会が増えることです。重複した情報は強化されるので、反復によって定着度が高まります。これが、反復すればだれでもできるようになるという暗唱の方法論を支えています。
また、暗唱を繰り返していると、入力される情報が重複するだけでなく、ある神経細胞に情報が入力される直前にその神経細胞が発火するという状態が生じます。このことによって、入力情報を受け取る受容センサー自体が強化されます。この結果、短い文章を何度も反復することによって、物事の理解力そのものが高まるのです。
しかし、短い文章を単に覚える目的を超えて反復し続けるという勉強は、現代の社会では子供たちが飽きて実行することができません。そこで、言葉の森では、10分間で簡単にできる300字暗唱を進めつつ、記憶術のノウハウを身につける練習も兼ねてその300字暗唱を900字暗唱につなげていくというような勉強の仕方を考えています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)
7月下旬に、サーバーの文字コードをEUC-JPからUTF-8に変更しました。
その際、HPの検索機能のところだけ、EUC-JPのまま残っていたようです。
先ほど検索してみて、検索機能が使えないことに気がつきました。
今直しました。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19) 質問と意見(39)
中1の保護者の方から、「国語の問題の解き方を直接説明してもらえるか」というご質問をいただきました。
以下は、そのご質問に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。
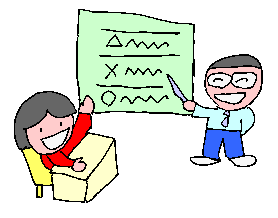
国語の選択問題は、その子のまちがえたところを中心になぜその答えではないかを説明すると急速に力がつきます。
学校や塾でも、そういう説明の仕方ができる先生がいると思います。全員に共通の問題を説明するならば、そういう一斉指導でもできます。
しかし、いちばんいいのは、家庭で父親か母親が実際に問題を解きながら、その消去法の考え方を説明することです。なぜかというと、実際に模擬試験などの問題を解きながら説明すると1時間ぐらいかかるからです。
その際、親が理詰めで説明できない問題は、もともと解けなくてもいい問題だと割り切っておくことが大切です。
大事なことは、子供がそういう発想で問題を解くのだと理解することですから、必ずしも全部が全部できなくてもいいのです。
この消去法の発想は、下記のページなどをごらんください。。
センター試験の解き方1/
2この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語問題(15) 質問と意見(39)
中1の保護者の方から、「暗唱をしないと力がつかないか」というご質問をいただきました。
以下は、そのご質問に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。
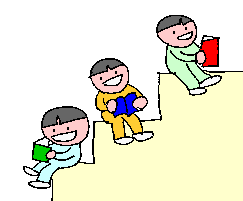
暗唱をしなくても力はつきます。
しかし、どのような勉強もそうですが、学力はかけた時間に比例するところがあります。
特に、作文力と国語力は、読む量と質に関係が深いので、音読や暗唱や読書の時間をとればそれだけ学力がついていきます。
以前は、長文の音読ということでやっていましたが、音読だけではチェックが不十分になるので、今は暗唱にしています。
しかし、中学生のころになると、これまで何かを暗唱するという勉強をしていない人がほとんどなので、この新しい勉強の仕方にとまどうようです。
やりにくい勉強を無理にやるよりも、あまり抵抗なくできる勉強を中心にして実力をつけ、余裕ができてから新しい形の勉強に取り組むということでもいいと思います。
中学生でいちばん抵抗なくできる勉強は、読書又は問題集読書ですから、まず読む時間を確保するというところから始めるようにしてください。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 質問と意見(39)
中1の保護者の方から、「作文を書くときの時間がかなりかかっているが」というご意見をいただきました。
以下は、そのご意見に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。
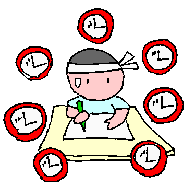
作文を書く時間は、中高生以上になると、一般にかなりかかります。社会人になると、毎回3時間ぐらいになる人もかなりいます。
それだけよく考えているからだとも言えますが、やはり書くことにまだ慣れていないために時間がかかるというのがいちばんの原因です。
中高生は、1200字に1時間半ぐらいかかるのが普通です。
しかし、試験などのことを考えると、1200字60分以内を目標に書く力をつけておくといいと思います。
早く書くコツは、
1、早く書くことが大事なのだと自覚し、そう心がける(作文は、納得いくまで時間をかけてじっくり書くのがいいのだと考える人が多い)
2、1200字の作文を、長くても90分以内、できるだけ60分以内で書くことを目標にする(題名を書いてから全文を書き終わるまでの時間。メモなどの時間はいれずに)
3、消しゴムを極力使わない、パソコンの場合もできるだけ書き直さない、書いている途中で考えたり読み返したり調べたりしない(考えたり読み返したりするのは、最後の仕上げの段階で)
4、構成図で、最初に全体を考える。作文を書いている間に書くことに詰まったら、構成図に戻って書き続ける
すぐにはできないと思いますが、取り組む気持ち次第でかなり時間は違ってきます。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 質問と意見(39)
中2の保護者の方から、「振替のときの先生の説明がよくわからなかった」というご意見をいただきました。
以下は、そのご意見に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。
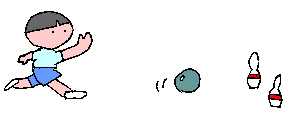
振替の先生は、そのときに指導のできる講師があたることになっています。
振替の先生は、その生徒のこれまでの指導の流れを見て、その週の課題の項目をひととおり全部説明します。
しかし、その生徒の普段の実情を知っているわけではないので、説明が不十分に感じられたことがあるのかもしれません。
書いている途中でも、もう少し説明を聞きたいというときは、教室にお電話ください。追加のピンポイントの説明をいたします。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。質問と意見(39)
中2の保護者の方から、「先生と生徒が電話でどのような話をしているかわからない」というご意見をいただきました。
以下は、そのご意見に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。
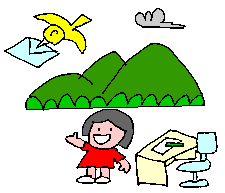
中学生ですと、本人が自分だけで勉強していくので、保護者の方が不安に思われる場合があります。
先生の指導内容は、インターネットの「山のたより」で見られますから、それを参考にしてください。
また、必要に応じて保護者と先生との連絡がとれるようなブログ的なものを今考えているところです。
電話指導の内容は、大体7~8分のことが多いと思います。
内容は、前回の作文の講評が少しで、今回の作文の指導が大部分です。指導が早めに終わったときは、近況などを聞くこともあります。
電話指導は勉強のきっかけ作りという面が強く、勉強の内容は、本人が解説やヒントなどを参考に自分で苦労して書いていくことそのものの中にあると考えています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。質問と意見(39)