
小学1、2年生のころは、勉強する内容も簡単で、子供が親や先生の言うことをよく聞く時期ですから、ついいろいろなことを教えたくなります。
しかし、ここで、親のペースで勉強させると、子供はそのときは楽しくやっているように見えますが、内心は親にコントロールされている自分に肯定的な感情を持てなくなります。
人間は誰でも自分の意思で自由に行動したいと思っています。人に言われたとおりにやることが好きな人はいません。しかし、「教える―教えられる」という関係ができあがると、言われたとおりにやることが正しいことなのだと自分に言い聞かせてやり続けるようになります。
こういうやり方が限界に来るのが、小学4年生ごろからです。このころになると自立心が育ってくるので、親に言われたとおりにやることに反発するようになるのです。
本当は、小学5年生以降の勉強が難しくなる時期に、親と協力して勉強することが大事なのですが、低学年のときに親の言うとおりにやってきた子は、高学年になってから親とうまく協力することができなくなります。
すると、親は子供の勉強を見ることができなくなり、その結果、学習塾などに勉強を任せるようになり、ますます子供の勉強に関与できなくなり、ただ点数の上でしか子供の勉強の実態がわからないという状態になるのです。
こうならないためには、低学年のころから、子供が自主的に勉強する環境を作っておくことです。そのためには、親が手取り足取り勉強の内容を指示するのではなく、あらかじめやるべきことを、子供が無理なくできる範囲に絞って決めておき、子供が毎日の習慣としてその勉強をするのを、横で静かに見守るという接し方が必要になります。
低学年のころは、親が無関心でいると意欲が低下するので、見守ることは大事なのですが、できるだけ口出しをしないようにする必要があります。
そして、注意はできるだけ少なくし、よくできたときに褒めるという接し方をすることによって、子供は自主的に勉強する姿勢を身につけていきます。
褒めるというのは、必ずしも直接褒めることに限りません。例えば、本をよく読んでいたら、「○○ちゃんは、本を読むの好きなんだね」というその行動を認めてあげるだけでいいのです。
しかし、自主的な勉強と褒め言葉だけでは、時に子供がさぼったり、ずるをしたりする場面も出てきます。こういうことができるのも、人間に自主性があるからなのですが、それをそのままにしておくと、あとで修正するのが難しくなります。
こういう場面で登場するのは、やはり父親です。
特に男の子は、知っていて悪いことをするということがよくあります。それは、ある意味で、自分がどこまでやると叱られるか試している面もあるのです。
母親は、そういうときの注意は苦手です。母親の注意は、愚痴のような小言になることが多く、子供を叱るというパワーに欠けることが多いのです。
叱り方の原則は、厳しく短く一度だけです。何度も同じことを言うような叱り方では、叱られることに免疫ができてしまい、ますます何度も言わないと言うことを聞かないというようになります。
母親の役割の中心は、叱ることではなく、優しく認めてあげることです。
その分、父親が厳しい叱り方の役割を分担する必要があります。しかし、それは、父親が憎まれ役を買うというのではありません。厳しく一度だけ叱って、あとを引かない父を、子供は尊敬するからです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
母親は、手芸のように細かいことをきちんとやるのが得意です。
しかし、それを子供の教育でそのままやってしまうと、子供の自主性が育たなくなることがあります。
子育てで大事なことは、親がきちんとやることではなく、子供が自分でやるように仕向けることです。
そうすると、きちんとやれないことも出てきます。しかし、そのきちんとやれないことも含めて子供が自分の力でやることが大事なのです。
一方、父親は一般的に、手芸や料理のように細かいことが苦手です。
晩酌のつまみなども、ひとりのときは、冷蔵庫にあるニンジンに味噌をつけてそのままボリボリかじったりします。(おまえだけだろ)
しかし、そのきちんとしない分、肝心なときに子供の前に登場することができるのです。
ウルトラマンみたいです。
(写真は、9月30日の朝の太陽)
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 勉強の仕方(119)

小学2年生は、字数に燃える学年です。
1年生のころはまだ指の力が弱くて、長く書くことができなかった子が、2年生になるとだんだん長く書けるようになってきます。
すると、その長く書けることがうれしいので、ひたすら長く書くことを目標にするようになります。
これは、これでいいことです。人間は、自分が成長しているところを伸ばすのが好きですから、字数が長く書けるようになってきたら、その字数をもっと伸ばしたくなるというのは自然の感情です。
しかし、字数を長く書くのに関心が向く分、字が雑になったり、細かい表記ミスが出てくるようになります。
このときに、「字数だけ長くてもダメ。もっと○○でないと」などと言ってはいけません。
褒め言葉は、本人ががんばっているところに向けて言うのが原則です。だからそれほど難しくはありません。
しかし、注意の言葉は、本人が意識していないところで言ってしまうことが多いので、それが作文の苦手な子を作ってしまうことがあるからです。
字数の長さに燃えているのであれば、ただそこを褒めているだけでよくて、その字数以外の注意は言う必要ありません。
もし、注意をするとしたら、それは事後的な注意ではなく、作文を始める前に、「今日は、こういうことに気をつけて書くんだよ」と事前に言っておくことです。
字数の長さを褒めるだけで、なぜ細かい表記の注意はしなくてよいかというと、字数に燃える時期は小2の間だけで、小3になると自然に字数の長さへのこだわりを卒業するようになるからです。
小3になると、字数よりも、表現の工夫や内容の面白さなどに関心が向いてきます。すると、字数は自然に短くなります。
小2のころよりも字数が少なくなるので、手を抜いているように思うかもしれませんが、この字数が短くなってきたことが進歩なのです。
では、なぜ小2のころ長く書けるのかというと、小2までは、自分の言葉で書いているわけではないからです。
本をよく読む子は、読んだ本の文章がのリズム感がそのまま頭に残っています。だから、自分で考えて書くのではなく、本の文章のリズムをそのまま自分が書こうとしている事実に結びつけて写しているだけなのです。
読書の好きな子は、小2のころに大人も顔負けの達者な表現で作文を書くことがあります。そういう文章が書けるのもやはり、自分で考えて書いているわけではないからです。
ところが、小3になると、自分の言葉で作文を書くようになります。すると、小2のころよりも、字数も短くなるし、表現もつたなくなることが多いのです。
言葉の森では、生徒によく、「上手に書けたものがあったら応募するといいよ」と言っています。
しかし、コンクールなどの応募の適齢期は、小3から小4にかけてです。なぜかというと、この時期は、本人も上手に書くことを意識できる時期で、また作文の題剤も書きやすいものが多いからです。
小5以降になると、課題が難しくなるので、上手な作文は書きにくくなります。しかし、もちろん小5以降、小6も中高生も、自信のある人はどんどんコンクールに応募しておくといいのです。
小2以下は、コンクールへの応募はおすすめしません。その理由は、どこかに応募したいという意識が本人にまだないからです。
また、応募するとなれば、いろいろ書き直すところが出てきます。もともと自分の意思で応募したいと思っているわけではないところに、細かい書き直しがあるわけですから、作文というのは大変だという気持ちを持ってしまうことが多いのです。
小2までの生徒のいちばんの喜びは、身近なお母さんやお父さんや先生が、自分の作文に関心を持って温かい言葉をかけてくれることです。
コンクールに入選するとか、ご褒美の賞品があるとかいうことは、この時期の子供たちの本当の喜びではないのです。
言葉の森では、小1と小2の作文の重点目標は、「楽しく書くこと」としています。
この時期に、たっぷり楽しく書いていくことが、その後の作文の勉強の土台となるのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 小学校低学年(79)

子供たちが書く作文は、学年によって大きな違いがあります。
小学校1年生は、まだ文章を書くこと自体に慣れていないので、「わ」と「は」の区別や、会話にかぎかっこをつけることや、文の終わりに「。」をつけることなどができません。
それは、当然です。普段の会話の中で、「こんにちは」の「は」の部分を「は」と言う人はいません。誰もが「わ」と言うので、文に書くときにも自然に、「こんにちわ」と書くのです。
同じく、会話のカギカッコや句読点も、会話の中には出てきません。だから、それはできなくてあたりまえなのです。
なぜ小1でこのような話し言葉と書き言葉の区別の問題が出てくるかというと、日本では小1で作文が書けるからなのです。
世界にはいろいろな言語がありますが、小1で作文が書ける言語というのは日本語だけだと思います。
日本語は一音と一語がほぼ同じように対応しています。欧米などの言語は、話し言葉から書き言葉の文字列を連想することはできません。だから、日本語では、小学校1年生で作文が書けてしまうのです。
ここで微妙な問題が起こってきます。
小1の作文の勉強の目標は、「楽しく書くこと」です。小1のころに作文を楽しく書いている子は、学年が上がっても作文に対する肯定的な印象が続くので、難しい課題になっても書き続けることができます。
だから、この時期の作文は特に、書いたことをそのまま認めてたくさん褒めてあげるといいのです。
ところが、「わたしわおとおさんとうみえいきました」などという文をそのまま褒めるということはなかなかできません。
かと言って、表記のミスに赤ペンを入れていちいと直していたのでは、すぐに書くことが嫌いになってしまいます。
小1の作文は、こういう問題が出てくるのです。
この問題の解決策は、書くことよりも読むことに力を入れることです。
なぜなら、書かれた文章には、「わ」と「は」の区別も、カギカッコも、句読点も、目に見える形で出てくるからです。
この読む練習が少ないまま、作文の書き方を直すと、何度同じことを注意しても直りません。カギカッコなどは何ヶ月言い続けても直りません。
だから、表記のミスがなかなか直らない子は、注意をするのではなく、読む力をつけることが先決なのです。
小1で、まだ表記のミスが多い生徒に、作文を書く練習を続けながら、読む力をつける方法が、幼児作文コースです。
それは、お母さんが子供と話をしながら構成図を書き、子供が絵をかき、お母さんが作文を書くという方法です。
子供は、親のやることを真似したがります。
親が読書をしている姿を見ている子は、自然に本好きになります。同じように、親が文章を書くのを見ている子は、自然に作文好きになります。
「本を読みなさい」とか「作文を書きなさい」とか強制するのではないのです。何も言わなくても、本を読んだり作文を書いたりしたくなるのです。
幼児作文コースでは、お母さん又はお父さんが書いた、親子合作の作文を見ているうちに、子供は自然に表記の仕方を頭に入れます。
正しい表記を何度も見ている子は、表記を直すときでも一度の注意ですぐに身につきます。
一度の注意で直らないときは、まだ読む量が少ないというだけなのです。
読む力が書く力の土台となっているというのは、小学1年生の時期だけではありません。
小6になると、作文の主題に抽象的な概念を盛り込むことが求められるようになります。難しい本を読んでいない子は、そういう語彙がありません。
中学生でも、高校生でも、その学年に必要が語彙のレベルは、常に読む力に引っ張られる形で書き言葉に現れてきます。だから、毎日の音読という自習が、作文の勉強の基礎になっているのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
小1の作文の目標は、楽しく書くことです。
しかし、小1のころは表記のミスが多いので、正しい書き方も身につけなければなりません。
ところが、普通に作文を書いていたのでは、この「楽しく書く」と「正しく書く」は両立しないのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 親子作文コース(9)

テレビゲームばかりしていて勉強をしないという子がいると思います。
同じように、昔は、マンガばかり読んで、ちゃんとした本を読まないという子がいました。
しかし、悪いのはテレビゲームでもマンガでもありません。
勉強をしっかりしてテレビゲームを楽しむ子もいます。読書をしっかりしてマンガも楽しむという子がいます。
問題なのは、勉強をしないとか読書をしないとかいうことであって、テレビゲームやマンガそのものではないのです。
だから、子供のときからテレビゲームを禁止するということは、あまりいいやり方ではありません。それでは、誘惑のある娯楽に対する免疫が弱くなるからです。
テレビゲームの時間を守る約束をして、約束が守れなかったらテレビゲームを捨てるということを主張する人もいます。
しかし、そういうやり方をすること自体が、もう手遅れです。
ここでも問題は、テレビゲームの時間を守れないことではなく、テレビゲームの時間を自分で守る練習をしてこなかったことにあります。
そういう練習は、小学校中学年以上になってテレビゲームの楽しさがわかってからでは遅いのです。子供がまだ小学校低学年で、テレビゲームなどにあまり興味を持たない時期から、時間を守るという練習をしておく必要があります。
これは、テレビの視聴などでも同じです。
子供がテレビ好きになってから、時間を決めて見るような約束をしても、なかなか守らせることはできません。
子供がテレビなどにそれほど興味を持たない時期に、時間を決めて見る練習をしておくのです。
そのときのやり方は、禁止や命令ではなく、子供の自主性を生かす形をとる必要があります。
子供が小学校低学年のころは、誰でも親の言うことを素直に聞きます。その素直に聞く時期に、命令のような形で一方的に何かをさせると、子供の自律心が育ちません。
子供の自主性を生かす形にすると、最初は必ず守れない場面が出てきます。そのために、叱ることが出てきます。この小さな叱責が大事なのです。
逆にうまく守れる場面も出てきます。そのときの小さな賞賛もまた大事です。
この小さな叱責と小さな賞賛を繰り返す中で、自然に自分で自分をコントロールすることができるようになります。
こういうことができていないと、大きくなってから、大きく叱るようになるのです。それが、「約束を守れなかったらゲーム機を捨てる」というような叱り方です。
この躾面で言えることが、勉強面でも同じように言えます。
小学校低学年のころの勉強の内容は簡単です。そして、子供は、親がやれと言ったことは素直にやります。
この時期に、自主的な勉強の仕方を身につけておけば、大きくなってからでも自分で勉強することができるようになります。
しかし、この時期にやらされる勉強をさせてしまうと、そのときはよくても、将来自分で勉強する習慣が育たないのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
小学校1年生のころは、誰でも親の言うことをよく聞きます。 その時期に、親が命令によって子供に言うことをか聞かせると、子供の自律心が育ちません。 簡単に言うことを聞く時期にこそ、子供の自主性を生かしていくことが大事です。 例えばテレビゲームの時間なども、親が簡単に、「はい。時間になったからおしまいね。ブチッ」などとやっていると、かえって時間を決めてゲームをするという自律心が育ちません。 親が一方的に言うことを聞かせられる時期にこそ、「自分で時間を決めてやるようにしようね」と優しく教えていく必要があるのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

作文の勉強には時間がかかります。
特に小学校高学年から中高生の生徒でしっかりと書く子は、大体1時間半ぐらいかけて書きます。
そして、1200字ぐらいの文章を一つ書き終えると、そのあとすぐに何か勉強的なことをするということはなかなかできません。
よく、15分ぐらいで作文を書いて、そのあと30分ぐらい算数の勉強をして、そのあと漢字の練習を10分して、などと予定を立てたくなりますが、作文はそういう細切れの勉強の中にはうまく収まりません。
作文指導の方法の中には、穴埋め方式で短文を作るような練習をするところがありますが、それはただ穴埋め方式の短文を書いているだけで、その練習をいくらやっても作文力がつくわけではありません。
作文力は、ひとまとまりの文章を書く中で身につくのです。
また、1ヶ月に1回か2回作文を書いて、それで作文の練習をしたことにするところもありますが、作文の勉強の理想は毎日何かを書くことです。少なくとも1週間に1回はまとまった文章を書く時間を取る必要があります。
作文の勉強は、心理的な負担の大きい勉強です。
時間が来て机に向かってすぐに書き出すような子はあまりいません。しばらくは、作文以外のほかのことをして、そのうちに心の態勢が整ってからおもむろに書き始めるという始め方をする子がほとんどです。
特に、学年が上になるほどそういう心理的な負担は大きくなるようです。
言葉の森の通信は、先生からの電話指導があるので、その電話をきっかけに書く気持ちがまとまりますが、そういうきっかけがないと、自分で予定を立てて作文の勉強を始めるというのはかなり難しいと思います。
さて、こういう続けにくい作文の勉強を続けやすくするには、いくつかの条件が必要です。
その第一は、読む力をつけることです。
音読(精読)と読書(多読)によって読む力をつけることで、作文力もつき、書くことが楽になってきます。
第二は、いつもよいところを見て褒めてあげることです。
書いたあとに、欠点を指摘し、悪いところを直して上手にさせようとすると、一時的には欠点は直りますが、その後作文の勉強は続かなくなります。
あらゆる習い事や勉強は、続けることで上達します。作文の勉強もまず続けることを第一に考えていくことです。
第三は、事前の準備です。
小学3年生以上の課題は、題名が決まっている作文と、長文を読んでから書く感想文の2種類で作られています。
題名課題のときは、家族に似た話を取材してくるようにします。感想文のときは、その長文の内容を家族に説明した上でやはり似た例を取材してくるようにします。
作文でも感想文でも、材料があれば書きやすくなります。その材料を集めておくのが事前の準備です。
これは、自由な題名の小学1、2年生でも同じです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
作文の勉強とは、ほかの勉強と比べてかなり負担の大きい勉強です。
小学校低中学年のころはそれほどでもありませんが、高学年や中高生になると、書くことにかなりエネルギーを使うようになります。
その証拠に、小学生の学年別の平均字数を見ると、小4あたりがピークで、小5、小6になると、かえって書ける字数が低下してくるのです。
それは、書く内容に考える要素が出てくるからです。
お母さん方の中には、「ほら、作文なんてさっさと書いちゃいなさい」と言う人がいますが(笑)、小学校高学年以上の生徒にとっては、なかなかそういうわけにはいかないのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 作文の書き方(108)

受験の主要科目は、国、数、英です。
この中で、最も差がつきにくいのが国語です。というのは、国語は全くできない人でもそこそこの点数を取ることができる代わりに、よくできるからと言って満点を取ることは難しい科目だからです。
これに対して、数学と英語は、勉強力の差がはっきり出ます。特に、数学は大きい問題ができるかできないかで全体の点数が大きく変わってきます。だから、受験を左右するのは、数学と英語なのです。
では、なぜ数学と英語は、勉強力の差が出るのでしょう。それは、問題作成に人工的な要素が盛り込めるので、さまざまなレベルの難しい問題を作れるからです。
だから、学習塾も予備校も、数学と英語に力を入れています。そして、国語には力を入れていません。
国語は差がつきにくいから力を入れないということもありますが、それ以上に、勉強をさせてても力がつかないから、塾でも予備校でも力を入れられないのです。
もちろん、受験指導をするという建前上、塾や予備校は一応国語も教えるようにはなっています。しかし、国語は教えても力がほとんどつかないとわかっているので、問題集をやらせて解説を詳しくするような勉強しかしていません。
国語力をつけるとうたっているところも、せいぜい解き方のコツを教える程度の指導です。解き方のコツがわかると、確かにある程度の点数は上がります。しかし、それは国語力がついたのではありません。
国語力は、実は国語のテストではあまり測ることができません。
本当の国語力は○×式のテストではなく、文章を読み、それをもとに文章を書かせることでわかるからです。
だから、今後、このような国語の試験が増えてくると思います。
本当の国語力は、受験のときにも役立ちますが、それ以上に社会に出てからも役に立ちます。
数学や英語の場合は、社会に出てからはあまり使わない人もいます。逆に、仕事などで使う場合は、学生時代さぼっていた人でもがんばれば比較的短期間で身につけることができます。
これに対して国語力は、社会に出るといやがうえにも使わざるをえなくなります。
文章を読むことでも、書くことでも、話し合いをすることでも、考えることでも、すべて広義の国語力が必要です。
しかも、こういう国語力は、必要になったからといって短期間では身につけることができないのです。
だから、子供時代の国語の勉強は、国語の成績を上げるということももちろん大事ですが、それよりももっと大事なのは、読む力、書く力、考える力をつけるといことを考えていくといいのです。
そういう国語力は、問題集を解くような勉強法では、決して身につきません。
実際に文章を読み、考え、文章書くことによって身につくのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
国語力と国語の成績は少し違います。
国語の成績は、解き方のコツによって上げることができますが、国語力は毎日の読み書きによってしか上げることはできません。
そして、国語の成績は、国語力によって上限が決まってくるのです。
受験に役立つのは、国語の成績と国語力の両方ですが、社会に出てからも役に立つのは国語力の方です。
だから、国語の勉強は、成績を上げるだけでなく国語力をつけるつもりで取り組んでいくといいのです。
はじめまして。いつも森川様の記事を楽しく拝読させて頂いております。
現在私は30代前半の社会人ですが、子どもの頃から国語が苦手で、今の仕事でもとても苦労しています。
色々記事を参考にさせて頂き、国語力の向上のために本の暗唱を毎日しております。本は、三木清の『哲学入門』です。300字くらいに区切って、毎日100回音読し、10日間で同じ文章を計千回音読しています。
ただ、私のように30過ぎてもこのように暗唱していけば国語力は向上していくのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
サムさん、こんにちは。
読んでいただいてありがとうございます。
読むのは自分の興味のある本ですから、「哲学入門」が好きならそれはそれでいいと思います。
しかし、300字を100回は長すぎます。
何事も続けて6ヶ月ぐらいたつと、効果がわかってきます。
もっと短い時間(10分ぐらい)でできるやり方にして、半年継続を目安にしていくといいです。
それから、国語力の基本は多読と難読(復読)ですから、その音読暗唱と並行して、自分が楽しく読める本を1日50ページ以上を目標にして読んでいくといいです。
がんばってください。
ご回答ありがとうございました。
そうですね、結構長い気がしますので、毎日の暗唱する分量を減らして多読と並行してやっていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました!
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

日本の寺子屋式の勉強は、従来の欧米式の勉強に比べると、一歩も二歩も進んでいる勉強法です。
現在、学校教育の中で教育格差が拡大しているのは、その教育が欧米式の教育だからです。
欧米式の教育とは、等質の生徒集団を前提として、先生が一方的に教える形で理解させ、理解度をテストで評価し、競争で意欲づけを図るという教育です。
その教育の前提となる社会は、成績が学歴と結びつき、学歴が社会的地位と結びつくという画一的な価値観が中心となっていた社会です。
戦後しばらくの間は、子供たちは黙っていても勉強する動機がありました。それは、成績が地位と結びつくという社会の価値観があったからです。そして、家庭環境は誰もが等しく貧しいというところで等質でした。
しかし、その後、受験塾が登場すると、勉強は受験のためのテクニックを必要とするようになりました。
また、昔は読書とラジオぐらいしかなかった室内の娯楽が、テレビ、ゲーム、インターネット、SNSと多様化すると、娯楽に多くの時間を取られる子も出てきました。
その結果、等質集団という前提が崩れてきたのです。
欧米式教育は、できすぎる子と、できなさすぎる子には対応できません。誰もが同じ程度であるときにだけしか効果を発揮できない勉強法です。
そして、世界の子供たちを取り巻く環境は、社会が貧しいときは等質なので、欧米式の学校教育も効果的ですが、社会が豊かになるにつれて、日本と同じように等質性が崩れてくるはずなのです。
昔は、等質の生徒集団を、単一の教科書で、一人の担任が教えていました。また、社会全体が教育に求める価値観も共通していました。
この時期が、欧米式教育の成功していた時期です。
今は、多様な生徒集団を、多様な教材で、多様な塾がそれぞれに教えています。しかし、先生が教えるという形を前提にすると、欧米式教育を効果的にするためには、少人数学級や習熟度別クラスや個別指導で、等質の集団を細分化する形で作り直さなければならなくなります。
そして、この多様性を多様性のままに教えるための仕組みづくりの一つとして、ICT教育が期待されているのです。
しかし、江戸時代の寺子屋教育は、コンピュータのない時代に、多様性を多様性のままに教えるシステムを作りだしていました。
なぜそれができたかというと、自学自習の方法が確立されていたからです。つまり、今で言う義務教育の年齢では、学ぶべきものはほぼ確定しているので、先生が多様な生徒を一律に教えるのではなく、生徒が自分の進度に合わせて教材を学習し、先生はそれを見守るだけで、ときどき進度の段階を決め直すという仕組みができていたのです。
しかも、寺子屋教育の利点は、ICT教育のように人間がコンピュータと向き合う孤独な勉強ではなく、集団の中で勉強するという集団の力学も生かしたものだった点にあります。
その自学自習を進める勉強の一つの方法が、限られた一つの教材を音読によって徹底して反復し身につけるという方法でした。
つまり、義務教育段階の学力は、理解による方法ではなく、反復による方法で身につければよいという教育観が確立していたのです。
この寺子屋教育の勉強法をインターネットを活用して現代に生かし、更に、創造性を高める作文教育に結びつけていくというのが、言葉の森がこれから考えている教育のビジョンです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
日本の寺子屋式勉強法のひとつの名残りが九九の暗唱です。
欧米では、九九を理解によって一覧表などを使って覚えようとするので、できる子とできない子の差が生まれ、できる子でも大してできるようにはなりません。
義務教育段階のあらゆる勉強は、九九と同じです。
しかし、九九は学校の勉強だけではできるようにはなりません。
ここが、学校と寺子屋の教育法の違いなのです。
なぜ学校だけでは、九九ができるようにならないかというと、学校は理解の場になっているからです。
教育の本質は慣れなのですが、学校は理解させる場になっています。そして、その理解を教えるのが先生の役割です。
では、慣れはどこで身につけるかというと、家庭での宿題か、学校のあともうひとつの塾か、又はその塾で出された宿題かなのです。
かつての寺子屋では、理解ではなく最初から慣れを身につけさせる教育法が確立していました。それが、限られた教材と音読による反復と集団の中での学習というシステムでした。先生の役割は、教えることではなく、そのシステムをメンテナンスすることだったのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)
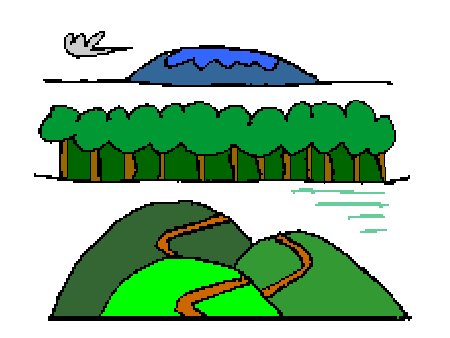
言葉の森は、昔、作文だけを教える作文教室としてスタートしました。
「創造性を育てる作文」というのが指導の目標でしたから、当初は国語の勉強などは度外視していました。今でも漢字の書き取りなどには力を入れていません。
それは、国語とか漢字とか、あるいか算数数学の勉強とか英語の勉強とかいうものは、答えも勉強の仕方もはっきりしているものですから、わざわざ人に教えてもらうようなものでないと考えていたからです。
しかし、創造性を育てるといっても抽象的で、具体的にどういう勉強が創造性を育てるのかわかりません。
そこで、いろいろな試行錯誤の結果、今は、音読で語彙力をつける、暗唱で文章を丸ごと理解する力をつける、構成と項目を意識して書く、プレゼン作文で発表と交流の機会を作る、というような方法で指導するようにしています。
また、作文の評価はどうしても主観的になるので、客観的な評価ができるように、森リンという自動採点ソフトを開発しました。特許庁の検索のページ(
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage )で、「言葉の森」と検索すると表示されます。
そして、この自動採点ソフトの点数と、小1から高3までの構成・項目指導の評価を組み合わせて作文検定試験を行うようにしました。
作文の勉強というものは心理的な負担の大きいものなので、なかなか独学で続けることができません。
だから、夏休みの感想文の宿題なども、締め切りギリギリにならないと書け出せないという子が多いのです。
そこで、言葉の森では、開設当初から事前指導に力を入れ、作文を書く前に10分間、先生がその子に合わせて説明するという方法で指導するようにしました。
一般の作文指導はこの逆で、事前に何の指導もないか、あるいは全員一律の指導があるだけで、子供たちに作文を書かせます。そして、書いたあとに赤ペンで詳しく添削します。
赤ペンの添削がたくさんあると、いろいろ教えられているような気がしますが、その添削を生かせる子はまずいません。
作文は、事前指導でなければ力がつかないのです。
言葉の森の作文指導は、書く人の立場に立った系統的なものなので、小1から始めて高3あるいは大学生、社会人になるまで続ける人がよくいます。
そういう人たちは、書くことが苦にならないのはもちろん、書くこと、読むこと、考えることが好きな、個性のはっきりした人になるようです。
ところが、このように順調に勉強を続けられない人も一部にいることに、最初のころから気づいていました。
それは、例えば、読書の習慣がない子、簡単な本しか読まない子、長文の音読をして来ない子、その結果親子の対話もない子、暗唱が続けられない子などです。
更に、作文や国語だけでなく、算数や数学の勉強でも、通信教材を漠然とやるだけだったり、塾に行っているという理由で家庭学習の習慣がなかったりする子などもいました。
また、小学生なのに、勉強が忙しくて読書の時間がとれないという逆立ちした勉強の仕方をしている子もいました。
もちろん、その反対に、中学入試や高校入試や大学入試の受験の直前まで作文の勉強を続け、読書の生活も続け、受験にも合格し、合格後またすぐ作文の勉強を開始するという子もいました。
この差は、能力の差ではなく、家庭学習や家庭環境の差だと思ったのです。
しかし、教室では、家庭学習まではコントロールできません。
「長文ちゃんと読んでくるんだよ。そしてできればお父さんやお母さんに取材してくるんだよ」と前の週に言っているのに、その週になると、「まだ読んでいませんでした」となってしまう子は、やはり密度の濃い勉強はできません。
それは、やむを得ないことだと思っていました。教室では、家庭での過ごし方まで関与できないからです。
ところが、インターネットの技術の発達で、クラウドサービスのひとつとして、教室と家庭を結びつける学習指導ができるようになったのです。
それが、今行っている寺子屋オンエアです。
生徒は、自宅で自分の好きな時間に勉強を始めます。
しかし、勉強の仕方を知らない子がほとんどなので、言葉の森の方で国数英の指定の教材を決め、その勉強の方法も決めておきます。もちろん、自分のやりたい教材でやってもかまいません。
勉強時間は約1時間ですが、低学年の生徒は自由に時間を短くできます。
予定の勉強が終わると、読書をして先生の電話を待つようにしています。これで、読書習慣のない子でも、毎日本を読む習慣がつきました。
勉強している間は、先生や同じ時間に勉強している友達が見えるので、自然に勉強する雰囲気で集中して取り組めます。
勉強が終わると、先生がその日の感想を聞いたり質問をしたり雑談をしたりします。電話だけでなく顔も見えるので、話が弾みやすくなります。
生徒がその日に音読したものは、録画して先生に送るようにしているので、音読の習慣もつきます。
こういう形で毎日勉強をしていると、確実に力がつきます。
勉強は、塾に週何日か通ったり、通信教材をひととおりやったりするよりも、毎日の自学自習を続けることで本当の力がついてくるからです。
なぜかというと、塾や通信教材の勉強は、わかることもわからないことも同じようにやるので、わかることをやっている時間は無駄になり、逆にわからないことはいつまでもわからないままになることが多いからです。
小学校低中学年のときは、勉強自体が易しいので、こういう勉強法でも力がつきますが、高学年になると塾や通信教材の勉強ではなかなか力がつきません。力をつけるためには、無駄を承知で勉強の時間を長くするか、自分なりにわからない問題を反復する仕組みを作らなければなりません。しかし、そういう仕組みを作れるような子は、自学自習で勉強できる子なのです。
寺オンは、この家庭での自学自習になるのです。自学自習を先生がアドバイスする形の勉強なので、家庭学習のいいところと通学教室のいいところを兼ね備えた勉強になります。
寺オンの応用形態として、作文の勉強と寺オンの勉強を結びつけることもできます。
作文の勉強で、10分間の事前指導を受け、そのまま寺オン上で作文を書き、作文が終わったら他の勉強や読書をし、勉強が終わったときにまた先生から10分間の話があるという形です。
その間、生徒は先生とずっとつながっているので、先生もその子がどういう感じで作文を書いているかがわかります。
また、ネットワーク環境があると、プレゼン作文発表会などの生徒どうしの交流の企画もすぐに行えるようになります。
夏合宿などのリアルな交流も並行して行えば、ほとんど自宅にいながらにして、勉強も交流もできる充実した教育環境ができます。
インターネットを利用した教育ですから、この寺オンの勉強を日本国内だけでなく、海外にも広げていくことができます。
作文指導は、既に海外の生徒を対象にして行っているので、時差の問題さえ解決できれば、寺オンも海外生徒対象に行うことができます。
海外の場合、最初は海外の日本人の子供が対象ですが、将来は、日本語を勉強したいという外国人も生徒の対象になります。
すると、そういう海外の生徒を、ホームステイなどで日本に滞在させる形で受け入れる場所も必要になります。
それが「森の学校」という構想です。
そこは、もちろん日本国内の生徒も、寺子屋合宿の場所として利用できます。
以上の作文と寺オンのシステムは、教材を送るのに宅急便を使うような場面以外は、ほとんどすべてインターネットを基盤としているので、どこでも立ち上げることができます。
例えば、世界中の生徒を、三浦半島の海と山に近い静かな場所に森の学校を作り、そこから教えるということもできるのです。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
「教育が変わらなければならない」と考えている人は多いと思います。
しかし、何をどう変えるのかというと、それぞれの人が主観的に勉強の内容をどう変えたいかと言っていることが多いのです。
歴史の勉強をもっと人間的な感動のあるものにしたいとか、国語の教材をもっと明るく前向きなものにしたいとか、道徳の教科に力を入れたいとかいうことは、それぞれに大事なことです。
しかし、本当に変えなければならないのは、勉強の内容よりも勉強の方法です。
教えてもらう勉強ではなく、自ら学ぶ勉強にしなければ、教育の根本は変わらないのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)